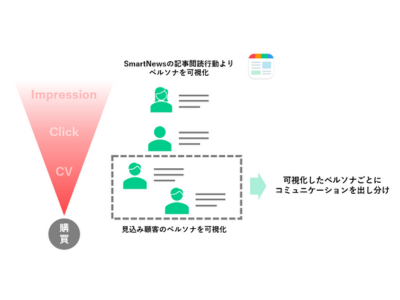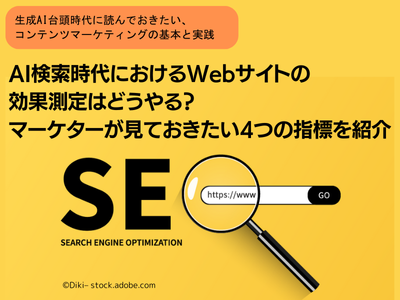会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
新規会員登録無料のご案内
- ・全ての過去記事が閲覧できます
※プレミアム記事(有料)は除く - ・会員限定メルマガを受信できます
- ・翔泳社の本が買える!500円分のポイントをプレゼント
この記事は参考になりましたか?
- 事業と人を成長させる「強み」起点のマーケティング思考連載記事一覧
-
- 戦略の質は「初期仮説」で決まる。元リクルートVP直伝・最速で“勝ち筋”を見つける「サーチラ...
- マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える...
- AI時代のマーケティング戦略。「変わらない」非合理性の理解と、「変わる」LLMOへの備え
- この記事の著者
-

金井 統(カナイ オサム)
NexGen Inc. CEO
新卒でNTTドコモに入社。端末のマーケティングを経験した後、iモードでビジネス展開をする会社へのコンサルティングに従事。その後、リクルートへ転職。マーケティング室のVP(ヴァイスプレジデント)として、横断の人材育成・知見流通とHR領域のマーケティング責任者を担当。HR領域におけるToC及びToB双方のプロダクト横断での事業・マーケティング戦略、ブランディングからdirectADやSEO等のネットマーケティング、...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア