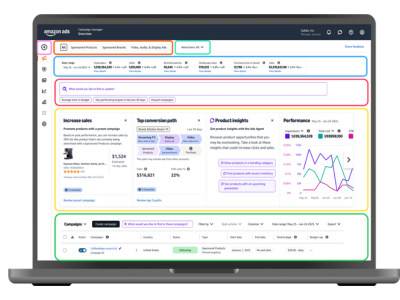非構造化データに「宝」が眠っている
坂部氏はここで新たな問いを投げかける。「AIエージェントが台頭する中、真の顧客理解とはどのようなものなのか」と。生活者の人格を宿したAIエージェントとの対話なのか、顧客の実際の行動データの分析なのか、生身の顧客の声に耳を傾けることなのか。山崎氏は「それらすべてを繰り返すことが真の顧客理解である」と回答する。

「LLMは非構造化データの処理を得意としています。つまり、顧客アンケートの結果やコールセンターの通話記録などに宝が眠っているのです。どのようなデータを使えば自社のお客様を解像度高く理解できるのか。この点を整理した上でAIエージェントに学習させると、アウトプットは様変わりします。データの精査と学習のサイクルを繰り返しながら、トライアンドエラーを繰り返すことがポイントです」(山崎氏)
AIエージェントの浸透によって、マーケティングはどう変わっていくのだろうか。坂部氏の質問に対し、山崎氏は「マーケターの担う役割が変わる」と予想する。
「マルチエージェント化が進めば、マーケターの役割は『どのエージェントを呼び出して、いかなるディスカッションするか』というオーケストレーションに変わっていくでしょう。そのため、マーケターは生成AIや顧客に対する理解はもちろん、マルチエージェントの仕組み全体についても理解を深めてプランニングする必要があります」(山崎氏)
顧客データ中心経営の心得とは
一方の牧野氏は「長い目で見れば企業の在り方自体が変わる」と回答。顧客中心経営から顧客“データ”中心経営へと既に変わりつつある中、これまでは業務別に縦割りで部門が分かれていた組織も、今後はコンテクストデータ中心の横断的な組織体制に組み替えられる可能性があるという。

「現在は業種や商品のジャンルによって企業の特性が分類されていますが、これも今後は商品ジャンルを横断して『どのようなコンテクストを作れるのか』という横断的な観点で企業が分類される気がしています。マーケティングにとどまらず、経営も変わっていく意識です」(牧野氏)
最後にパネリストの両名は次のようなメッセージを参加者に残し、セッションを締めくくった。
「AIとかれこれ10年以上向き合っていますが、ここ一年の進化は目覚ましいです。変化を楽しみ、受け入れ、理解する力に加え、周囲を巻き込む力を養うと良いのではないでしょうか。周囲を巻き込めば、専門家を頼ることもできます。AIエージェントが事を起こすきっかけを与えてくれるかもしれません。皆さんにも変化を楽しみながら、イノベーションを起こしていただきたいです」(山崎氏)
「AIエージェントの台頭によって、自身のロールが変わることに不安を覚える方もいらっしゃると思います。ただ、自分がやりたいことにフォーカスできるタイミングとも言えるのではないでしょうか。企業間を隔てる垣根もAIによって変わってくるはずですから、ロールや企業の枠に縛られず、おもしろいものを皆さんと作っていきたいです」(牧野氏)