【誤解2】「このサービスの価値はゲーミフィケーションにある」
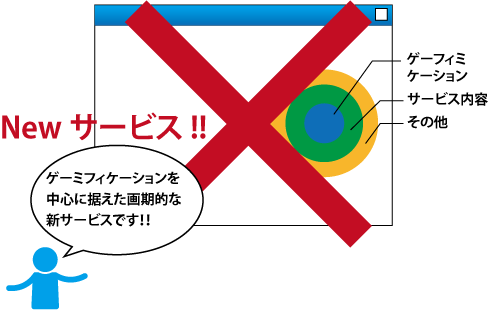
こちらは、【誤解1】とは全く反対の観点での誤解です。“サービスの根本の価値をゲーミフィケーションにある”とするような考え方を指しています。BtoC型のサービスを新規に立ち上げる際に、ゲーミフィケーションを導入しようとしているケースは最近非常に多く目にするようになりました。中には、「ゲーム要素を取り入れること自体が、このサービスの価値だ」と考えているかのようなサービスも散見されます。
前述したように、ゲーミフィケーションが有効に機能するのは、サービス自体がユーザーにとって意味のある価値を提供していることが大前提となります。ゲーミフィケーションそのものが重要な差別化要素として機能することはあり得ますが、それ自体がサービス本来の価値となるものではありません。
著者自身がよく取り上げる例で説明すれば、回転寿司の「くらずし」は“おいしいお寿司が安価に提供されている”からこそ、ビックらポンが機能しているのです。ANAは“飛行機の搭乗体験が十分に満足のいくものである”からこそ、マイレージに意味があるのです。ユーザーが“ランニングの意義を十分に理解できている”からこそ、Nike+は機能します。
ゲーミフィケーション自体はこうした価値を代替することはできませんし、そもそも、そういうものではありません。ゲーミフィケーション・フレームワークで目的設定の重要性を説明しているのは、こうした誤解を防ぎたいという意図も込めています。
特に新たにサービスを立ち上げる際、この誤解に陥らないよう、まずそのサービス自体の価値が何なのかということを踏まえた上でゲーミフィケーション・デザインに取り組むようにしてみてください。
【誤解3】「ネガティブ商材には合わない」
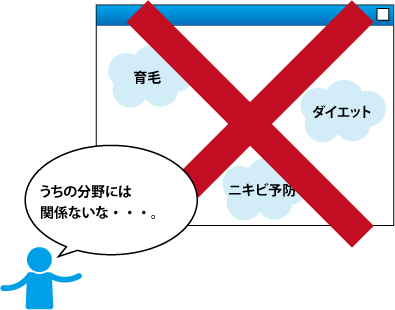
「ネガティブ商材」とは一般的な用語ではないかもしれませんが、その商材を購入したことを必ずしも人には知られたくないような種類の商材を指していると考えてください。典型的な例としては、ダイエット系の商材や毛髪育成系の商材などが該当します。
“エンターテイメントさせる”という発想と合わないのではないか、という観点からの誤解かと推測しますが、ゲーミフィケーションは必ずしもエンターテイメント的な手法・見せ方でのみ実践するわけではありません。よりシリアスなシーンや、笑いや娯楽といった要素と縁遠い場面であっても、ゲーム要素は有効に使うことができます。ある意味、航空会社のマイレージプログラムはゲーム要素を取り入れてこそいますが、エンターテイメント的な見せ方にはなっていない例として捉えることができます。
ネガティブ商材における合う・合わないは、ゲーミフィケーションというよりも、“ソーシャル性をどのように使うか”という点に最も影響されるでしょう。
現実の知人と共有したくない話題でも、匿名性が担保されているのであれば同じ悩みを共有している人とつながりたい、というユーザーは、ネガティブ商材では多く見られるのではないでしょうか? このような場合には、匿名のままでソーシャルグラフが利用できるようなソーシャルアクションをデザインすることで、ゲーミフィケーションを機能させることができます。米国ではソーシャルグラフの活用と言えば事実上Facebook、そして実名制が前提となりますが、日本では必ずしも実名性を前提とする必要はありません。


































