ユーザーの声からつくられているLINE
LINEのサービスはソーシャルリスニングでユーザーの声を拾い上げ、ユーザーのにニーズがどこにあるのかを探りながら、チューニングされている。ユーザーの声を集めるために、情報発信を積極的に行い、TwitterやFacebookなどのソーシャルメディア上でユーザーの声を収集する。そこから得たフィードバックをサービスに戻すというPDCAサイクルを高速で回している。
「この仕事は、毎日やっているからこそ、微妙なユーザーの変化、だんだん大きくなっているユーザーの声に気付くことができます。常に見ているからこそ、わかりますね。例えば、常に1時間あたり5人くらいのユーザーが言っていることが、急に50人くらいに増えた時に、緊急で各担当者に確認や対応をしてもらうように情報を共有したり。たとえ1人だけでも、こんな声があると、担当者がわかるように社内に日々情報を共有します」(金子さん)
ユーザーの声やニーズを拾う秘訣をたずねたところ、「基本的に全部見るようにしています」と金子さん。
「拾えるかぎり、見れる限りですね。なるべく幅広く、全部ひろって、社内みんなに共有できるようにしています。最近はユーザー数が増えて、いろんな国で使われるようになったので、グローバルなコメントを全部カバーしていくのは課題でもありますね。ユーザーのコメントの数も増え、幅も大きくなっているのでそこに対応していくことが課題です」(金子さん)
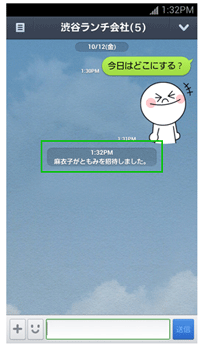
また、広くソーシャルメディアを通じて拾い上げたユーザーの声を、LINEの新しい機能として実装し、ユーザーが求めるサービスのかたちへLINEを変えている。
「最近だと、LINEのグループトークの機能に、ユーザーの声から機能が追加されました」(金子さん)
グループトークとは複数人(最大100人まで)が1つの画面でトークをすることができる機能。学生などのユーザーから、誰が誰を招待または削除したのかがグループメンバー全員に対して表示されるようにしてほしいという声が寄せられ、対応したとのこと。
「このような細かい機能や設定こそ、ユーザーの要望をもとにして機能を実装していっています」と金子さんは語る。このようなユーザーとのコミュニケーションが積み重なり、ユーザーの声が活かされたサービスが作り上げられていく。また、マーケティングチーム内だけでなく、企画開発チームやデザイナーチームまで、全員で共有している姿勢はNHN Japanの文化であり強みなのだろう。
広告は時間を短縮するもの
NHN Japanのマーケティング戦略についてうかがった。
「私たちの基本的な考え方として、広告は時間を短縮するもの。本質的に競争力があるものに対しては、テレビCMなどのマス広告で一気にリーチを稼げばその分だけ使ってくれるユーザーが増えるでしょう。逆に競争力がないものに対しては、いくら広告コストをかけてもユーザーは固定化しない。
まずはしっかり情報発信をして、ユーザーとコミュニケーションをして、フィードバックをもらう。このプロセスを地道に続けていくことで、コアなファン層ができる。その段階で初めてそのサービスに競争力があるのか判断できる。土台になるファンベースがあれば、マス広告をやる意味はあるし、逆にいえばゼロベースでマス広告施策をしても意味がない」(矢嶋氏)

テレビCMの本当の効果
LINEの国内ユーザー数を伸ばす大きな成功要因として、ベッキーのテレビCMは有名だ。このテレビCM施策の効果は、ただ新規ユーザーを伸ばしたという表面的なものではない。
「テレビCMで、新規のユーザーも当然増えましたが、どちらかというと『もともと使っていたユーザーが友達に進めやすくなった』というのが大きい。テレビCMを打って、無料通話というわかりやすい機能があって。CMによって『ベッキーのCMのやつだよ、無料通話のアプリだよ』って既存のユーザーが友達に紹介しやすくなった。そこでコアなファン層たちが一気に立ち上がって、LINEを広めてくれるようになったことが大きい」(矢嶋氏)
テレビCMの効果はLINEというサービスの認知をを高めただけではなく、既存のサービスのファンが自分たちの友人に紹介しやすい環境をもつくった。つまり、ここでも中東で起きたようなポジティブなスパイラルが起こったのだ。そして既存のユーザーを長期的なファンへ成長させた。


































