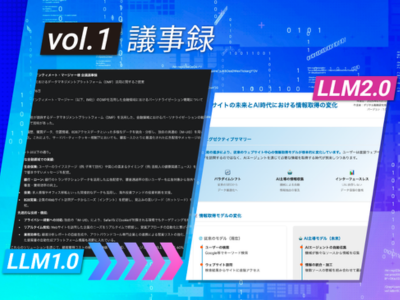「できないことをもはや技術のせいにできなくなった」マーケターに投げかけられた課題とは?【Adobe Summit2013:ユーザー特別対談】
会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
新規会員登録無料のご案内
- ・全ての過去記事が閲覧できます
※プレミアム記事(有料)は除く - ・会員限定メルマガを受信できます
- ・翔泳社の本が買える!500円分のポイントをプレゼント
-
- Page 1
-
- Page 3
この記事は参考になりましたか?
- 世界各国のマーケターがSLCに集結!「Adobe Digital Marketing Summit 2013」連載記事一覧
-
- 「できないことをもはや技術のせいにできなくなった」マーケターに投げかけられた課題とは?【A...
- モバイル・ソーシャル・オーディエンスデータの切り口から見る米国デジタル広告最新事情
- 楽天経済圏における、グローバルウェブ解析ガバナンス戦略に迫る!
- この記事の著者
-

大山 忍(オオヤマ シノブ)
米国大学卒業。外資系企業を経て2000年にネット広告効果測定ツールを提供するベンチャーに創業メンバーとして参画。その後、バリューコマース株式会社と合併し、アフィリエイトシステムの開発企画やマーケティングマネージャーを務める。
2007年1月にオムニチュア株式会社(現Adobe)に参加、コンサルティングサービスを立ち上げる。ビジネスコンサルタントとして米国のベストプラクティスを日本の課題やニーズに合わせて提供、ウェブ解析やガバナンス(データ主導の組織・仕組化)...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア