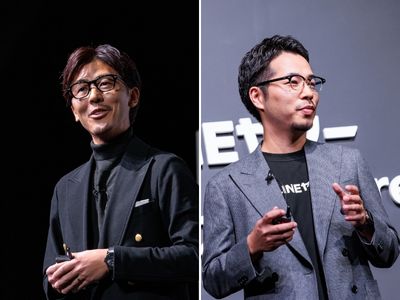データ活用に工夫の余地があるほど、インパクトを生み出す可能性もある
MZ:今の話を踏まえて、人工知能やAIという言葉が頻繁に使われるようになって、ある種、昔のインターネットのように「よくわからないけれど、何か色々とやってくれるのではないか」という過度な期待を持ってしまうケースもあると思います。それは怖いことだと思います。ディープラーニングなどを活用したい、コラボレーションをしたいと考える場合にどのような点に注意すべきだと思いますか?
得丸:「何のためか」という目的意識を持つことが大前提ですね。データをやみくもに集めても、何かできるわけではない。何のために何のデータを集めるのかを、最初に考えることが重要だと思います。昔は目標があってもコストの面で断念していたことも、テクノロジーが大きく変えようとしている。技術がもたらしたベネフィットをどうしたら先手先手で活用できるかを考える事が、企業の競争力の差を生むでしょう。
田場:コミュニケーションの視点でいくと、データを読み解いて分析して、仮説でもいいから未来のストーリーを作れる人が鍵になると思います。過去のデータを見て現状を理解しても、その先をこうしていこうという視点でストーリーをうまく立てられないケースは少なく無いと思います。データを一生懸命集めるけれど、活用の仕方がよくわからない。だから、とりあえずデータをもっと集めようといった流れがあります。
未来を見据えてコミュニケーションや消費者と企業側の接点を考えられる人がいないために、本当は意味のあるデータも、意味がないものになってしまうことは意外と多いのです。
松田:テクノロジーの面では、どうしても研究と実企業の間にはギャップが出てしまいます。企業は、テクノロジーがあって研究も進んでいることは知っているけれど使い方がわからない、というのが現状だと思います。この間を埋めるのが私達のような会社。
プロジェクトの成功の決め手の多くは最初の目的設定だと思います。その目標に対して「この方法が現実的です・これはできません」といったテクノロジー活用の線引きが必要。そこを他の企業さんと一緒にやっていければと思います。
MZ:ちなみに、いわゆる宣伝広告に目を向けた時、テクノロジーとコラボレーションすることによってアプローチの型に変化はあるのでしょうか?
田場:クリエイティブとは、課題を見つけて解決することですから、本来の意味により近づいてきたと思います。いつの間にかクリエイティブという言葉が、広告、広く伝えるという話と同一視されてしまった。けれど、それだけが問題の解決ではありません。技術の進化で手段が増えたことで、やっと本来のクリエイティブの姿に戻っていくっているきがします。
MZ:問題解決となると、企業が何を解決しているのかが明確になってないといけないと思います。これは、目的意識と重なる部分が出てきそうですね。
田場:そうですね。ですから私達もなるべくクライアントとなる企業とディスカッション型で仕事をすすめるよう意識をしています。要件をもらって何かを返す従来のやり方ではなく、お互いの知見や思っていることを出し合うことで本当の課題を見つけ出したり、解決策を出したりできるのです。
MZ:現状の課題を見つけるためにはデータが重要な役割を担いそうです。となると、やはりデータ活用が上手な企業が先に進むように思います。
得丸:逆説的ですが、現状ではデータを使いこなせていない、あるいは工夫の余地があるほうが、大きなインパクトを生み出すことができるかもしれません。私はそこにクリエイティビティをうまく融合させて、何か新しいバリューが生み出させないかと考えます。私たちは先日、石巻の1次産業とコラボレーションしたアイディアソンを行ったのですが、これも、新たな爆発を生むといった狙いもあります。
MZ:企業によってできることや段階は異なるかと思いますが、未来を見据えて目的を持ち、データをいかに入手し、活用していくかが重要なのですね。これを突き詰めると、自社だけで行うのか、他社と組むのかといった選択も検討材料になりうるのが、現在の状況なのだと思います。本日は、ありがとうございました。