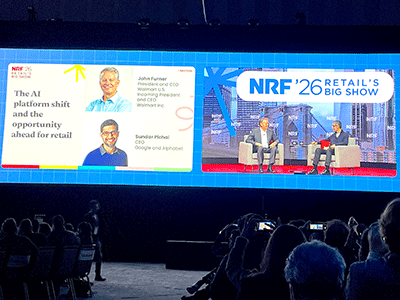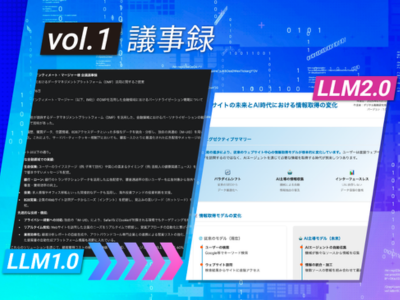デジタルの普及で「顧客」が見えづらくなっていった

株式会社ニューバランス ジャパン DTC&マーケティング ディレクター 鈴木健
大学卒業後、広告代理店のオリコムに入社。営業担当などを経て、戦略プランナーとしての職につく。その後はナイキジャパンでゴルフ部門の広告担当などを経験し、ニューバランス ジャパンに入社。現在はマーケティングのディレクターを務めるだけでなく、直営の店舗やEC事業も担当している。
――はじめに、「顧客体験(CX)」の概念がここまで広まった背景について伺えますか?
鈴木:順に時代の流れを追っていくと、まずデジタルが普及する以前の90年代当時は、「One to Oneマーケティング」がトレンドでした。インターネットが本格的に普及し始めたのは、95年以降。その頃はまだデジタルの存在感も弱く、テレビ広告などマス向けの施策を行っているような大きな事業会社でないと、広告やマーケティングを語ることが許されないといった風潮があったように思います。
どのような変遷をたどって「顧客体験」という言葉が台頭したのかまでは明言できませんが、「体験」という言葉を盛んに耳にするようになった背景にはデジタルの台頭があると思います。デジタルを起点とした顧客とのタッチポイントは、顧客行動が把握しづらい部分があります。数字やデータで顧客行動を理解すると言っても、あくまでそれはログ情報などでしかない。実店舗やイベントと違って、顧客が実際にどのような行動をして、何をどういう風に鑑賞しているのかまでは追いきれません。
そうした中で、「デジタルを活用した顧客とのコミュニケーションがどう機能しているのか」を具体的に理解する必要性が増してきたのだと思います。そこで、デジタルが普及する以前に特に重要視されていたキャッチコピーやクリエイティブの話ではなく、もう少し顧客との関係性を俯瞰して見るような視点を、総じて「体験」という言葉で表現するようになっていったのではないでしょうか。
――「UX」も同様に体験の意味を含む言葉ですが、「CX」とは何が違うのでしょうか?
鈴木:そうですね。デジタル領域では当初から「UX」という言葉は存在していました。ただ、こちらは現在の「CX」と同じ文脈で用いられることはなく、どちらかと言えばWebサイトにおけるユーザービリティなどを指して、「UI」とあわせて使われることが多かった印象です。「ユーザー」だと限定的なイメージを与えてしまうため、「顧客(Customer)」を採用して「顧客体験(Customer Experience)」という言葉が使われるようになったのだと推測します。
必要なのは、単なる機能を超えた「ひと工夫」
――御社は、プロダクトを展開する上でどのような「顧客体験」を考えていらっしゃいますか?
鈴木:たとえばランニングの市場を考えてみると、流行のサイクルが早いことを感じます。市場規模自体の変動はそこまでありませんが、その都度異なる顧客のニーズを捉えた体験設計が重要になってきます。
これまでランニングは、あまり進んで行うものとして捉えられていませんでした。たとえば、学校の部活動などでも、「罰として校庭を走らせる」といった文化があったと思います。
それが近年では、趣味としてランニングを選ぶ人が増えてきた。ここ10年ほどで顕著なのは、「ランニング=楽しい」という考え方が広く浸透してきたということです。こうした市場の変化にともなって、我々も販売するプロダクトの設計を入念に行っていく必要があります。
シューズのカラーをひとつ取っても、部活動での利用が主であればカラーバリエーションもいわゆる「部活感」のあるものが適切と言えます。ところが、趣味としての利用が増加している現在では、より自らのファッションに溶け込むようなカラーやデザインが求められます。

機能面で言えば、趣味でランニングする人たちのニーズは「走った後の達成感」を得ることだったりします。そのため、あえて反発力のある素材をシューズのミッドソールに採用することもあります。長距離のランニングであれば、楽に走れるクッション素材を使うことが多いのですが、日常的に30分~1時間程度しかランニングしない人たちにとってみれば、その反発力が「走った」という感覚につながり、達成感を醸成することができます。こうした機能面でのひと工夫を通して、顧客の感情面にも働きかけられる体験が設計できるわけです。