ルールに必要なのは「制限・シンプル・盛る」の3要素
――ルールを作る上で、意識している点はありますか。
良いルールには、3つの要素が必要だと思っています。1つ目は、制限をすることです。たとえば「54文字の文学賞」では、54文字ぴったりであることを応募資格としています。短文の小説と言っても、10文字からTwitter小説のような140文字と幅広いです。すると、スキルのある人とそうでない人の差が開いてしまって、応募のモチベーションが下がってしまう。実際、54文字という制限をかけることで参加ハードルを下げることができました。このように、多くの人に参加してもらうための制限は必要だと思っています。
2つ目は、キャンペーンや商品のネーミングをシンプルに表現することです。テキストを中心としたコミュニケーションにおいて、人から人へ伝播していくときに重要なのは言葉です。僕はこれを“流通する言葉”と呼んでいますが、シンプルであるほうが良い。
そして、シンプルな言葉同士の組み合わせで新しさを作るようにしています。たとえば、「54字」と「物語」という単語はそれぞれ普通の言葉ですが、「54字の物語」のように組み合わせると新鮮で、どんなものだろうと相手に想像させることができます。この「言葉はシンプルだけど初めて聞く」「いかに見たことのない感覚を作れるか」の視点を大事にしていますね。
これは、「ツッコミかるた」というカードゲームを作るときにも意識しました。このゲームは、フリートークをしながら自由にボケて、それに対するツッコミワードが書かれた札を取るというかるた遊びです。

「ツッコミ」と「かるた」という言葉の組み合わせは、聞いたことがないけどなんだかおもしろそうと感じますよね。このように言葉を洗練させて、自分の手元を離れても機能して広がっていく要素を大事にしています。
――3つ目はなんでしょうか。
3つ目は、「盛れる」ことです。これは、参加することで誰もがクリエイターの気分になれる工夫を指します。たとえば、単に54字のテキストをTwitterで投稿するだけではシェアされません。Twitterには、テキストを画像にして発信するという文化があります。それを参考に、「54文字の文学賞」では入力した文字が正方形の原稿用紙フォーマットに画像化され、投稿できるジェネレーターを開発しました。
そうすることで、どんな文章でも作品感が出て、自分が表現したという達成感や実感を持ってもらえました。どんな人でも最低限の満足度が得られるような設計を心がけています。
――確かに、簡単にそれらしいアウトプットができると嬉しいですね。
Twitter発で書籍化した『あたりまえポエム』も、きれいな背景素材に明朝体であたりまえのことを書くだけで、高尚な作品に見えてしまうという誰でも参加できる仕組みです。これを開発したことで、普段文章を書かない人でもルールに従って文字を書くと、作品のように見えて気分がアガるという状態を生み出せました。
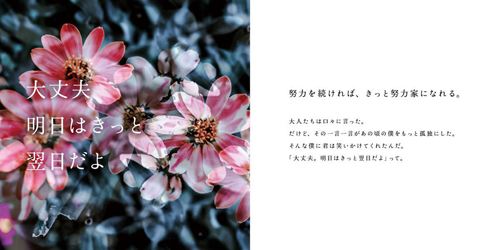
バズが生まれるプロダクトを作りたい
――様々なルールを作っていく中で、新しく気づいたことはありますか。
「54文字の文学賞」に投稿された作品の中には、僕が発信している物語よりもシェアされてバズったものもあります。正直悔しい気持ちもありますが、一方で才能のある人たちが世の中にたくさんいて、アウトプットする場や見せ方次第でその才能を多くの人に知らしめることができると気づいたんです。
元々ルール作りに着目したきっかけは、一方的に伝えるのではなく、様々な人が共感して代わりに発信してくれる仕組みを作りたいと思ったからです。そのような仕組みを世に出すため、一緒になって楽しんでもらえる、タイムライン上の人々が味方になってくれることを念頭に置いて企画を考えています。
――昨今、バズに対する成果を捉えるのが難しいと言われることが多く感じるのですが、氏田さんはどのように考えていますか。
僕もすごく悩んでいます。まだはっきりとした答えがあるわけではないのですが、商品ありきで「デジタルのコミュニケーションだけ考えてください」と言われるような仕事があると、とてももったいないと感じてしまいます。リツイートキャンペーンをしたり、おもしろいWebサイトを作ったりするなど、コミュニケーションの部分を設計するだけではできることも限られてしまいます。
まず、商品開発と広告を分ける必要があるのでしょうか。現在在籍しているチョコレイトでは、広告案件だけでなく、企業とブランドを育てるコンテンツも作りますし、オリジナルでコンテンツ制作も行っています。
――広告だけ考えていても、成果につながるバズは生みにくいと。
今は、まったく無名のグッズをYouTuberが紹介しただけで流行ることもあります。その中で、企業や作り手視点でコミュニケーションだけ考えて戦えるのかなと思ったんです。今や、広告代理店のプランナーがアイデアを集結させて予算を投下した動画よりも、一般人が投稿した動画のほうがバズります。
であれば、たとえば1本のペンを売るためにテレビCMをたくさん流すよりも、そもそもYouTuberやSNSユーザーに「このペンウケるんだけどwww」と投稿されるようなペンを作ったほうが早いんじゃないかと思っています。商品をどのようなコミュニケーションで売るかではなく、先にみんなが楽しめるルールから作り、商品開発をし、それに合わせたコンテンツを用意してコミュニケーションを取るほうが、自由度も高く、できることがたくさんあるはずです。ですので、プロダクトを作るところから関わる案件も増やしたいですね。




































