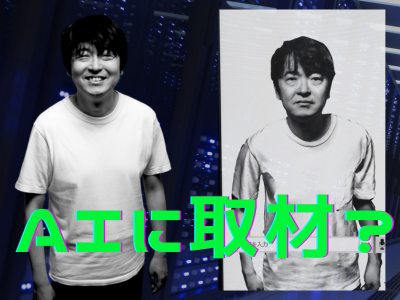「メディア」の産業構造を理解する
廣澤:今回、高広さんとの対談テーマは、「“メディア”とは何か」です。マーケティングに関わる人は、日常的に「メディア」という言葉を使いますが、立場によってその言葉の使い方が異なると感じることがあります。この違いが、マーケティングそのものの考え方やメディアリテラシーの低下につながっているのではないかと思うんです。高広さんはメディアをどのように捉えていますか。

右:株式会社スケダチ代表・社会情報大学院大学客員教授 高広 伯彦氏
高広:メディアを捉える視点というか定義の仕方はいくつかあると思っています。まず、今のメディアを“メディア産業”という視点で見た場合、そこには実は「メディア」と「プラットフォーム」という切り分けができます。ここで言うメディアは、すなわちコンテンツパブリッシャーであり、出版社や新聞社などを指します。これらはコンテンツを生み出す制作機能と、コンテンツを伝達するビークル(媒体)としての機能を併せ持ちます。一方で、プラットフォームとは、例えばFacebookやTwitter、YouTubeなどがそうですが、基本的にプラットフォーマーは自分たちでコンテンツを作りません。コンテンツを流通させる機能はありますが。
そして最近では、メディア内のコンテンツ制作機能の部分だけを切り出す形で、コンテンツパブリッシャーである新聞社が、広告主向けのコンテンツを制作する「ブランドスタジオ」と呼ばれる機能を立ち上げるといった例も出てきています。
また、もともと映画やテレビ業界のように、コンテンツ制作を専門とする「スタジオ」機能は外部化されている例もあります。これらの外部のスタジオは、今はNetflixやAmazon プライム・ビデオなどからも番組の制作依頼を受けています。先ほどの分類で言うと、両動画配信サービスもプラットフォームです。それらに対して従来映画会社やテレビ局に納品していたようなコンテンツを提供するような、大きなコンテンツスタジオが今は存在しています。
「インフルエンサーを買い上げる」がおかしい理由
廣澤:これまで広告・メディア業界で呼ばれてきた「メディア」は、コンテンツ制作とその配信がセットになっていましたが、プラットフォームが誕生し、スタジオなどとの区別が曖昧なままにまとめてメディアと呼んでいるのが現状ということですね。さらに、スタジオ以外にも個人がコンテンツを生産するということも起こっています。
高広:それも大きな変化ですね。様々なプラットフォームが登場したことで、コンテンツを個人がインターネット上で公開できるようになりました。言ってみれば、個人レベルでのコンテンツスタジオです。英語圏では、UGC(User Generated Content)と言いますが、日本語では、CGM(Consumer Generated Media)と呼ばれてますよね。日本では「インフルエンサーの誰々はメディアだ」というように、個人をメディアと考えるから、CGMという言葉になる。実際に生み出しているのはコンテンツなのでUGCのほうがふさわしいように思うのですが、このあたりも「メディア」という概念の捉え方をさらに曖昧なものにしているかもしれません。
廣澤:確かに、「インフルエンサーを買い上げる」という表現があるように、インフルエンサーなどもひっくるめてビークルと考えている気がします。
高広:メディア産業的観点でいえば、「コンテンツパブリッシャー」「コンテンツスタジオ+プラットフォーム」「UGC+プラットフォーム」という3つの見方がある。これらの見方を身につけるのは、企業のマーケターには重要なポイントです。そうすると、「個人をメディアとして買い上げるのはおこがましいのでは?」という視点も出てくるのではないかと思うんですが。

廣澤:広告を出稿する側にいるマーケターは、メディアと呼ばれるすべてを「お買い上げするもの」というイメージを持ちがちなので、こういった俯瞰的に見た理解が必要ですね。