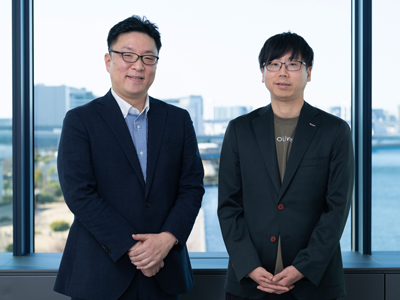「可処分精神」に着目し、タイアップを再定義

事業部長/レーベルヘッド 高野修平氏
――初めに、高野さんのお仕事について教えてください。
高野:トライバルメディアハウスのマーケティングレーベル「Modern Age/モダンエイジ」を統括しています。音楽やテレビなどのエンターテインメント業界のマーケティング支援と、音楽やエンターテインメントを活用したブランドのマーケティングやコミュニケーションを支援してきました。
その経験から、ブランドづくりにおける音楽やエンタメとのタイアップには大きな可能性を感じていて、マーケターは音楽やエンタメがもつ力を、もっと戦略的に活用できるはずと考えています。
――戦略的な活用とは、どういうことでしょうか。
高野:前提として、私たちは「情報大爆発」と言われる社会を生きていて、企業のメッセージはますます届きにくくなっていますよね。このためマーケティング活動は、生活者の心の中をいかに占有するかという勝負、つまり「可処分精神」の奪い合いになりつつあるのです。
「可処分精神」は、SHOWROOM代表の前田裕二さんがインタビュー記事(東洋経済オンライン「前田裕二『可処分精神を奪い合う時代が来る』」)の中で発した言葉ですが、私はこれを「つい、そのことばかり考えてしまうもの」、「自分の人生においてなくてはならないもの」、そして「生きる活力になるもの」と解釈しています。
これまで私たちマーケターは、いかに生活者の可処分時間や可処分所得を獲得するかについて議論を重ねてきましたが、コンテンツがあふれている今、より上位にある「精神」を押さえることが重要になってきているということです。
――確かに心を占めることができれば、結果として時間もお金も費やしてもらうことができますね。
高野:はい。しかしそこに到達できるブランドはほとんどないのが現実です。実際に「つい、そのことばかり考えてしまう」企業やブランドを挙げてほしいと言われても、なかなか浮かばないのではないでしょうか。
一方、アイドルや音楽、漫画や映画などエンタメの多くは、そもそもファンの可処分精神を占めることで成り立っていて、人を惹きつけ、熱狂させる強い力をもっています。
とあるアーティストのファンであれば、そのアーティストの活動をSNSで毎日チェックし、ライブ発表があれば、ファンコミュニティを回遊して情報収集や情報交換をして、ライブチケットやグッズを手に入れる。まさに「つい、そのことばかり考えてしまう」状況で、限られた時間とお金を費やしています。
ブランドと音楽・エンタメがタッグを組むこと自体は、目新しいことではありません。しかし可処分精神の獲得という観点に着目し、時代性を踏まえながら、タイアップの意義を構築し直すことで、双方にとってより高い価値を生み出していけると考えています。
エンタメへの愛をブランドに転化する「タイアップ2.0」
――タイアップの再定義についてうかがう前に、そもそもブランドが音楽やエンタメと組む目的について、改めて教えていただけますか。
高野:「可処分精神の転化」と「ファネルを飛び越える力」の2つに集約されると思います。
「可処分精神の転化」というのは、人々の可処分精神を占めている音楽やエンタメとコラボすることで、そのコンテンツのファンを自らのブランドやプロダクトのファンへと転化させるケースです。
「ファネルを飛び越える力」については、アーティストやアニメとのコラボ商品が即完売する例をイメージしていただければと思います。ブランドは認知・興味・比較検討……とマーケティングファネルに対して個別最適化したアプローチを試みるのが通例ですが、音楽やエンタメとコラボした場合、ファンは認知した瞬間に比較検討を飛び越えて購入、さらに商品を推奨する役割まで担ってくれることもあります。

――2つの目的を達成するために、これまでのタイアップはどのようにアプローチしていたのでしょうか。
高野:これまでに多く見られたタイアップは、短期的なプロモーションのために用いられることが多く、限定のコラボ商品やテレビCMのタイアップなどが該当します。どちらかというと「ファネルを飛び越える力」を重視していて、短期的な売り上げに寄与するという効果はあるのですが、それ以上の広がりを生みづらい。
たとえば好きなアーティストと一度だけコラボしていた商品のブランドに、あなたは好感をもち続けるでしょうか。その時の好感度は上がるかもしれませんが、タイアップが終わると元に戻ってしまうことが多いはずです。つまり、「可処分精神の転化」という目的はこれまでの手法では達成することが難しい。
これが従来型の「タイアップ1.0」であるのに対し、ブランディングを目的としてより長期的な視点で音楽やエンタメを活用し、ブランドへの可処分精神の転化を図っていく。こうした取り組みを私たちは「タイアップ2.0」と呼んでいます。
なお「タイアップ1.0」と「タイアップ2.0」に優劣があるというわけではなく、その時々の企業やプロダクトの課題によって使い分けることが重要です。
他社が短期的に追いつけない、強いブランドを醸成
――「タイアップ2.0」を通じてブランディングを行う利点について、教えてください。

高野:音楽やアーティストとの取り組みから例に挙げて説明しますと、音は記憶に残る力や想起させる力が強いということです。たとえばJR東海の「そうだ 京都、行こう。」の曲を聴けば、電車やテレビCMのワンシーンを思い出す方が多いでしょう。
また同じ音楽を使い続けることで、その音楽がもつイメージやメッセージがブランドにも浸透していき、長く残るブランドの資産となっていきます。
さらに音楽やアーティストをしっかり理解し、愛とリスペクトのある姿勢をもってコラボし続けていると、可処分精神の転化が起こります。ファンたちが、ブランドもそのアーティストを応援する一人だと感じてくれるようになり、音楽に対する愛や熱狂がブランドにも向けられていくのです。
こうして醸成されたブランドイメージは、他社が短期的に追いつこうと思っても不可能なもの。その意味で「タイアップ2.0」は、大きな投資効果を期待できるものと言えます。
可処分精神の転化を仕掛ける、3つのポイント
――ブランディングを強く意識した「タイアップ2.0」を実施するにあたっては、これまでとは違った点にも気を配る必要がありそうですね。
高野:おっしゃる通り、ただタイアップを実施すればよいというものではありません。ブランドへの可処分精神の転化を図っていくには、3つのポイントを押さえる必要があります。
1つ目は、「トライブ」です。トライブとは、「年代や性別を超え、共通の趣味や興味、価値観で形成される部族」という意味。その音楽やエンタメにおけるトライブを的確に見極めてアプローチしなければ、可処分精神の転化は起こりません。
2つ目は、「文脈的価値」を創造すること。より具体的には、「わかってるね感」もしくは「そうきたか感」を生むことです。「わかってるね感」は、「このブランドは、私の好きな○○のことをしっかりわかっているな」というファンの納得感を生み出すもの。「そうきたか感」は、音楽やエンタメの文脈や背景を理解しつつ、ファンの想像を超える結びつきを起こすことです。
3つ目のポイントは「継続性」。ブランディングと同様、可処分精神の転化は短期間で起こるものではなく、ある程度時間がかかります。一貫して取り組まなければ、そのたびに新たにブランドアセットを作り直すことなり、効果は薄くなってしまいます。
この3つを意識することで、音楽やエンタメを短期的なマーケティングの「手段」とするのではなく、中長期的な戦略パートナーに位置付けていくことができるでしょう。
Hondaやレッドブルも実践
――「タイアップ2.0」に近い取り組みとして、高野さんが注目している例を教えていただけますか。
高野:たとえば「Honda(本田技研工業)とONE OK ROCK」のコラボは良い事例です。音楽をテレビCMに用いて、映像にアーティストを登場させただけではなく、ONE OK ROCKファンの“トライブ”に対して、アーティストの持つ“世界観”とHondaが伝えたいメッセージをうまく融和させた展開を行うことで、ブランドイメージを醸成しています。
高野:また一風変わったコラボとして、スマホ決済サービス「Origami Pay(オリガミペイ)」の決済音をロックバンドのサカナクションが手掛けたという例もあります。アーティストと二人三脚となって、ブランドイメージの醸成を手掛けている興味深いケースです。
このような取り組みはもっと増えて良いと思いますし、工夫次第でまだまだ活用の余地があるはず。企業が既にもっている固有の音を活かすためにアーティストと組む、という方法もあるでしょう。
――様々な企業が、音楽やエンタメを通じた可処分精神の転化を試みているのですね。
高野:はい。さらに言えば、タッグを組むのはアーティストに限らなくても良いのです。
たとえばエナジードリンクのレッドブルは、ずっとエクストリームスポーツを中心にエンタメに寄り添っていますよね。その企業姿勢やプロダクトの背景を含めて、エクストリームスポーツと親和性が高い。ファンの納得感を生み出し、継続性もある、良い事例です。
音楽やエンタメが獲得している可処分精神をブランドへと完全に転化させるのは難しいと思いますが、ブランドのほうへ少しずつ移動してもらうことはできるのではないでしょうか。
音楽マーケティングを当たり前の選択肢に
――高野さんご自身は、「Modern Age/モダンエイジ」において今後どのような取り組みを展開していきたいですか。
高野:「音楽やエンタメはブランドを形成する同志である」という理解を広げていきたいですね。
これまでブランドのマーケティングの文脈で「音楽」と言うと、プロモーションの一要素という認識が強かったと思います。そうではなく、SNSマーケティングやダイレクトマーケティングなど数あるマーケティング手法の一つとして、「音楽マーケティング」が選択肢の中に入るような未来を作っていきたいのです。
それが当たり前になることで、企業と音楽を保有するアーティストの双方にとって高い価値が生まれていくでしょう。
「Modern Age/モダンエイジ」には、ブランドマーケティングとエンタメマーケティング、両方の専門スタッフがそろっているのが強みです。これまでも、文化や慣習が違う2つの業界の橋渡し役として、どちらにとっても「実施して良かった」という取り組みとなるよう、お手伝いをしてきました。今後も音楽やエンタメのもつ可能性を追求しながら、マーケターの皆さんにその価値を伝え続けていきたいです。