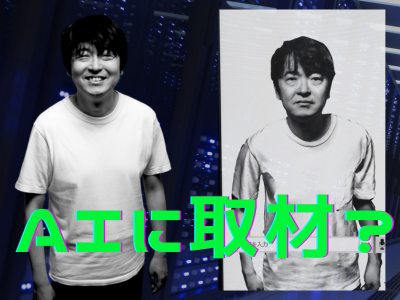データリッチ/データプア企業の差が大きくなる
これらの環境変化が示すのは、データそのものでの差別化が困難になるという事実ですが、企業への示唆はそれだけに留まりません。魅力的なストーリーを生活者に提示できなくては、データ収集すらできなくなるという、データ個人主権時代の到来です。
これはつまり、生活者の資産であるデータを預かり、活用することに対価が必要な時代になっていくということを意味します。しかしこれは、生活者目線でデータを活用し、その企業でしか得られないポジティブな体験の提供をすることで、生活者はデータ提供について必ずしも不快感が生じるものでなく、むしろ前向きに捉える可能性があることを示唆しています。一方で、これは結果的に、企業はデータリッチとデータプアに二極化し、その格差はどんどん広がっていくと考えられます(図表7)。その分水嶺は、いかに優れた体験を提供できるか、にあります。提供体験を豊かにすることが、データ質量の増大につながるわけです。

このような動向も踏まえ、データ活用を図る企業は何を論点と捉えるべきでしょうか。当社では、データプラットフォームの競争優位性を「エクスペリエンス」「プラットフォーム」「データ/テクノロジー」の3つのレイヤーで整理しています(図表8)。

データの質量、すなわちどれだけのデータ量を持っているか、どれだけ多様なデータやアルゴリズムを持っているかという観点はもちろん重要ではありますが、この論点だけでの差別化は難しくなっていきます。そもそもDXに取り組む企業にとって、規模で勝るプラットフォーマーに対し、データ競争を挑もうというのはとても分が悪い勝負といえます。
プラットフォームのアーキテクチャーやプロジェクトの体制作りも差別化に寄与します。なぜなら、デジタル領域では、戦略と実行をフェーズを分けるのではなく、一体化して取り組まなければ激しい変化に対応することができないからです。すなわち “どう作るか”は実は戦略そのものといってよく、データプラットフォームで成果を生むためのカギを握ります。
そして最も重要な論点は、データをどういう幅と深さで使って優れた体験を生み出すか、その体験設計にあります。仮に得られる食材は同じであっても、他社にはできない調理や盛り付けができる。このような競争軸を志向することは、結果的に他社より質量豊かなデータの確保を約束します。
そしてそのためには、自社のコアコンピテンシーは何かを見極める、あるいは再定義する行為が必要です。具体的には、たとえばメディア企業であるならば、自分たちは広告業なのか、コンテンツ業なのか、エンタメ業なのか、会員制サービス業なのか、という問いに答えていくことです。そのように再定義した提供価値をコアにして、それを実現する装置や業務プロセスを検討していく、という流れを踏むことが、競争優位をもたらすデータプラットフォームの構築に結び付きます。
「Content is King」、「Data is Queen」に加え、「Experience is Prince」を改めて認識することが、データ独占あるいはデータの均質化時代に極めて重要な論点となるでしょう。