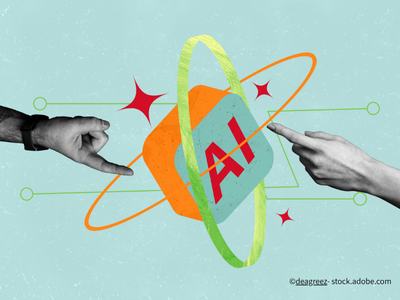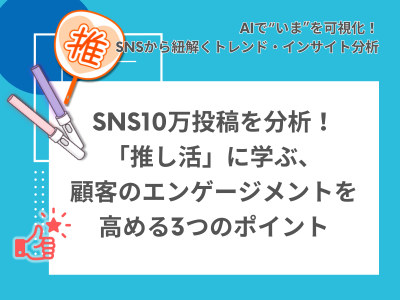金融の「重たいデータ側」に参入できないGoogle
軽い側のデータが重い側のデータと相性が合わない別例として、Googleの動きも見てみる。下記の2件の記事(日本経済新聞より)には、一連のシグナルがうかがえる。
(1)『Google、銀行口座サービスの提供を見送り』2021年10月2日
(2)『みずほ、グーグルと連携 DXテコ入れ、提案力磨く』2022年3月23日
2021年の記事(1)は、Googleが米国でのスマートフォンを通じた銀行口座サービスの提供を見送ったことを報じていた。筆者の解釈ではGoogleが米国で「Banking-as-a-Service(BaaS)」にまつわるAPI連携などの「組込み金融」参入から手を引き、SIerのごとく「銀行のバックオフィスの業務」の利ざやにシフトさせた判断に見える。
その方向転換の理由について「銀行業界の風当たりが強いから」とするが、額面どおりの理解よりも、「(軽い側のデータの蓄積による)強みが活かせない」というGoogle側のジレンマは見えてこないか。金融産業への足掛かりをGoogleの弱みの「赤字」部門である(ビジネス)クラウド事業に押し付けた風だ。
上記の仮説の6ヵ月後が2022年の記事(2)だ。ともすればトラブル続きだった某邦銀システム(DX)を、「マーケティング(=ターゲティング)」発想を持つ「軽い側」起点のシステム企業に、「重い側」である銀行の「金融バックヤード」を任せる構図である。
たとえば、「お客様のボーナス時期ですね、この金融商品がオススメです」という「軽い側のデータ」の推量をもとに「当てにいく」ようなマーケティング手法やシステム運営は、銀行という顧客の貴重なデータをお預かりする「重い側のデータ」の産業には「水と油」ほどの違和感がある。医療や金融産業における法律での規制や責任の重みやモラルを含めて、両者は異次元のはずだ。「軽い側のデータをかけ合わせれば新しい“ビジネスの飴玉”が生まれるかも」では、かなり「軽い」発想だ。
GDPR以降データに関する制限は増えたが、そのおかげでこのような次のステージへ向けた考え方が無限に広がっている。過去のマーケティング基軸での「軽い延長」だけでなく、「新しい(重みのある)価値」を丁寧に見つけたい。