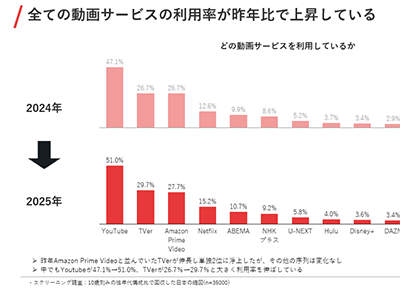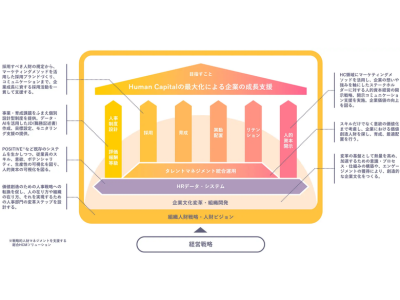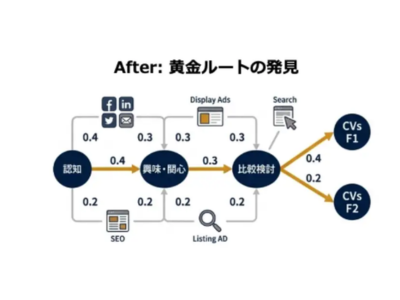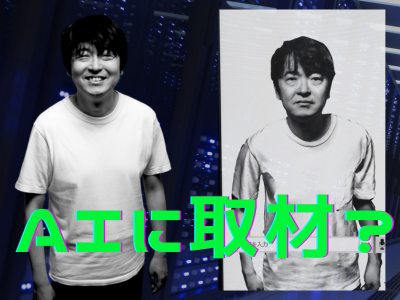会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
新規会員登録無料のご案内
- ・全ての過去記事が閲覧できます
※プレミアム記事(有料)は除く - ・会員限定メルマガを受信できます
- ・翔泳社の本が買える!500円分のポイントをプレゼント
-
- Page 1
この記事は参考になりましたか?
- この記事の著者
-

下 寛和(シモ ヒロカズ)
株式会社野村総合研究所 グローバル製造業コンサルティング部 グループマネジャー。慶應義塾大学卒業後、トヨタ自動車、会計系コンサルティング会社を経て、2014年に野村総合研究所に入社。専門はプライシング、原価企画、SCM、データサイエンス。日経BP「プライシングの技法」、技術情報協会「利益を拡大させるプライシング戦...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア