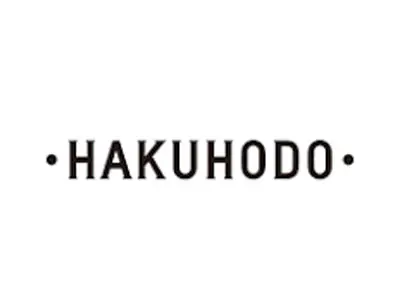効率化を求めた分業化が顧客理解を難しくしている
佐藤(MOTTO):本日はゲームアプリのマーケティングプロモーションとデータ戦略について、業界をリードしてきた2社の担当者とディスカッションを進めていきたいと思います。お二人はゲームアプリのマーケティングに対して、どのような課題感をお持ちですか?

加藤(WFS):ゲームアプリ単体というよりは、マーケティング全体における課題になるかもしれませんが、まず一般論として、顧客理解の難しさが挙げられます。背景にはタッチポイントの多様化が指摘できるでしょう。

加藤(WFS):ショート動画やCTVなどの新たなフォーマットやメディアが盛り上がっているほか、エンターテインメント領域ではVTuberの長時間ライブを視聴する人が増えています。加えて、ゲームをPCでプレイする人が増加するなど、ゲーム周辺で顧客の行動が多様化してきているのです。
この変化に我々マーケターが追いつくことは非常に難しいと感じています。組織や人材の課題にも関連しますが、効率化のために「SNS運用担当」「リアルイベント担当」などと分業化を進めてきたのが、ゲーム業界のマーケティングの歴史だからです。顧客の多様なニーズやインサイトを捉え、マーケティング全体を設計することが難しくなっているため、役割を超えた組織作りが新たな課題となっています。
さらに、日本のゲーム市場が頭打ち状態になっていることは、様々な調査でも指摘されており、皆さまも実感されていると思います。一方で、海外市場においては日本のコンテンツにまだまだチャンスがあるものの、大きな成功事例は少ないのが現状です。この点は課題であると同時に大きなチャンスだと考えています。
新規ユーザーの獲得数だけでなく定着率にも目を向けよ
吉永(ルーデル):私は「費用対効果の最大化」に課題があると考えています。加藤さんのお話と重複する部分もありますが、マーケティングのチャネルや打ち手が増えたことで「どの方法が最も効果的なのか」を判断することが難しくなっているためです。これは業界を問わず、永遠のテーマではないでしょうか。この課題にどこまで向き合い、改善していけるかが重要です。

吉永(ルーデル):同時に、費用対効果を広告やマーケティングの領域だけに限定せず、より広い視点で捉えることも必要だと思います。たとえば新規ユーザーを獲得した際に「そのユーザーを効率良く定着させられているか」といった視点です。獲得数だけで施策の費用対効果を測っても、そのユーザーが早々に離脱しているようであれば、非常にもったいないと言えます。サービスの中身や入り口の部分も含めて、いかに費用対効果を最大化していくかが課題だと考えています。
山根(Adjust):デバイスの多様化により、費用対効果の最大化は一層難しくなりつつあります。この課題に応える手法がクロスデバイスの計測です。当社のクライアントからも「それまでなんとなく捉えていたものをしっかりと可視化したい」という要望が業種問わず増えてきました。

モバイルアプリトレンド2024:日本版
AdjustとSensor Towerが共同調査した「モバイルアプリトレンド2024:日本版」では、日本市場のアプリパフォーマンスに関する戦略的なインサイトをお届けします。ゲーム、ファイナンス、Eコマース、コネクテッドテレビ、PC、コンソールなどのチャネルのデータ分析から、アプリの成長機会を探ります。ダウンロードはAdjustのサイトから。
ヘブバンは未知の海外市場にどう進出したか
佐藤(MOTTO):山根さんから「クロスデバイス」の話題が出ましたが、今のゲームアプリマーケティングにおけるキーワードはまさに「クロスボーダー」ではないでしょうか。クロスするボーダーは「デバイス」であり「国境」でもあり「プラットフォーム」も含まれます。加藤さんには、国境をクロスしたお取り組みを紹介していただきたいです。

加藤(WFS):我々がグローバル展開をスタートしたのは約5年前です。ゲームを海外に展開する際、主に二つの方法があります。一つは自社でパブリッシングを行う方法。もう一つは現地の企業を通じて我々が制作したものをパブリッシングしてもらう方法です。我々は前者、つまり自社で海外市場に挑戦しています。
「新しい驚きを、世界中の人へ。」というミッションを掲げていることもあり、ビジネスのさらなる成長を目指すためにはグローバル展開が不可欠でした。2018年頃から本格的に取り組み始めましたが、当初は右も左もわからない状態だったため、現地の企業やプロモーション協力会社を探して体制を整えました。
体制を整えたのち、2023年には「ヘブンバーンズレッド(へブバン)」というタイトルを、韓国・繁体字圏でリリースすることが決まりました。とはいえ現地では会社名もタイトルもほとんど知られていませんでした。そこで、現地で制作発表会を開催することにしたのです。
最初は人が集まるか不安でしたが、韓国でも繁体字圏でも日本のゲーム市場に対する注目は高まっています。そんな日本国内で一定の認知度を誇るタイトルということもあり、制作発表会には多くのメディアの方々が参加してくれました。我々が大切にしている価値観やタイトルの魅力を、現地の方々と直接コミュニケーションを取りながらプレゼンテーションすることができ、良い機会になりました。
その後はプロモーションを強化し、日本と同様韓国や繁体字圏でもテレビCMやOOH広告を展開しました。商習慣の違いなどに適応しながらクリエイティブを制作したことは、非常に良い経験でした。
異文化交流に相当の費用と時間をかけるワケ
加藤(WFS):リリース直前には、台北ゲームショウという大規模な展示会に出展しました。事前プロモーションの効果もあって多くの方々にヘブバンを認知・体験していただき、“期待のタイトル”としての地位を確立できたと思います。
佐藤(MOTTO):海外展開の先輩から挑戦を考えている企業に向けて、成功させるためのポイントをお聞かせください。
加藤(WFS):文化的な違いを100%理解することは難しいですが、理解のないまま現地でのマーケティングやプロモーションを効果的に行うことは困難です。デジタルを中心としたアプローチであれば、ある程度は可能でしょう。しかし、我々が目指している地点は「タイトルのストーリーを伝え、豊かな体験を提供すること」です。そのためには、現地の文化をしっかりと理解することが重要だと考えています。
現地の文化を理解するために、当社のマーケティング部門では従業員の約4分の1を他国籍のメンバーで構成しています。海外でプロモーションを実施する際は、日本人メンバーとともにアイデアを出し合ってもらい、計画を立てる形です。加えて定期的に海外へ出張し、現地の方々と直接会って情報交換する機会も設けています。逆に、海外の方が日本を訪れる際も同様です。このような異文化交流には、相当の時間と費用をかけています。
佐藤(MOTTO):ライトフライヤースタジオがオフラインプロモーションを重視する理由が理解できました。Adjustとしては、海外展開をする企業にどのようなサポートを提供しているのでしょうか。
山根(Adjust):Adjustは海外に16の拠点を持っているため、現地の展開に必要なサポートを提供することが可能です。お客様のニーズに合わせて対応しますので、ぜひ相談いただければと思います。
広告費の回収率を日時単位で可視化
佐藤(MOTTO):もう1点、加藤さんにはプラットフォームをクロスしたお取り組みについてもうかがいたいです。
加藤(WFS):「Steam」というPCプラットフォームへの対応に注力しています。Steamはグローバルで非常に大きな規模を誇り、モバイルアプリで言うところのApp StoreやGoogle Playに相当するプラットフォームです。我々は2022年からへブバンをSteamで展開しています。日本国内でもPCゲーマーは増えていますが、PCでゲームを楽しむ需要がより高い、海外に向けての重要な戦略です。スマートフォンとPC間のゲームデータ連携や、PCのコントローラー対応、4K対応など、モバイルでは体験できないゲーム体験をPCで提供できるように設計してリリースしています。
佐藤(MOTTO):吉永さんにうかがいます。クロスデバイスやクロスプラットフォームが進むと、先ほど課題として挙げられた効果分析がより難しくなると考えられます。御社ではこの課題にどう対応しているのでしょうか?
吉永(ルーデル):まず必要なことは「広告費用を回収できているか」の確認です。その上で「獲得したユーザーが定着しているか」という視点で効果を測る必要があります。
一連のプロセスにおいて重要なのが「データの可視化」です。当社の場合、ゲームに関連するあらゆるデータをダッシュボードで可視化し、関係者全員がブラウザ上でいつでも閲覧できるようにしています。流入したユーザーごとの広告費用回収率が日時単位でわかるようになっているほか、新規ユーザー数のKPI達成率なども可視化しています。

吉永(ルーデル):新規だけでなく復帰ユーザーの数も重要視しているため、復帰率のKPI達成率も注視しています。テレビCMの放送タイミングでユーザーがどの程度流入し、その中で新規と復帰の割合がどうなっているかを分析しているのです。新規ユーザーの数だけを見ると、それほど大きな効果が実感できなくても、復帰ユーザーがテレビCMを見て大量に戻ってくるケースもあります。
流入初日の課金額で新規ユーザーのLTVが予測できる!?
佐藤(MOTTO):LTV予測の取り組みについても教えていただきたいです。
吉永(ルーデル):データ分析の結果、流入初日の課金額で、新規ユーザーの将来的な課金額をある程度AIで予測できることがわかったんです。この予測を基に、必要に応じて数値を調整しつつ広告を最適化しています。
また、新規ユーザーの定着率向上のため、ゲームのチュートリアルの突破状況を日時で可視化しています。ゲームの操作方法がわかるタイミングで突破率が大きく下がることもあるのですが、データを細かく見ていくと、何らかの問題が見つかることもあります。たとえば「チュートリアルのローディング時間が長すぎる」「端末がクラッシュする」「ゲームが急に難しくなる」などの問題です。
問題をさらに深掘りするため、機械学習モデルを使って新規ユーザーの離脱要因分析を行っています。「インストールした翌日に再度アプリを開いてもらえるかどうか」を重要なポイントとし、継続する人としない人の違いを細かく分析するようなイメージです。
佐藤(MOTTO):機械的かつ定量的に進めながら、定性的な感情を動かすという、非常に難しいチャレンジに取り組まれているのですね。加藤さん、吉永さん、本日は貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。