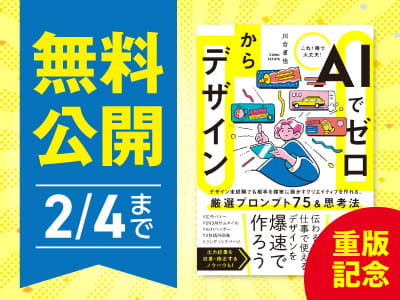CreepyNuts、YOASOBIはなぜヒットしたのか?
レコード、ラジオ、雑誌、テレビ、カセットテープ、CD、MD、MP3、ストリーミング、YouTube、TikTok……。昭和・平成・令和にかけて、音楽視聴メディアとサービスの変遷とともに、音楽の流行の作られ方も変化しています。
しかし、CreepyNutsの『Bling-Bang-Bang-Born』やYOASOBIの『アイドル』が、なぜ億超えの再生回数を叩き出せたのか、その背景を説明できる人は少ないでしょう。そこで、ヒットがどのように生み出されているのかを知りたいマーケターにお薦めしたいのが、書籍『令和ヒットの方程式』です。

本書は、昭和・平成・令和の3時代のヒットの方程式の変遷を解説するとともに、博報堂独自の「コンテンツファン消費行動調査」のデータを基に、現在の音楽業界、音楽ファンの実態を明らかにしています。
情報源が多様化した現代において、音楽がどのように消費されているのかを紐解く上で、本書では音楽利用層を9つのクラスターに分類。それぞれが重視する情報源や使用する音楽サービス、音楽の楽しみ方が異なることや、デモグラフィック、支出金額を含めて詳細に解説しています。
9つのクラスター
- 強み令和アイドル推し層
- Jポップアイドル推し層
- 令和トレンドセッター層
- 音楽ディープダイバー層
- 音楽で井戸端会議層
- 令和の王道リスナー層
- ストリーミングチャートザッピング層
- ボカロ&ネット系音楽愛好家層
- 昭和音楽愛好家層
著者は、「企業が音楽コンテンツを活用してコミュニケーションを仕掛ける際や、アーティストサイドが新規リスナーを獲得していくためには、それぞれのクラスターの音楽の嗜好に合わせてプランニングをする必要がある」と述べています。
フィードコンテンツが鍵
では、ストリーミングやショート動画が普及した現代において、どのようにヒットは生まれているのでしょうか。その鍵となるのは、作品そのものではないコンテンツの付帯情報「フィード(直訳すると、餌・食べ物)コンテンツ」です。
フィードコンテンツの例としては、作品周辺の小ネタ(裏話、エピソード、制作秘話など)や、視聴者による作品批評、作品に関連するネタを投稿するUGC・口コミなどが挙げられます。
そしてフィードコンテンツの代表例としては、2016年のTBSドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』のエンディングの「恋ダンス」があります。SNSを中心に、「踊ってみた動画」が話題となり、ドラマと主題歌の大ヒットを生み出しました。踊ってみた動画が広がった背景には、フィードコンテンツを手軽に量産できるTikTokの登場があり、他プラットフォームでもショート動画に対応することで、この流れはさらに加速しています。
YOASOBIの『アイドル』がヒットした背景にも、楽曲自体の魅力に加えて、ファンが制作した「踊ってみた」「歌ってみた」などの多様なフィードコンテンツの存在が大きく影響しました。
さて、ここで本書の肝心な部分である「令和版音楽ヒットの公式」を紹介しましょう。
アーティストの魅力×フィードコンテンツ=ヒット行動に関連するファンの動機
最初に、音楽ファンに知ってもらいたいアーティストの魅力を、送り手側が考える必要があります。その上では、先に挙げたクラスターを理解し、関係性を築きたいファンがフィードコンテンツを作りたくなるような素材を提供することがポイントとなります。そして、ミュージックビデオの再生回数やCDセールスなど、ヒット指標に関連する行動を促す仕掛けを作っていくのです。
フィードコンテンツの種別やクラスター別の適した素材は、ぜひ本書でご確認ください。また、この公式を基にヒットした曲を分析した解説も、読みごたえ十分です。
令和のヒットは、ファンとの共創が必要
本書の指摘する現象は、音楽ファンの実体験からも裏付けられます。筆者自身、2008年頃からK-POPシーンを追い続ける一人として、この変遷を目の当たりにしてきました。
今や、世界的なグループになったBTS(当時は防弾少年団)も、2013年にデビューして以来、YouTubeでは楽曲の映像に加えビハインドストーリーやバラエティ番組風の映像を自ら制作し投稿していました。そして、その姿をきっかけに好きになり、ファンが彼らの言葉を翻訳したり、切り抜いたり、楽曲を解説したフィードコンテンツをきっかけに「沼落ち」した人は、私を含めて世界中にいるのだろうと思います。
本書が導き出したヒットの方程式をハックすることは、ヒットコンテンツを生み出す近道になることでしょう。しかし1ファンの身になって考えると、コンテンツ提供側に『餌(フィード)』として捉えられるのは少し残念に感じます。
令和の音楽シーンでは、送り手側が一方的にヒットを仕掛けるのではなく、ファンとの双方向のコミュニケーションを通じて作品の価値をともに作り上げていく時代に変化しています。ファンが作り出したコンテンツが、新たなファン層の開拓や楽曲の新しい楽しみ方の発見につながり「ヒット」の重要な要素となっています。
だからこそ、ファンは利用するものではなく、作品の価値をともに創造していく大切なパートナーとして改めて肝に銘じなければならないでしょう。