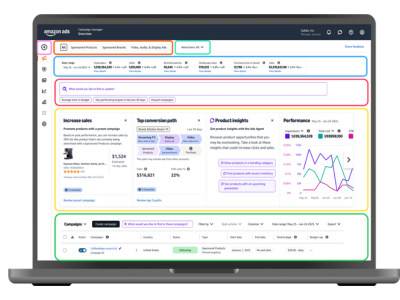メンバーの実行を促す「問い」を立てよ
第四次フェーズの今、企業はECを単なるチャネルではなく、事業活動全体の起点として捉える必要があることは既に説明されたとおりだ。澤田氏は、EC起点の事業運営を成功に導くための助けとして、次のようなフレームワークを紹介する。

「STEP1では事業基盤をはじめとする戦略を経営者視点で策定しましょう。続くSTEP2ではマーケティング施策などの戦術を生活者視点で考え、進めていくフレームワークです」(澤田氏)
このフレームワークを使えば、社内で共通認識を構築することができるという。ただし「関係者にフレームワークを渡すだけでは実践されない」と澤田氏。ポイントは、戦略や戦術を実践に移しやすい「問い」の形に翻訳することだ。

戦略立案において設定すべき問いは三つ。第一に「あるべきチャネルの使い分けって?」という問いを立てることで、各チャネルの役割を定義する。続いて「マーケティング視点でフルフィルメントをどう設計する?」という問いを立てれば、陥りがちなシステム選定の失敗を回避することが可能となる。第三の問いは、事業指標に関する問いだ。「KGI・KPIはどうやって設計する?」という問いがあれば、有効な指標をメンバー全員で議論できるだろう。
戦略の次は戦術だ。ここでも「ECで買いたくなる情報のタッチポイントって?」「もう一度物を買いたくなるための仕掛けって?」「長くファンでいたくなるツボって?」などの問いを立てることにより、生活者視点の意思決定が行えるという。
“あるある”から現場の課題を紐解くと
ここから桑嶋氏と澤田氏は「ECビジネス支援の現場あるある」というテーマの下、クライアントからよく聞くフレーズを三つ紹介する。
あるある 1
フルフィルメントは専門家に任せているので
「フルフィルメントは一般的に『受注から出荷まで』を指すと考えられていますが、この認識は正しくありません。ECで商品を購入した生活者にとっては、外箱や同梱物が最初の“顧客接点”になるケースが多く、フルフィルメントは顧客体験を左右します。『事業全体を下支えするインフラ』のようなイメージでフルフィルメントを捉えるべきです」(澤田氏)
あるある 2
限られた宣伝費でEC起点のブランドを作りたい
確かにEC起点のブランドでは、限られた予算でスモールテストを行うことができるだろう。しかしながら、スモールテストを意味あるものとするためには「初期仮説が重要」と澤田氏は強調する。
HAKUHODO EC+では、初期仮説の構築にSNSの活用を推奨しているという。SNSで収集可能な顧客の“生の声”を商品開発の段階から取り入れれば、発売後にSNSでの発話を促せるためだ。
あるある 3
ECってデータ取れるんでしょう?とりあえず分析して
このフレーズの問題点として、澤田氏はデータ取得に対する認識の甘さを指摘。生活者の情報リテラシーが向上する昨今、企業が自身から取得したデータの活用用途が不透明な場合に、生活者はその企業のサービスの利用をやめてしまうという。
「データを取得したい場合は、生活者に還元できるメリットを明確に示す必要があります。生活者への還元をゴールに設定した上で、データ分析のあり方を設計しましょう」(澤田氏)
桑嶋氏は最後に、次のようなコメントでセッションを締めくくった。
「Commerce Anywhereの時代を迎え、ECは出口ではなく入口のような存在となりました。つまり、EC起点のマーケティングが事業成功の鍵を握っているのです。今日ご紹介したフレームワークや問いを基に、経営者視点と生活者視点を行き来しながら、チームで議論を進めてみてください」(桑嶋氏)
書籍『EC起点の事業変革 博報堂式 ECから始める、これからのマーケティング』(翔泳社)では、本セッションの内容はもちろん、具体事例やメーカー担当者への取材記事も収録されている。ECビジネスを展開する企業のマーケターは必読の一冊だ。