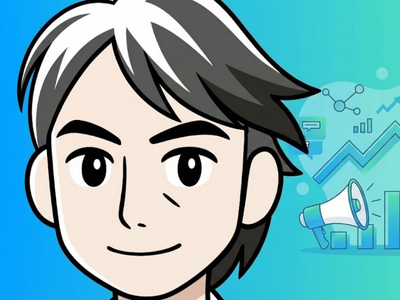成長スピードが鈍化しつつある日本のEC市場
日本のEC市場は、ここ10年で目覚ましい成長を遂げた。経済産業省が実施した「令和5年度電子商取引に関する市場調査」によると、国内のEC化率は2014年から2023年までの間で2倍以上伸長している。特に新型コロナウイルスが蔓延し始めた2020年、ECに取り組む企業が増加したことは想像に難くない。

では、2025年現在のEC市場はどうか。HAKUHODO EC+の桑嶋氏は「成長スピードがやや鈍化傾向にある」と指摘。その背景を示す目的で、市場の変遷をEC黎明期から四つのフェーズに分けて振り返る。

第一次フェーズにあたる1990年代~2000年代、楽天市場の登場とともにEC市場が誕生した。この頃のECは「通販企業の1チャネルだった」と桑嶋氏。通販企業が深夜帯の受注の受け皿として、ECを利用していたためだ。“インターネットで物を買う”という行為が徐々に浸透し始めたフェーズと言って良いだろう。
第二次フェーズは2010年代からコロナ禍直前までを指す。Amazonが日本での活動を本格化させ、楽天市場との競争を繰り広げた時代だ。
「この頃から、メーカー各社が楽天市場やAmazonを活用するようになりました。その結果、ECは実店舗など他の販売チャネルと横並びで考えられるようになったのです」(桑嶋氏)
桑嶋氏は第三次フェーズとして、2020年から2022年までの期間を指定。コロナ禍の影響で多くの企業がECへと参入した時期であり、直前に北米で急激に伸びたD2Cブランド各社の成功事例が研究され、日本での導入が進んだ時期でもある。
「D2Cの利点は、顧客と直接つながることで1st Party Dataを収集できる点にあります。ブランド各社が運用を通じて、その可能性に気付き始めたのです。こうしてECは単なる販売チャネルから『マーケティングチャネルの一つ』として捉えられるようになりました」(桑嶋氏)
過渡期の勝ち筋は「Commerce Anywhere」
そして現在、EC市場は「第四次フェーズに位置している」と桑嶋氏は語る。第四次フェーズでは何が起こっているのか。
HAKUHODO EC+が実施した調査の結果によると、コロナ禍を経て50代・60代のEC利用が増加した一方、若年層を中心に実店舗での購買が増加している。実店舗回帰の波を受け、第二次・第三次フェーズでECに参入した企業の中には期待した成果を得られず、EC市場からの撤退や再建などの経営判断を迫られているところもあるという。
「第一次から第三次フェーズにかけて、各社が激しい競争を繰り広げてきました。一方、生活者目線では購買チャネルの選択肢が増えたと同時に、EC体験が快適なものへ進化したフェーズとも言えます。過渡期にあたる第四次フェーズ、企業は競争の勝ち筋を見出さなくてはならない状況です」(桑嶋氏)
HAKUHODO EC+が第四次フェーズの勝ち筋として考えているのが「Commerce Anywhere」という概念だ。この概念では、ECをマーケティングや事業におけるハブの役割として捉える。
「今、我々が考えなければならないのは、ECビジネスをECだけで完結させることではありません。オフライン・オンライン双方におけるマーケティングのプラットフォームとして、つまり事業活動全体の起点として、ECビジネスを捉える必要があるのです」(桑嶋氏)