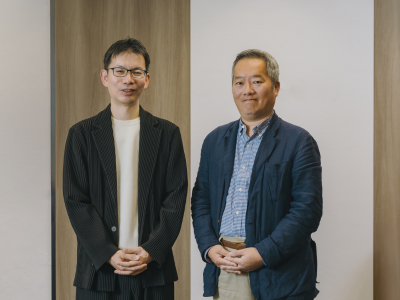日本発のバーチャルヒューマンAIカンパニー Aww
MarkeZine編集部(以下、MZ):はじめに、そもそも「バーチャルヒューマン」とは何か、簡単にお伺いできますでしょうか。
守屋:バーチャルヒューマンとは、3DCG技術とAI技術を駆使して生成される、本物の人間に見紛ってしまうようなクオリティのキャラクターのことです。人間の外見や行動、中身までも模倣し、AIを用いた声を発します。デジタル空間にいるキャラクターとリアルタイムで、まるで人間と話しているかのようなコミュニケーションが可能です。

映像プロデューサーとしてキャリアをスタート。2012年、Pairsを運営するエウレカでプロデューサーを務める。その後、Web、アプリ、メディアを提供するブルートを20代に設立。AR、VR、XR事業、AIエンタメ開発、5Gコンテンツ制作など多岐にわたって携わる。2016年、新しい映像ビジネスを構築するためにナイオンを設立。2018年にアジア初のバーチャルヒューマンimmaを創造し、アウ(Aww)を設立する。創業1年足らずで60ヵ国以上、8,000以上のメディアに掲載され、バーチャルヒューマン事業を確立させる。
MZ:バーチャルヒューマン事業を展開するAww社についても教えてください。
守屋:Awwは、アジアで初めてバーチャルヒューマンを定義し、商材として提供し始めた企業です。事業は大きく分けて二つ展開しています。一つは、「imma」をはじめとしたバーチャルヒューマンをプロデュースし、自社のIPとして成長させていくこと。もう一つは、バーチャルヒューマンを活用したい企業と協業し、企業独自のバーチャルヒューマンの開発・制作・プロデュースなどを支援していくことです。2025年に入り、企業からのお声がけは特に増加してきていますね。
また、バーチャルヒューマンのなかに対話型AIを内包させ、独立した思考や会話ができる「対話型AI バーチャルヒューマン」の開発にも、2024年より注力中です。
SNS総フォロワー数100万人超え グローバルで活躍する「imma」
MZ:Awwでプロデュースしているバーチャルヒューマンの活動と、その影響力について教えてください。
守屋:たとえば、最初に誕生したバーチャルヒューマンのimmaは、ファッション分野を中心に世界で活躍する、グローバルかつ等身大な女の子です。100万人以上のSNS総フォロワー数を抱え、いまや時代のアイコン的な存在となっていますね。タレントやモデルの域を超えた、新しい形の「バーチャルヒューマンインフルエンサー」として、活躍の幅を広げています。

ピンクのボブスタイルが特徴的なアジア初のバーチャルヒューマン。2018年のデビュー以来、そのリアルとバーチャルの境界線を超えた唯一無二の存在が世界中を騒然とさせ、これまでに世界60ヵ国、8,000以上のメディアにて話題になった。現在Instagramのフォロワーは40万人、TikTokでは48万人を超え、アジアを代表するバーチャルヒューマンに成長。2021年には「東京2020パラリンピック」の閉会式にも登場し、2024年にはカナダで開催されたTED Talkにバーチャルキャラクターとして初めて登場。2025年大阪・関西万博のスペシャルサポーターにも就任している。
MZ:企業の広告モデルとして起用される機会も多いのでしょうか。
守屋:はい、国内外から多くのオファーをいただいています。ポルシェ、SK-II、COACH、IKEAなど、有名企業の広告塔となっていますね。物珍しさだけではなく、エンゲージメントの高さを評価して継続起用していただいているのが嬉しいところです。2024年から継続的に起用していただいている野村ホールディングスさんからは、「これまでの新聞広告のなかで最も問い合わせが多かった」とご評価いただきました。

MZ:2018年の開発当初から今までで、反響の変化は感じますか。
守屋:当時はとてもセンセーショナルでしたが、昨今は生成AIの登場もあり、一般にも受け入れられやすくなってきたと思いますね。認知度は随分高まった一方で、日本では具体的なビジネス導入はまだ限られているのが現状です。欧米や韓国、中国での導入のほうが先行して進んでいます。ただ日本においても最近、顕著に問い合わせが増加してきているので、いよいよビジネス活用が本格化する段階となってきたのかもしれません。
バーチャルヒューマンが企業に選ばれるワケ
MZ:どんな業種業態の企業がバーチャルヒューマンを活用していますか? また、どのような目的で活用されているのでしょうか。
守屋:自治体、飲料メーカー、空港、銀行など、幅広い業種業態の企業に問い合わせをいただいております。
目的は主に三つです。一つ目は、自社の商品やサービスをプロモーションする目的。先ほど例に挙げたような広告モデルとしてバーチャルヒューマンを活用するイメージですね。
二つ目は、自社でオリジナルのIPキャラクターとして新しくバーチャルヒューマンを作り、会社の財産として保有・マネタイズしていく目的です。もちろん「人型」でなくても作成できるので、「バーチャルキャラクター」として提供する場合もあります。
三つ目は、業務効率化の目的です。AI技術を使って業務の手助けやお客様のご案内を行うことで、人手不足解消、ユーザー体験向上に寄与します。たとえば、とある飲料メーカーでは、イベントの受付としてimmaを導入していただきました。そこでの会話をAI解析しユーザーニーズを探ることで、マーケティング的な観点でもご活用いただいています。

MZ:広告以外にも様々なニーズがあるのですね。タレントやVTuberではなく、バーチャルヒューマンを企業が活用するメリットはどんなところにあるのでしょう。
守屋:まず企業から挙がるのは、「炎上リスクの回避」ですね。炎上を避けるためにバーチャルヒューマンを開発したわけではなかったものの、全世界がパパラッチ化し、コンテンツが過激化するSNS時代において、避けては通れない観点となってきているのかもしれません。
MZ:炎上回避の観点では、AIで生成したキャラクターやモデルを活用する手もあると思います。なぜ、バーチャルヒューマンが選ばれるのでしょうか。
守屋:バーチャルヒューマンはストーリーを紡いでいるからです。AIでその日に生成したようなキャラクターには、歴史や背景がありませんよね。そこにタレントバリューは生まれにくいでしょう。
一方、当社のバーチャルヒューマン、特にimmaには、ファッション誌での活動や日々のSNS投稿など「ここまでの物語」の積み重ねがあります。「ストーリーテリング(物語性を持たせて惹きつけること)」が可能な点は、AIで生成した人物やキャラクターとは大きく異なるでしょう。
オリジナルバーチャルヒューマンが、たった2日で作成可能⁉
MZ:バーチャルヒューマンを開発するうえで、Awwならではの特徴やこだわりはありますか。
守屋:モデリング技術と量産体制、スピードには自信があります。immaだけでも10段階以上はアップデートを重ねていますし、アップデートされた最新の状態をもとに、別のバーチャルヒューマンを作っていますので、大量のスキャンデータが蓄積されています。結果、バーチャルヒューマンを1体2日程度で新規作成できる量産体制が整ってきました。
加えて、「ストーリーテリング」に挙げられるように、バーチャルヒューマン一人ひとりの個性や背景にこだわっている当社では、大規模言語モデル(LLM)を独自で研究開発しています。これによって、一般的なAIの特徴に影響されることのない、バーチャルヒューマンの個性を前面に出したアウトプットが可能となりました。
なお、企業からバーチャルヒューマン制作をご依頼いただいた際には、モデリングだけでなく、搭載する機能、ストーリー設計、コンテンツ企画など、開発からプロデュースまでを自由度高く、総合的にカバーすることが可能です。
リアルタイムで会話できる「対話型AIバーチャルヒューマン」
MZ:2024年11月には、「対話型AIバーチャルヒューマンα版」が公開されました。対話型AIバーチャルヒューマンとは、どのようなものなのでしょうか。
守屋:ブラウザやモニターデバイスを通して話しかけると、画面内のバーチャルヒューマンが人の声を認識し、自分で考えた内容で返答してくれるというものです。言語切り替えも自動でできますので、日本語で話しかければ日本語で、中国語で話しかければ中国語で返答します。
MZ:どんな場面での活用ケースが期待できるでしょう。
守屋:展示会での営業マンの代わりになったり、医療現場で患者さんのおしゃべり相手になったり、社外取締役になったり……、当社が想定していなかったような活用方法も含めて、既に様々なご相談をいただいています。
MZ:人手不足の現場はもちろん、どんな企業でも活用余地がありそうですね。2025年1月には、「対話型AIエージェントライトパッケージ」もリリースされました。こちらの特徴についてもご紹介いただけますでしょうか。
守屋:ニーズの高まりを受けて、簡単かつ低コストに、まずは導入してもらうためのプランです。136種類の顔のタイプから、活用したいバーチャルヒューマン1体を選んでいただき、RAG(検索拡張生成)などを活用し、その会社に合わせた回答に調整し、そのまま導入いただけます。まずは実際に使ってみて、「もっとこうしたい」という部分が挙がってくれば、オリジナルでのバーチャルヒューマン制作をお薦めしています。
バーチャルヒューマンが日常化する未来を目指して
MZ:最後に、Awwとしての今後の展望を教えてください。
守屋:将来の目標は二つあります。一つは、バーチャルヒューマンからスターを生み出すこと。バーチャルヒューマンから歌手、女優、モデルなど、世界に通用するスターを増やすことにトライしていきたいと考えています。
もう一つは、企業の意思決定タイミングにバーチャルヒューマンが同席したり、日常的にアシスタントとして業務をサポートしたりといった機会を、当たり前にしていくこと。「バーチャルヒューマンが日常化する未来」を創っていくのが、これからの私たちの使命と言えるでしょう。