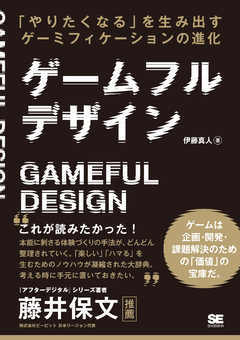ゲームの力を課題解決に応用するゲームフルデザイン
ゲームが持つ「人を動かす様々な仕掛け」をゲーム以外の分野、ビジネス課題や社会問題などを解決するために活用する。
これは一昔前にマーケティングにおいても注目された、ゲーミフィケーションの基本となる考え方です。
マーケティングの文脈ではリピーター獲得などを目的として、スタンプやバッジ、あるいはポイントといった「ユーザーが行動に応じた報酬を獲得できるゲーム的な仕掛けを利用する手法」として知られるようになっていきました。残念なことに、こうした手法にはあまり効果がなかったと記憶している人もいるでしょう。
では、本書で提唱されるゲームフルデザインは、こうしたゲーミフィケーションとどう違うのでしょうか。
ゲームフルデザインは内発的動機づけ
セガでゲームプランナーとして活躍したのちセガ エックスディーを設立するなど、ゲームの力を最前線で体感し活用してきた著者の伊藤真人氏は、ゲームフルデザインを「内発的な動機づけを通じた、ゲームをはじめとするエンタテインメントの「ついやってしまう」「ついやりたくなってしまう」「ついやり続けてしまう」仕掛けを活用するアプローチ」と定義しています。そして、そのアプローチの結果として考案される具体的な手段がゲーミフィケーションだとしています。
少し噛み砕くと、ゲームフルデザインは、時間も忘れてゲームを遊んでしまう人間の本能(欲求)にまで理解を広げ、その本能を刺激することで対象者が自発的な(つまり内発的な動機づけを通じて)行動変容を促す方法を考えるためのフレームワークです。
また、これまでマーケティングにおいて広まっていたゲーミフィケーションは外発的な動機づけ(スタンプを貯めると景品がもらえる、買い物時におまけでポイントが付与される、etc.)によるものがほとんどでしたが、ゲームフルデザインは内発的な動機づけにもとづくアプローチに限定されます。
内発的な動機づけとは、誰かに強制されるのではなく自分からやりたいと思うようになる動機づけです。本書では内発的な動機づけについて、瞬間的に反応してもらうためのアプローチである瞬間UX、継続的に行動し続けてもらうためのアプローチである習慣UXに分類しています。
さらに、瞬間UXは「ついやってしまう」という無意識なものと、「ついやりたくなってしまう」という意識的なものに分類されます(習慣UXは「ついやり続けてしまう」)。ゲームフルデザインは、瞬間UXと習慣UXを組み合わせることで行動変容を促すアプローチなのです。
人間の欲求を理解する必要性
本書ではゲームフルデザインの個々のメソッドが多数紹介されていますが、当然ながら「人間のどんな欲求を利用するとよいのか」という観点から解説されています。そのため、ゲームフルデザインを利用したいマーケターは顧客理解の前に人間の欲求を理解する必要があります。
伊藤氏がゲームをはじめとするエンターテインメントの仕事で培った経験則から人間の欲求を整理したものが下記の表です。

大きく分けると、中央に生理的欲求である感性欲求、その周りに社会的欲求である8つの欲求が配置されています。伊藤氏は、ゲームがこれら社会的欲求を満たしてくれるからこそ、人はゲームに夢中になるのだと説明しています。ゲームフルデザインは、ゲームが持つこの力を応用し、様々な課題解決を可能にします。
では、ゲームフルデザインが解決を得意とする課題はどういうものでしょうか。その可能性について書かれたパートを本書から抜粋します(一部編集)。
幸福度を高めるゲームフルデザインの可能性
ゲームと聞くと遊びや娯楽が真っ先に想像されるため、活用できる領域は限られるのでは、と考えられる方も多いかと思います。ただ、ここまで説明してきた通り、ゲームの本質活用の範囲は非常に広いです。
ガートナーのレポート「ゲームのメカニズムを非ゲーム的な分野に応用することで、ユーザーのモチベーションを高めたり、その行動に影響を及ぼしたりする幅広いトレンド」というゲーミフィケーションの定義に立ち返ってみても、方法論が一般化してしまった歴史はありつつも、本質的にはゲームのメカニクスを活用したモチベーションデザイン、ビヘイビアデザインそのものを指していると考えられます。
機能的価値だけでは解決できない課題があふれる現代社会において、人間の行動変容によって課題を解決するビヘイビアデザインの重要性は増しています。そしてビヘイビアデザインには人間の本質的な欲求の理解が必要です。
そしてゲームは、人間の遺伝子レベルの生存・生殖欲求を満たすために必要な精神的欲求を満たす構造を持っています。ゲームの構造が生み出す「ついやってしまう」「ついやりたくなってしまう」「ついやり続けてしまう」体験が、人間の行動を変容し課題を解決していきます。
金銭や外的強制によらず、人間が自発的・能動的に行動を変えたくなり、その変化を通じて、課題が解決され世界がより良くなっていく、そんな社会の幸福度を高める考え方・手法がゲームフルデザインです。
考えられる活用範囲は無限にありますが、以下に例を挙げておきます。
- 継続して勉強をし続けることが難しい
- 営業職の従業員が毎日の営業レポートの報告を忘れがち
- 毎日少しずつ健康のためにトレーニングをしないといけないのはわかっているがどうしても続かない
- ゴミのポイ捨てをなくしたい
- 若者が選挙になかなか参加せず投票率が上がらない
これらは全て、解決のためにゲームフルデザインの考え方を活用した先行事例が存在する課題です。「選挙をゲームフルにする」「勉強をゲームフルにする」「営業をゲームフルにする」など、社会の多くの課題に対しゲームフルデザインの考え方は活用することができます。非常に活用範囲が広いゲームフルデザインの考え方ですが、特に得意なケース、苦手なケースは存在します。
特に得意なケースは、行動対象となる人間が潜在的にその行動が重要であることは認識しており、なかなか行動に踏み出せない(緊急性が低い)という状況でのアプローチです。先の例でも
- 勉強は大事であることは理解している(が続かない)
- 営業レポートは必要なことは認識している(が報告を忘れがち)
- 健康は大事であることは理解している(が続かない)
- ゴミのポイ捨てはしてはいけないと理解している(がしてしまう)
- 選挙は大事だと理解している(が投票に行かない)
と全て、行動の重要性は認識されている前提でした。こういったケースはゲームフルデザインの考え方を通じて行動の後押しがしやすく効果を発揮しやすい傾向があります。
逆に苦手なケースは、完全自動化された工場内でのマシンの稼働効率化など、人間の行動が課題解決に介在しない状況です。ゲームフルデザインは本質的な人間の欲求を理解した上で欲求を刺激し行動を変容することで結果的に課題を解決するアプローチです。人間の行動が課題解決に寄与しないケースでは、どうしても活用が難しくなります(このようなケースでも、例えばマシンの稼働効率を改善させるための方法を考える従業員の方に対して、改善案を考えたくなるようにアプローチする方法は考えられます)。
人間の本質的な欲求を理解した上でビヘイビアデザインの手法を考えていくという前提のもと、次項からは、より具体的な実践として9つの欲求ごとに効果的な手法を細かく説明していきます。全部で101個の手法を定義しています。それぞれの手法ごとに、どういうケースで使うとより効果的か、という実践のヒントも記載していくので是非、辞書のように手元に置いて活用してください。
概念、手法、実装方法、ケーススタディまで
本書ではこのように、ゲームフルデザインがどういうものかが丁寧に解説されています。そのうえで具体的な手法が網羅的に紹介され、さらにどうやってそれぞれの課題に手法を活用すればいいのかが説明されます。
最後の第5章ではケーススタディとして、伊藤氏が実際に携わったプロジェクトでどのようにゲームフルデザインを活用したのかが紹介されています。「エンタメ型防災訓練 THE SHELTER」はオフラインの事例として、「英語学習リズムゲーム Risdom」はオンラインの事例として非常に参考になります。
ゲームフルデザインの活用には「この手法が使えそうだからこれにしよう」という手段優先ではなく、課題の特性とゴール、そしてそれを解決するための人間の欲求を分析することが欠かせません。本書を読み通すことで、そのための考え方と方法論がセットで身につくでしょう。