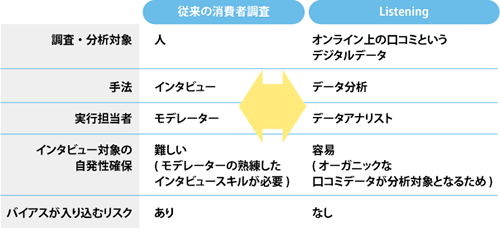従来の消費者調査との比較から見るListeningの可能性
企業のビジネス活動において顧客・消費者のインサイトを捉える重要性については、広く認識されているところではある。では、どのような戦略を持ってインサイトを捉えていけばいいのだろうか?
一般的には、グループインタビューやデプスインタビューといった定性的な消費者調査が考えられる。本稿では、これら従来の消費者調査と比較しながらListeningの可能性について述べていきたい【図表3】。
対象や担当者における違い
まず、従来の消費者調査手法では、調査対象は当然ながら「人」である。「正しい人(ライトパーソン)」に「正しい質問をする」ことが肝要であり、インタビュー対象となるライトパーソンの特定およびリクルーティングが重要となる。実際の調査では、ライトパーソンのリクルーティングに相応の日数がかかることになる。そして、インタビューでは、消費者の本音であるインサイトを引き出すために、モデレーターの熟練したスキルが必要となる。
それに対してListeningは、オンライン上で起こっている「オーガニック(自然発生的)な口コミ」に耳を傾けるというアプローチである。対象は、「人」がソーシャルメディア上で起こした「口コミ」というデジタルデータであり、分析もデータアナリストが担当する。
なお、アフィリエイトやブロガープロモーションによって、企業やメディアが強制力を働かせて引き起こした口コミは、基本的にはオーガニックな口コミとは言えない。そのため、そのようなバイアスを勘案したうえで、分析を行う必要がある。このことについては、さらに後述する。
調査手法や結果における違い
従来の消費者調査では、まず設問を設計し、その設問に沿って消費者に質問をしていくというのが基本的なプロセスである。そういう意味では、従来の消費者調査手法は「Asking」と考えると分かりやすいかもしれない。
一方で、Listeningはソーシャルメディア上で自然発生的に巻き起こっている口コミを収集し、分析していく過程で口コミが引き起こされている背景を探り、意味合いを抽出していくプロセスである。この場合、なるべく企業側で仮説を置かずに、「曇りのない目で顧客・消費者が語っていることに耳を傾ける」というスタンスを取っている。
Askingでは、モデレーターがあらかじめ設定した仮説、もしくは社会通念上の常識というバイアスに引きずられて、その範囲外の顧客のインサイトを見落としてしまうリスクがある。それに対して、Listeningは口コミというファクトを見つめて、その意味合いを紐解いていくアプローチのため、バイアスが入り込むリスクはないと言える。
通常、企業や商品ブランドに対して、オンライン上でどのような口コミが起こっているかは、ある程度は想像できる。しかしながら、予期していなかったような口コミを発見したり、口コミの意味合いを深く読み解くことで、商品開発・マーケティング・CSといった企業のバリューチェーン全域に対して、アクショナブルなインサイトを導き出していくのが、Listeningの本質的な意義と言える。