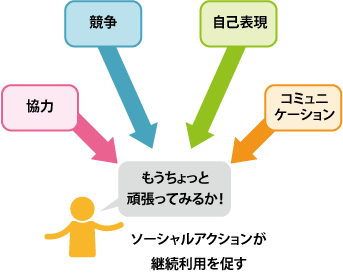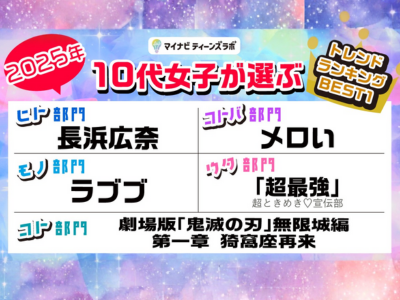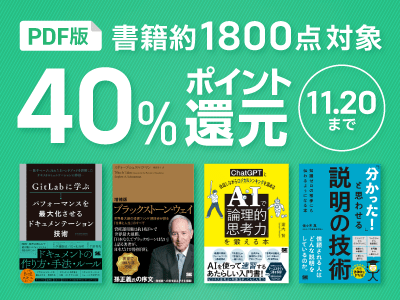(2)可視化要素
通常、ゲームでは様々な要素が可視化されています。自分や相手の強さ、地図、行けるところと行けないところ、目標達成までの距離、ソーシャルグラフ上の友人の行動、など色々な要素が数値やテキスト、あるいは何かしらのフィードバックを通じて見えるようになっています。
ゲーミフィケーションでも、このような可視化を考えることになります。(1)で検討した「目的」が明確になれば、目的にどの程度近づいているのかを数値化することができ、利用者のモチベーション向上に大きく貢献します。達成感を得てもらためにも、自身の取った行動がどのような結果に結び付いたのかを数値などの形で見せることは重要です。
また、利用者が次にどのような行動を取るかを自律的に選択する上でも、可視化が必要となります。取れる行動にどのようなものがあるのか、行動を取った結果どのような状態になることが予測されるのか、そのために必要な労力はどの程度か、などの材料が可視化されていれば、次に取るべき行動を利用者が自分で考えることができるようになります。
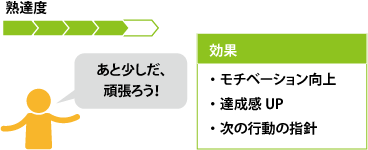
可視化要素としては、目標達成時にどのような報酬が得られるのかを見せることでやる気を喚起する、ということも含まれます。ただし、第2回で紹介した「自己決定理論」で触れたように、金銭的な意味のある報酬を設定することで外発的に動機づけようとすると、長い目で見た場合、逆効果になることもあるため注意が必要です。
(3)目標要素
ゲーミフィケーション・フレームワークでは、「目的」と「目標」を区別しています。目標を数多くクリアしていくことで、目的に近付いていくという関係性で捉えてください。そのため、目標は「大目標⇒中目標⇒小目標」とブレイクダウンされていくことにもなります。
ソーシャルゲームを眺めると、目標要素には様々な例があることがわかります。ざっと列挙するだけでも、多種多様な目標要素があります。
- アイテムをコンプリートする
- ボスを倒す
- レベルを上げる
- 称号を獲得する
- キャラクターを育てる
- 新しい世界を開拓する
- ライバルの友人を追い抜く
- 周りの友人から評価される
ゲーミフィケーションにおいても、こうした例を応用することができます。また、(1)で明確にした目的の達成をブレイクダウンし、どのような目標や行動が相応しいのかを考えることでも、目標要素を設定することができます。
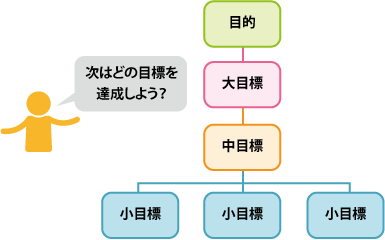
(4)ソーシャルアクション
ゲーミフィケーションを考える上で非常に重要になるのが、このソーシャルアクションの要素です。ソーシャルアクションとは、直接・間接に関わらず利用者間での交流につながるあらゆる行動を指します。行動情報を共有したり、メッセージを送ったり、戦いを仕掛けたりといった直接的・能動的な交流もあれば、相手のマイページやアバターを見に行ったり、ソーシャルグラフ上の友人の行動がタイムラインに表示されたりといった間接的・受動的な交流もあります。
大きく分類すると、ソーシャルアクションには、次の4種類があります。
- 協力
- 競争
- 自己表現
- コミュニケーション
ゲームが有する利用者を楽しませる仕掛け自体は、必ずしもソーシャル性を含んではいません。例えば、家庭用ゲームのほとんどは一人プレイで楽しむことが主体となっています。しかしながら、一人プレイばかりでは、ゲームを一旦クリアするとすぐに飽きられてしまいます。また、途中で飽きてしまうと、そのゲームに復帰することはほとんど考えられません。
そのため、ソーシャルアクションは利用者が途中でゲームを離脱しないようにすることや、場合によっては離脱した利用者を再度復活させるような役割を果たします。同時に、まだそのゲームをプレイしたことがない人も巻き込むことにも貢献します。
このように、ソーシャルアクションは利用者がそのゲームを継続的にプレイし続けるための「エネルギー」を供給する、というイメージで捉えることができます。