ボトムアップでのプロジェクト推進がビッグデータ活用のカギ
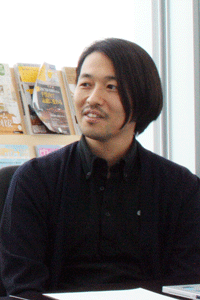
押久保:リクルートのビッグデータチームは100人という大所帯ですが、そもそも、どのような経緯で生まれたのですか。
西郷:5年くらい前に、データ分析に興味のある数人で始めました。それが徐々に大きくなって、100人になったという(笑)。でも、私たちのチームが、企業内のデータ分析チームの成功例になるなら、そのヒントは組織の成り立ちにあるような気がします。
押久保:というと?
西郷:世の中には、ビッグデータの取組をトップダウンで行っている会社が多いようです。しかしデータから宝を見つけるには、ビッグデータチームや事業部サイドが執念をもって分析し続けねばなりません。当社のビッグデータチームはボトムアップで生まれましたし、プロジェクトに必要な予算は事業部持ちです。組織や仕事がボトムアップで生まれているからこそ、上手くいくと思っています。
河本:当社のデータ分析チームも、15年前に生まれて以降、ずーっとボトムアップです(笑)。さらに、うちの組織は独立採算制なんですよ。データアナリシスセンターが「こんな分析しませんか?」と事業部に営業し、プロジェクト化されたら、分析にかかる人件費は事業部にもってもらいます。でもこの形を15年続けたおかげで、各事業部に味方が増えました。
西郷:継続することの大切さは、僕も感じています。データ分析って、一度見いだした結果を再度分析したり改善することで、さらなる効果を生むんです。一度降った雪が、固くなって地面に定着していくイメージに似ているので、これを僕は「根雪の重要性」と呼んでいます(笑)。さらに当社では、過去のプロジェクトの担当者が、ここ5年くらいで一気に出世しまして…当社のデータ活用において、彼らはとても重要な因子になっています。

河本:そうそう、過去の担当者の昇進はありがたいですね。もしくは担当者が異動して、別部署でデータ分析の重要性を訴えて下さったり。
西郷:ああ、それもありますね。担当者が異動したおかげで、同じ分析を別媒体で行って、さらに大きな効果が生まれることもありますね。これを私は「複利効果」と呼んでいます(笑)
押久保:これまでの積み重ねが、いまのお二人につながっていることがよく分かりました! ちなみにデータ分析プロジェクトが始まっても、一定の結果が出るまでには、結構なご苦労がおありだと思います。プロジェクトを成功させるには、何が必要ですか。
西郷:うーん、信念…ですかね。ネットビジネスって、最後の磨き込みが必要なんです。パッと見はキレイなサイトに見えても、少し使い勝手が悪いと、一気に評価が下がってしまう。それと同じで、データ分析の精度も「最後の磨き込み」で一気に変わる気がします。
河本:私も同じ考えですね。データを分析すると色んなことが分かりますが、ビジネスの意思決定に役立つのはごく一部なんです。なかには、データとビジネスの接点が全く見えてこないプロジェクトすらある(苦笑)。でも「ビジネスにつなげよう」という信念を持ち続けることで、事業部の期待に応えることができます。あとは、体力ですかね(笑)。



































