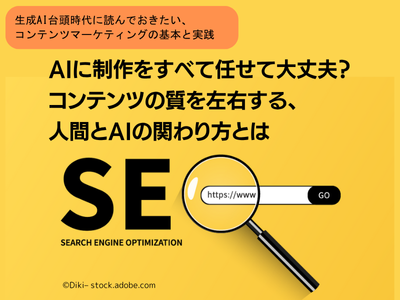2. (A≠A)で興味を持たせ、物語によって継続して見てもらう
以前、ライフネット生命とのコラボ企画で『どうしてパパはカメムシになったの?』というマンガをLINEで配信しました。タイトルや表紙からして違和感しかないでしょう。

このマンガは150万人に読まれました。このマンガを例に、「(A≠A)で興味を持たせ、物語によって継続して見てもらう」という原理を説明します。
「知っているモノが、別のモノに見える」というのは一つの謎かけです。その謎を解いていく物語を展開し、コンテンツを長く見てもらうようにします。人間は謎をかけられると、その謎が解けるまでは目が離せなくなるため、多くのマンガやドラマ、映画作品には冒頭でなんらかの謎かけがあります。
『どうしてパパはカメムシになったの?』は、タイトル自体が「パパ≠カメムシ」という形で、ストレートに謎かけしています。そこで興味を持たせ、経緯を描く物語に引き込みます。内容は、交通事故で死んだ父親がカメムシとなって生まれ変わり、父親を失って貧乏になっていく家族を哀しく見守る話です。
物語のパターンはそう多くありません。多くの物語は大切なモノを失った主人公が、それを取り戻そうと奮闘する中で成長していく話です。カメムシマンガの場合も、自分の死で家族を失った男が、それを取り戻せないことを知って反省する話です。
3. 物語のメッセージによってユーザーを変え、態度変容を起こす
あらゆる物語にはメッセージ(テーマ)があります。そもそもメッセージを元に物語を作るのですが、カメムシマンガのメッセージは「自分が死んだ後も、家族の生活は続く」でした。
ユーザーはカメムシを通して、自分が死んだ後の世界を体験し、家族のことをちゃんと考えてなかったことを後悔します。それによって、万一の備えについて気づきを与えます。ユーザーは物語の主人公に自分を投影しているため、主人公が変化するとユーザーも影響を受けます。実際にSNSでは「生命保険に入りたくなった」という感想がありました。物語を通じてメッセージが届くと、ユーザーの態度変容、行動変容が起こります。
さらに、コンテンツに社会性があるとより広く拡散しやすくなります。前述のJK用語動画は様々なテレビ番組で紹介されました。それらの番組を見ると「JK用語がわかるか街頭インタビュー」と「スタジオ内でのJK用語クイズ」という演出が多用されていました。ある時代の社会現象を切り取ったモノで、「街頭インタビュー」「クイズ」に展開しやすいものだとテレビでも取り上げられやすくなるのだなと勉強になりました。