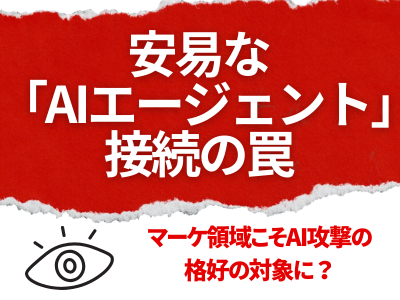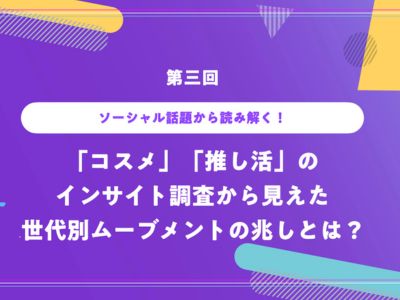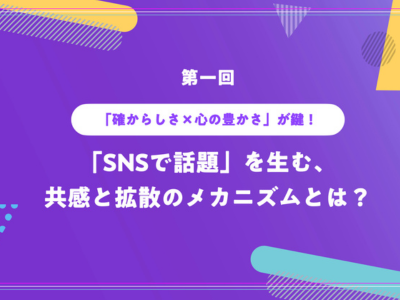※本記事は、2019年11月25日刊行の定期誌『MarkeZine』47号に掲載したものです。
広告クリエイティブには、企業の思想を反映させるべき

株式会社カラス代表/株式会社エードット 取締役副社長 兼 CBO 牧野圭太氏
2009年、博報堂に入社(2015年退職)。現在はカラス代表/エードットの取締役副社長兼CBO(Chief Branding Officer)。#ブランドジャーナリズムという「ブランドと社会を結びつける」クリエイティブ・コミュニケーションを標榜し、啓蒙している。「広告がなくなる日」を執筆中(2020年2月発売予定)。
――牧野さんがブランドジャーナリズムを標榜するようになったのはいつからでしょうか。
僕がブランドジャーナリズムを意識するようになったのは2年前です。きっかけは、カンヌの3部門でグランプリを獲得した「Fearless Girl」を目にしたことでした。
アメリカの金融会社が、ウォール街の象徴的な存在である牛の銅像「チャージング・ブル」の前に、胸を張って、微笑むように立つ少女の像を設置したんです。アメリカの企業における女性役員の少なさを訴えるこの像は、SNSで話題となりました。さらに、SNSで話題になっただけではなく、広告主の投資先企業で女性取締役が多く誕生するなど、問題の解決に向けて社会が動き出したんです。
SNSの影響力は年々強くなっているとはいえ、ここまでの波及効果が出せるものなのかと衝撃を受けました。
そして、なぜ「Fearless Girl」がこれほどの効果を上げられたのかを分析した結果、「ジャーナリズム精神が通底しているからなのではないか」という結論にたどり着きました。アメリカの経済を支えてきたウォール街で、女性が活躍できていないことに対して問題を提起したからこそ、ここまで拡散されたのではないかと。そこから、ブランドジャーナリズムの重要性を認識したんです。
――では、牧野さんはブランドジャーナリズムをどのように定義しているのか教えてください。
僕が定義するブランドジャーナリズムとは、「ブランドが意志と美意識を持ち、社会に対して批評を投げかけることで、ブランドのストーリーをファンと共有するコミュニケーション」を指します。僕はジャーナリズムを権力に対するアンチテーゼであり、弱者を救うために存在するものだと捉えています。そのため、ブランドや企業が本来あるべき社会を掲げた上で、弱者を救うための問題提起を行うのがブランドジャーナリズムだと考えています。
――牧野さんの定義のように、社会問題に対して批評性の強いクリエイティブを出すと、批判的な意見が噴出して炎上につながるケースもあり、企業としてリスクに感じる部分もあると思うのですが、いかがでしょうか。
もちろん、批判はないに越したことはありません。ただ、誰からも批判されない無難なクリエイティブを作っても、結局響かないと思うんです。批判を恐れず自分たちの思想を打ち出して、共感してくれるファンを増やしていくことが、デジタル時代のクリエイティブには必要だと考えています。
事業的にも、自社製品の機能だけではなく、思想を気に入ってくれる熱量の高いファンとのつながりを強固にするほうが成長につながるはずです。機能だけで争っても、コモディティ化が進んでいくだけなので、企業としての思想を提示し、覚悟を決めてコミュニケーションしていくべきだと思います。