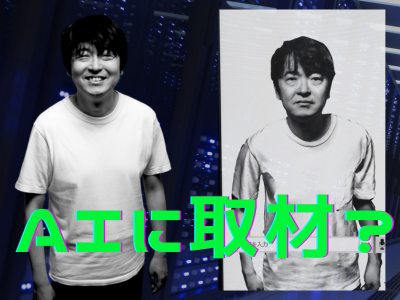CXM――顧客体験マネジメントの重要性
安成:そんなふうに感じられていたとは、意外です。ただ、確かに今、イベントに関わらず「心を動かす体験を提供できるか」が企業に問われるようになっています。その観点で、顧客体験をマネジメントするというCXMも提唱されているのだと思いますが、少し解説していただけますか?
祖谷:CXMを端的に言うと、顧客の視点で本当に望まれている体験を提供し続けることです。
これまでも、チャネルをまたいだ体験の設計が重視されてきましたが、あくまで1回のトランザクションに閉じて議論されていることが多かったのではないでしょうか。ですが、単発ではなく生涯にわたって自社と付き合ってほしいなら、トランザクションの発生時以外でも顧客を理解することが大事になります。その上で、一貫した整合性のある体験を提供し続けないと、それはいい体験になりません。
そうした根本的な発想の下で、チャネルもタイミングもメッセージも最適化した体験をマネジメントするのが、CXMです。それを支えるAdobe Experience Cloudも、どんどん進化しています。
安成:企業から届ける単発の体験を考えるのではなく、顧客のライフタイムの中で、自社の体験が全体としてどうあるべきかを考える、ということですか?
祖谷:そうですね。先ほど植野さんも「デジタルよりトランスフォーメーションが本質」と言われましたが、企業目線かつ単発で考えていくと、どうしてもデジタルという手段にフォーカスしがちです。でも、既に生活者はデジタルにすっかり親しみ、デジタル上で生み出される価値への期待値も上がっています。企業がその変わりゆく生活や価値観全体を捉えて、顧客が求めるサービスや困りごとへの解決策を提供できれば、成長の余地がすごく大きいと思います。あくまで、デジタルはそこに介在する手段です。
解消しつつある経営層の“DX幻想”
安成:なるほど。ひとつ、2020年9月にMarkeZine読者1,063人に回答いただいた調査結果を紹介すると、企業規模によらず4割近い企業が、「今後3年でマーケティング・販促予算は増える」と答えていました。特に中堅規模以下の企業では4割超で、デジタル投資が柱のひとつになると捉えると、DXへの遅れを課題と感じていることがうかがえます。ただ、祖谷さんが指摘されるように、手段が目的化しないようにすべきですね。

出典:『マーケティング最新動向調査2021』速報版レポート
祖谷:本当に、無駄な投資にならないようにしていただきたいと思います。
安成:植野さんはDX JAPANを設立されてすぐ後に、経営陣が抱く「DX幻想」を詳細に解説した連載記事を発表し、話題になりました(参考記事)。DXはデジタルマーケティングの強化だとか、データとAIですべてが解決できるといった7つの幻想を追い求めてしまうと、まさしく無駄な投資になってしまうと思います。
ただ、この半年でDXに向き合わざるを得なかった企業も多い中で、これらの幻想は晴れましたか? それともまだ残っている?
植野:幻想は晴れてきたと感じますが、その上で二極化しています。「DXとは単にデジタルツールで効率化することではない、経営アジェンダなのだ」と気づいて腹を括った企業と、現実はわかったけれど“DX疲れ”してしまった企業。
DX自体がバズワードになってしまい、最近ではDXと冠してもセミナーなどの集客が難しくなっているとも聞きます。これは、DXの議論が進んで具体的なフェーズになっているというポジティブな見方もできますが、飽き飽きしてきたネガティブな傾向もありそうです。

デジタルをトレンドとして捉えるなら、“DXごっこ”にしかならないと解説する
出典:定期誌『MarkeZine』第56号特集記事