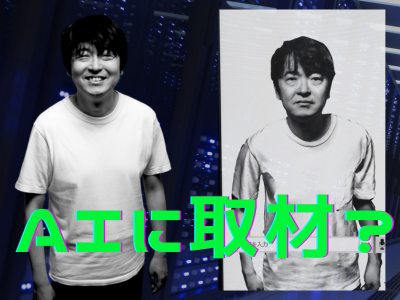新型コロナで注目される“無駄をそぎ落とす”発想
――まずは最近のマーケティングを取り巻く状況から、おうかがいしたいと思います。2020年に続き、現在もコロナ禍の影響は各方面に現れていますが、日本のマーケティング業界の議論、実践の方向性について、恩藏先生はどのようにご覧になっていますか。
恩藏:新型コロナによってさまざまな変化が起こりました。EC化やデジタル化、無人化率は一気に高まり、その流れは新型コロナ収束後も、以前の水準に戻ることはないでしょう。

外食産業のように、客数が減ったことで売上が減少したところも少なくないでしょうが、消費財企業などで話を聞いてみると、意外にも「売上は下がったものの、利益は持ちこたえられた」という答えが多く返ってきました。その要因は、テレワークへの切り替え、出張や残業の減少などで、出費を削減できたことにあるようです。また、事業そのものを見直す機会にもなり、さまざまな無駄に気づくことができたといった声も聞かれました。
こうした“無駄のそぎ落とし”を図っていく考え方に、「リーン」というものがあります。“リーン”は「ぜい肉をそぎ落とす」という意味をもつ言葉ですが、これはトヨタ自動車が生産ラインの無駄を徹底して排除するために確立した生産方式を起源としています。それまでの生産では、欠品をさせないために部品などを十分に在庫していました。しかしトヨタでは、在庫をあまり持たずに、必要な分だけ部品を仕入れてつくるという生産プロセスを取り入れました。
そこから導き出されたのがリーンプロダクションの概念で、さらに消費プロセスにも採用され、「リーンコンサンプション(消費)」の概念が生まれました。検索して各種情報を仕入れるなど、消費者による商品の購買プロセスにおいて、無駄や非効率を省こうとする動きのことです。
コロナ禍で注目が集まっているのは、マネジメントにおけるリーンなスタイルなのではないでしょうか。ただし何でも削るのではなく、それにより生まれた人材や資源を、どうやってより価値の出せる領域に向けていけるかが重要になっているのだと思っています。
無意識へのアプローチが重要度を増す
――コロナ禍の影響を受け、自分たちの組織やビジネスの無駄を削減し、より高い価値を創出しようという流れが出てきているんですね。消費者への向き合い方においてはいかがでしょうか。消費者のデジタルシフトが加速したと言われていますが、そのような中、何が勝負を分かつポイントになっているのでしょうか。
恩藏:現代が情報過多な状態にあることはよく言われていますが、コロナ禍によりデジタル上で過ごす時間が長くなり、ますます多くの情報に触れるようになった消費者が増えていると思います。日々、膨大な情報を受ける消費者に、少しでも抵抗なくメッセージを見てもらうためには、「押しつけがましくない」ものであることが大事です。そこで、私たちが取り組んでいるセンサリーマーケティング研究の知見が活かせるのではないかと考えています。
――センサリーマーケティングについて、詳しく教えてください。
恩藏:「センサリーマーケティング」とは、消費者の感覚(センサー)に働きかけることで、消費者の評価や行動に影響を与えようとするマーケティングの一手法です。
通常のコミュニケーションでは、外部から刺激(情報)を受けると、感覚レジスター(視覚・嗅覚・聴覚など、人の五感)に入り、頭の中に短期記憶としてとどまり、さらに長期記憶を含めながら情報処理し、その結果、ロイヤルティを抱いたり購入をするなどの流れになっています。しかしながら、センサリーマーケティングの場合は、短期記憶を経由せず、明確な意識なしに評価や行動に結びつくのが特徴です。つまり、テレビ広告などのように消費者による明確な意識を引き起こすことなく、消費者による購買を促すことができるのです。

たとえば、温度が人にもたらす印象がそうです。温かい飲み物を手に持って人と対峙すると、見知らぬ人であっても“温かみをもった心優しい人”と感じやすい。暖かさという触覚によって、情報処理をすることなく無意識に判断しているのです。
さらに、米国の大学内のカフェテリアで行われた実験によると、高い音程の音楽を流したときにはヘルシーな食事が売れ、低い音程だとジャンキーなものが売れる傾向が確認されています。このように、人間の感覚と購買の関連性がいろいろと明らかにされてきています。
コトラー教授の入門書にも「押し付けない」コミュニケーションの事例が
――恩藏先生はフィリップ・コトラー教授著作の翻訳プロジェクトを監修されていますが、近年のコトラー教授の研究の方向性と、このセンサリーマーケティングに関連性はあるのでしょうか。
恩藏:私が翻訳を担当していて、定期的に新しい版が出るコトラーのマーケティング入門書があります。その一番新しい版を読んでいると、理論やフレームワークはあまり変わらないものの、マーケティングの世界観が大きく変化している印象を受けます。というのも、本の中では、押し付けないコミュニケーションを意識した事例がいくつも掲載されているからです。
――押し付けないコミュニケーションを意識した事例について、詳しく教えてください。
恩藏:たとえば、米国では最近、広告会社的発想と映画会社的発想を融合させる取り組みが一般的になっています。ニューヨークのマディソン・アベニューは、大手広告会社が集まっていることで知られています。一方、映画会社が集まるハリウッド・アベニューにはヴァイン・ストリートが交差していることから、広告とエンターテインメントとの融合を「マディソン&ヴァイン」と呼んでいるのです。
広告とエンターテインメントの融合には、「アドバーテインメント」と「ブランデッド・エンターテインメント」という2通りの形態があります。アドバーテインメントの狙いは、広告そのものを娯楽性のあるものにするか、有益なものとすることによって、人々にその広告を見たいと思わせることです。たとえば、毎年、膨大な視聴者がスーパーボウルに釘付けになりますが、試合の観戦と同じくらい、そこで放送される娯楽的な広告にも見入っています。
また、広告というよりは短編映画や番組のような形態のコンテンツも作られるようになっています。ブランドのメッセージを伝えるプラットフォームは、ウェビソード、ブログ、オンラインの長尺動画、ソーシャルメディアの投稿など多様化しており、「広告」と「消費者によるコンテンツ」との間の境目が薄れてきているのです。
もう一つのブランデッド・エンターテインメントとは、ブランドを他のエンターテインメントやコンテンツに組み込み、一体化させることを意味しています。最もよく見られるのはプロダクト・プレイスメントで、ブランドを小道具としてテレビ番組や映画に組み込むのです。アメリカのドラマでは、登場人物がスターバックスのコーヒーを飲んでいたり、ジミー・ディーンのソーセージが登場したり、登場人物がチーズケーキ・ファクトリーで働いていたりします。
非対面推奨の環境で、センサリーの知見を活かすには?
――単に情報を押し付けただけでは、購買に進んでもらうことは難しい。その傾向はコロナ禍でますます強まっているのだと思います。一方で、コロナ禍では非対面のアプローチが推奨されていますよね。このような中、センサリーマーケティングの知見を実務に活かすには、どのようなアプローチがあるとお考えですか。
恩藏:対面コミュニケーションを補う手段の一つとして、紙のダイレクトメール(以下、DM)の持つ力を活かすと良いと思います。実際に、対面営業や店舗でのコミュニケーションが難しくなってしまった企業を中心に、DMを再評価する動きが見られています。私は2016年からDMをテーマとした産学連携の実証実験を監修してきましたが、さまざまなセンサリーの知見を活かせることが明らかになってきています。
たとえば、素材を変えることで触覚に刺激を与えることができるでしょうし、香りや音をつけることも可能でしょう。色というのも大きなポイントで、色によって人々の購買行動に影響を与えられることが実験でわかっています。これはコロナ禍の影響で利用が増加しているECを運用する際にも活かせる知識で、商品を掲載している背景の色、購入ボタンの色を変えるだけでも違いが出てくるはずです。
あるリゾートホテルでは、宿泊から2週間後に送るサンキューレターにそのホテルの香りを付け、楽しかった思い出を思い起こさせる取り組みをしています。
デジタル×センサリーでDMの送付効果を高める
――ここまで、コロナ禍でのマーケティングについてお話を聞いてきました。視点を活かしてコミュニケーションのシナリオを設計するときのポイントを教えてください。
恩藏:印象深い事例があります。2019年、「第33回全日本DM大賞」のグランプリに選出された、ディノス・セシールさんのパーソナライズDMの取り組みです。
2種類の施策があって、1つ目の「カート落ちDM」は、顧客が欲しいと思っているタイミングを逃さずに、パーソナライズされた情報を届けるというものです。具体的には、ECで商品をカートに入れたのに購入せず離脱した顧客に向け、最短24時間でその商品を含め3点の案内が送付されます。
2つ目の施策では、AIを活用して、顧客が購入した商品に似たアイテムを着ている写真をInstagramの一般投稿から抽出して、その着こなしアイテムに近しいものを提案します。

パーソナライズされた情報が欲しいタイミングで届くDM
クリック/タップで拡大
両施策とも、まさにデジタル×アナログが統合された内容になっており、コンバージョンとレスポンス率を向上させていました。今後のDMの方向性としても、デジタルを活かしながら、今回お話したようなセンサリーの知見を上手く取り入れられるといいのではないでしょうか。
いろいろな手段が考えられるので、それらをいかに上手く組み合わせ、使いこなせるかが大事になってくるのかもしれませんね。
――最後に、これまでに恩藏先生は日本郵便の「デジタル×アナログ振興プロジェクト」を率いてこられ、様々な事例や成果を出されてきました。そうした事例をセンサリーマーケティングの視点で読み解くポイント、活かしていくためのアドバイスがあれば教えてください。
恩藏:プロジェクトでは、約4年間にわたって、DMとデジタルとの組み合わせによる効果を探る実証実験を行ってきました。
そこでは、DMとEメールを送付する順序によって効果や受け取る側の感情が変わる“順序効果”の話など、さまざまな学びがありました。どの結果も、普遍化して使える部分が多い内容だと思います。
これまで蓄積してきた事例をマーケターが読み解くときは、インプリケーション、つまり、その結果をどう実務に生かせるかという視点を意識していただきたい。どうしてその結果になるのか、そのメカニズムや背景を深く理解することが自社のビジネスに応用できることにつながるのではないでしょうか。
日本郵便のデジタル×アナログ振興プロジェクトとは?
デジタル、データによりコミュニケーション、マーケティングの環境が大きく変わる中、アナログだからこそできること、DMだから伝わることとは何か。デジタルとアナログの組み合わせにより、より心に響くコミュニケーションを実現できるのではないか。日本郵便ではこのような問いをもち、2016年よりデジタル×アナログ振興プロジェクトとして、実証実験、産学連携、その結果を広くお伝えするPR活動を続けています。