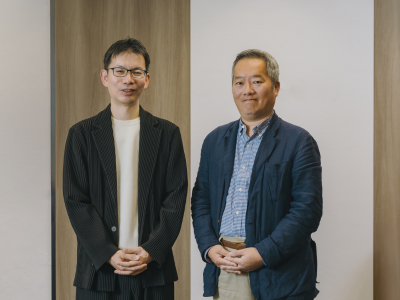会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
新規会員登録無料のご案内
- ・全ての過去記事が閲覧できます
※プレミアム記事(有料)は除く - ・会員限定メルマガを受信できます
- ・翔泳社の本が買える!500円分のポイントをプレゼント
この記事は参考になりましたか?
- 家計簿発!実購買データから読み解く消費者インサイト連載記事一覧
-
- 支出データから読み解く、Z世代の消費のリアル~特徴的な4つのクラスター~
- コロナ禍で狭まる、生活者の買い物エリア 支出項目×生活者属性から傾向を探る
- ハッシュタグのデータから「なぜ買ったか?」を捉える!世代別に見る、消費行動の裏側とは
- この記事の著者
-

亀岡 洋介(カメオカ ヨウスケ)
2001年外資系アパレル通販会社でデータ分析、レポーティング、計画管理業務に従事。2019年よりロコガイド社に入社し、ビジネス企画開発に所属し、トクバイサービスにおけるデータ分析~分析を通じた改善提案を行う。2021年10月よりZaimを兼任し、データ分析、データを活用したプロダクト開発に従事。
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア