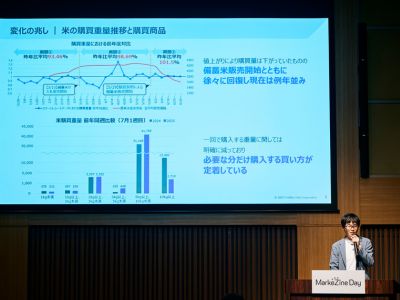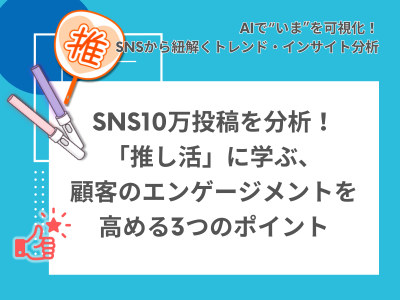マーケター職の報酬の相場感とは?
──マーケターという職種は、比較的転職が多くなりやすいため、報酬の相場感などの見極めも必要ですよね。
塩見:はい、必要だと思います。その際、転職者と転職先企業の双方で注意したいのが、マーケター本人ではなく、所属企業の要素で現報酬が設定されているケースが多いことです。困っている企業ほど高く設定しがちなため、マーケターが少ないという理由だけで低スキルなのに高報酬な方に出会います。逆に、優れたマーケターなのに所属企業の制度が理由で低い報酬になっている方もいます。採用活動においては、現年収に引っ張られ過ぎず、マーケター本人の市場価値に応じて評価するように努めています。
──リクルートでは、マーケターの報酬をどのように決めているのでしょうか。
松尾:能力+期待で報酬が決まる「ミッショングレード(以下、MG)制」を採用しております。年次や経験にとらわれず、高い価値の職務を担う人は高いMGになり、高い報酬を得られる仕組みです。

松尾:欧米で行われている「ジョブ型」とは異なり、MG制度は「人」が起点になります。当社では、個人の能力に期待分を上乗せした「期待役割」でMGを設定します。できる役割だけでなく、できるだろう役割、できて欲しい役割を設定するイメージです。
──人に合わせてミッションをパーソナライズするのですね。
松尾:そうですね。MGを決めるときは、個人の能力だけでなく状況や本人の希望を加味して、半年ごとにメンバーと上長がしっかり会話することからはじめます。
たとえば、さらなる成長を目指したいメンバーに対しては、能力を見立てた上で、「できるかもしれない」期待をもって仕事を任せます。反対に、介護や子育てなど家庭の事情で一時的に仕事の負荷を下げたい場合、メンバーの申し出を考慮して役割の期待レベルを下げて設定することもあります。
職務要件定義書で、期待や役割を明確に示すMG制
──MGを定義する際、評価の揺らぎをなくすために行っている工夫はありますか?
松尾:共通のモノサシとして、「職務要件定義書」を作っています。これは、どのような職務を担えばどのMGに当たるかを言語化したもので、メンバー用の職務要件定義書は上長だけでなくメンバー自身も見られます。マーケティング室では、職種によって8種類作成しています。
塩見:具体的にはスペシャリストマーケター、ゼネラリストマーケター、コンテンツディレクター、メディアプランナー、PRプランナー、アートディレクター・クリエイティブディレクター、スペシャリスト流通プロセスマネジメント、ゼネラリスト流通プロセスマネジメントの8種類ですね。
──職務要件定義書には、どんな期待役割が書かれているのでしょうか。
塩見:ざっくり言うと、一番下のMGは「標準的な業務をしっかりこなせること」。1つ上のMGになると「振り返りや改善、費用対効果の立証を自らできること」、もう1つ上になると「課題設定が自らできること」という感じで続いていきます。そこに職種によって細かいニュアンスが加わっていく形です。

塩見:マーケターの中にも複数の職種がありますし、スペシャリストなのかゼネラリストなのかでも期待役割は変わってきます。そのため、大きな1つのモノサシだけでは示せません。一方で、細分化し過ぎると評価者によってブレてしまいます。試行錯誤を経て現在は8種類に落ち着いていますが、定期的な見直しはこれからも続けていきたいと考えています。