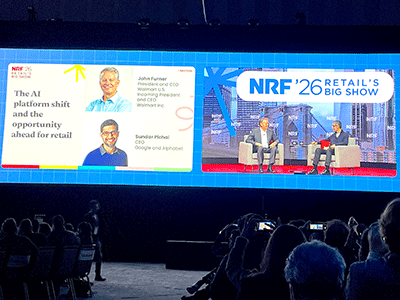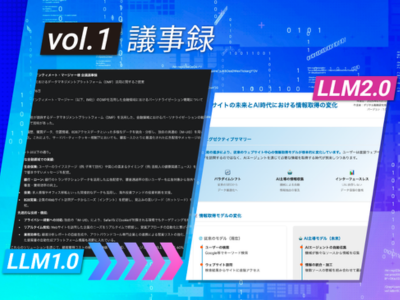本記事は『Webアンケート調査 設計・分析の教科書 第一線のコンサルタントがマクロミルで培った実践方法』(エイトハンドレッド、渋谷智之)の「第2章 Webアンケートの実施ステップ」から抜粋したものです。掲載にあたって一部を編集しています。
Webアンケートが手軽に実施できる時代に
定量調査は「インターネット調査」が主流に
インターネットが普及し始めた2000年、オンライン・マーケティング・リサーチ専業企業として、マクロミルは創業しました。インターネット調査の登場は、訪問調査や郵送調査が主流であったマーケティングリサーチ市場に大きな変化をもたらしました。
図2.1.1に、日本マーケティング・リサーチ協会(JMRA)が毎年公表している『経営業務実態調査』から、アドホック調査を100%とした場合の調査手法別売上高構成比を示しています。訪問調査、郵送調査、インターネット調査、定性調査のみ掲載しています。

インターネット調査は、2004年に郵送調査、2005年に訪問調査のシェアを抜き去り、2022年は55%に達しています。リーマンショック等による一時的な落ち込みはありますが、マーケティングリサーチの市場規模は拡大しており、インターネット調査がリサーチの裾野を広げた原動力になっています。また、定性調査も着実にシェアが増加しています。日本のマーケティングリサーチは、インターネット調査と定性調査に収斂されています。
アンケート画面が手軽に作成できる時代が到来
ゼロ・パーティー・データ取得の一環として、自社商品・サービス利用者や自社会員を対象に、アンケートを実施することがあります。調査会社はこのニーズに対応すべく、アンケートASPを提供しています。マクロミルが提供するアンケートASP『Questant』では、主要テーマのアンケートのテンプレートを無料公開しています(図2.1.2)。

上記に加えて、GoogleやMicrosoftなどのプラットフォーマーもアンケート機能を提供しています。Microsoftのアンケート機能「Microsoft Forms」はMicrosoft Teamsと連携しやすく、タブを切り替えるだけで、アンケート結果を閲覧することができます。また、設定次第で回答者の識別が自動的に可能であり、アンケート以外のデータとの紐づけも容易になっています。Webアンケートが手軽に実施できる環境が整備されています。
Webアンケートは簡単に見えて、奥が深い
リサーチ初心者が陥りがちなミスとは?
Webアンケートの敷居が低くなり、「アンケートは簡単」というイメージが広がりました。読者の中にも、役職者や同僚から「アンケートを作っておいて」と指示された経験がある方も多いと思います。
筆者がインターネット調査に携わり始めた2000年代前半は、事業会社の調査部、広告代理店のリサーチ経験のあるプランナー、調査会社からの調査依頼が中心でした。現在は、リサーチ初心者もWebアンケートを活用しています。その結果、自己流でアンケートを作成・集計・分析する人が増加し、筆者から見ると「もったいない」と感じるシーンが多くなりました。
本節では、リサーチ初心者が陥りがちなミスを6つ取り上げたいと思います(図2.2.1)。

「何を決めるか」を具体化せず、Webアンケートを実施して後悔する
マーケティングリサーチの出発点として実施されることが多いのが「現状を把握する」リサーチです。「実態がよくわかっていない」という理由からリサーチを企画し、簡単に実施できるWebアンケートが選ばれます。
その際、リサーチ企画書を拝見すると、調査目的が「〇〇の基礎資料とする」と記載されていることが多いです。何もわかっていないのでアンケートをしたい気持ちはわかります。ただし、最初のタイミングで、調査結果から「誰が、いつ、どこで、どのような目的で活用し、何を決めたいのか?」を具体化しておく必要があります。
目的が不明確な場合、アンケートはありきたりな一般論に終始しがちです。調査結果の大半が想定内になり、報告会で「で、どうしたらいいの?」「結果はわかるが、新しい発見がない。調査した意味あったの?」という厳しい言葉が並ぶ可能性が高まります。何もわかっていないならば、事前に定性調査を実施し、検証すべき仮説を立案してからWebアンケートを実施したほうが効果は高いです。目的を明確にせず、Webアンケートを実施すると失敗する確率が高まります。

Webアンケートの実施ステップ
Webアンケートの実施ステップを理解する
前節で取り上げたミスを回避するためにも、Webアンケートの実施ステップを理解しましょう。図2.3.1に、Webアンケートの実施ステップを掲載しています。

本節以降、「調査会社のモニタ(アンケート会員)を使ったインターネット調査」を前提に説明していきます。自社会員やサイト訪問者などに直接調査する場合も、基本的な考え方は同じになります。
出発点は「リサーチで明らかにすること」を具体化する
最初のステップは、マーケティング課題を整理し、リサーチで解決できる(わかる)領域とリサーチしても解決できない(わからない)領域に切り分けます。リサーチでわかる領域を特定した後は、調査背景と調査目的の違いを理解しながら、リサーチ課題を具体化します。リサーチ課題の分解の精度が、マーケティングリサーチの成否に大きく影響します。
リサーチ課題を解決できる「リサーチ企画」に落とし込む
リサーチ課題を明確にした後は、その課題を検証できる調査対象者の設定、割付とサンプルサイズ、調査項目などを検討します。そして、これらをリサーチ企画書として仕上げていきます。このタイミングで、調査項目が思うように浮かばない場合は、対象者の理解を深める目的で、定性調査の実施を検討します。
回答者が「誤解しない調査票」を作成して、アンケートを実施する
リサーチ企画で検討した調査項目をもとに、調査票を作成します。調査票の作成はブラックボックス化しやすい領域ですが、調査目的や調査仮説を調査項目に分解する、調査項目の流れを考える、回答者が誤解しない質問文と選択肢を作成するなど、ある程度パターン化することができます。
調査票を作成した後は、Web調査画面を作成します。そして、スクリーニング調査、本調査を実施し、設定したサンプルサイズを回収します。
アンケート結果を「集計・分析」し、「リサーチ課題に結論」を出す
アンケートを実施した後は、全体集計・クロス集計をもとに、集計結果を読み込みます。最後に「で、どうしたらいいの?」という結末にならないよう、クロス集計を中心にデータを丹念に読み込むことが重要です。リサーチ課題に結論を出し、ネクストアクションを検討するまでをワンセットにしましょう。最後に、社内関係者に共有するため、レポートを作成し、必要に応じてプレゼンを実施します。
Webアンケートの成否の7~8割は「リサーチ企画」が握る
筆者の実務経験から、Webアンケートの成否の7~8割は「リサーチを企画する(マーケティング課題の整理、リサーチ課題の明確化、リサーチ企画書の作成)」の段階で決まると断言できます。
実は、筆者も駆け出しの頃、リサーチ課題の重要性を理解できていませんでした。目的が不明確な状態でインターネット調査を実施し、レポートを作成する中で、違和感を持ち続けた時期がありました。
試行錯誤を続ける中、「最初の課題設定が甘いから、その後の流れも良くないのではないか?」ということに気づきました。これが筆者の大きな転機でした。それからは「この調査で、何がわかれば成功ですか? 嬉しいですか?」と問いかけることが口癖になりました。その結果、リサーチ企画~調査票作成~集計・分析のプロセスが、まるで流れ作業のようにスムーズになりました。

調査票を作成する前に「考え抜く」ことを忘れない
統計学の有名な言葉に「GIGO(Garbage In Garbage Out)」があります。ゴミを入れれば、ゴミが出てくるという意味です。インプットするデータがゴミならば、どんなに素晴らしい解析をしても、出てくる結果はゴミになります。これはマーケティングリサーチの世界でもあてはまります。リサーチ企画で間違えると、後工程で取り返しがつかなくなります。
リサーチ課題が曖昧なまま進行すると、調査項目の抜け漏れが生じる可能性が高まるだけでなく、集計データの海に溺れることになります。本調査で20~30問聴取したのに、データ分析に活用したのは半分程度ということになりかねません。このようなケースは案外多いです。
調査対象者の詰めが甘いと、本来の分析対象者以外の回答者が含まれてしまい、調査結果の信憑性が下がります。具体的には、集計・分析の段階で、「その他」の割合が高いことに気づき、「その他」の自由記述欄を確認したところ、「購入していないのでわからない」といった分析対象外の回答が含まれていることがあります。リサーチ企画がリサーチの成否を決める。これだけは絶対に覚えておきましょう。

インターネット調査の仕組み・特長
対象者をスクリーニングできるインターネット調査
図2.4.1に、調査会社が提供するインターネット調査の仕組みを掲載しています。インターネット調査は、調査会社が保有するモニタを対象に、スクリーニング調査と本調査を実施する流れが一般的です。

調査会社は、アフィリエイトやポイントサイト、金融機関・家電量販店・通信キャリアなどとの連携を通じて、アンケートに回答することを許諾したモニタを集めています。
実際の調査は、スクリーニング調査と本調査に分かれます。スクリーニング調査は本調査対象者を抽出するための事前調査で、3~10問程度で実施することが多いです。また、スクリーニング調査は、市場規模などの市場構造の把握にも活用されています。本調査は、スクリーニング調査をもとに抽出した数百人~数千人を対象に、20~30問程度で実施することが多いです。
アンケートに回答したモニタは、設問ボリュームに応じたポイントを付与され、銀行振り込みによる換金、商品との交換、提携ポイントへの移行、人道機関や基金への寄付などの使い道があります。
インターネット調査の特長は「対象者の条件設定」「レアサンプル確保」
インターネット調査は、訪問調査や郵送調査よりも費用が安く、スケジュールが短い点が最大の特長です。リサーチ企画の立案から集計結果の納品まで1カ月~2カ月で完了することが多いです。費用も従来の10分の1ぐらいで実施することができます。調査期間が短縮されることで、タイムリーな状況確認が可能となりました。新商品の上市直後の製品追跡調査、顧客満足度調査などが多く実施されています。
インターネット調査は、スクリーニング調査と本調査を分けることで、「希望する調査対象者を一定数確保しやすい」「出現率が低いレアサンプルを確保しやすい」といった点も大きな特長です。対象者のサンプルサイズが増えることで、多様な分析が実施できるようになりました。

インターネット調査の留意点
インターネット調査の「選択バイアス」に留意する
インターネット調査にも留意すべき点があります。その代表が「選択バイアス(カバレッジ誤差)」です。調査会社のモニタは「インターネット利用者かつ、調査協力として登録している人」が母集団になっており、世の中の一般的な傾向と異なります(図2.5.1)。

調査会社が保有するモニタは、インターネットのリテラシーが高く、高学歴の割合が高くなります。アンケートで情報収集源を聴取すると、インターネット関連が上位を占めることが多いです。
では、インターネット調査は代表性がないため使えないかというと、そうではありません。2006年の住民基本台帳法の改正に伴い、住民基本台帳の閲覧が原則非公開になりました。また、代表性が高いと言われた訪問調査でも回収率が50%を下回る状況が見られ、本当に母集団を反映しているかが不明といった指摘もあります。そのため、母集団の違いを意識して数値を読むことが必要です。これは自社会員やサイト訪問者に調査するときもあてはまります。
「代表性」よりも「安定性」を意識することが大事
代表性が高い調査の実施が難しく、どの調査手法でも「偏り」は避けられない現状においては、「代表性」よりも「安定性」を意識することが重要です。常に同じ「偏り方」であれば、過去の調査結果や競合との比較は可能になるからです。
図2.5.2に、マクロミルが毎週水曜日に1,000名のマクロミルモニタを対象に実施しているMacromill Weekly Indexの「個人消費金額」と、総務省の家計調査の消費支出と比較したグラフを掲載しています。個人消費金額と2人以上世帯の消費支出といった違いがありますが、同じ波形を辿っています。筆者の経験でも、世の中の変化と調査結果が連動していることが多いです。そのため、調査対象者、調査会社をあまり変更せず、安定性を重視することが大事です。

顧客は善意のウソをつく。意識と行動のギャップを埋める
アンケートは、顧客の頭の中を理解する手段です。ただし、顧客は「善意のウソ」をつきます。その代表例が「新商品の購入意向」と「実際の購入率」のギャップです。
10年以上前の話ですが、「今後3カ月以内に、家電製品を購入したい」と回答した人に、3カ月後に、「直近3カ月以内に、購入した家電製品」を聴取したことがあります。製品で若干の差異はありましたが、実際に購入したのは2割前半という結果でした。
別の事例では、商品・サービスの離反顧客に、アンケートで離反理由を聴取すると、「価格が高いから」が上位になることが一般的です。ただし、デプスインタビューを実施すると、「商品の特徴が伝わっていなかった」「商品の使い勝手・使用ステップの煩雑さ」のほうが影響しているといったケースが普通にあります。
意識と行動のギャップを埋めた需要予測事例
これまでの実務経験から、筆者には「顧客の行動は、正しい計算式と正しい数値があれば、ある程度は予測可能」「人間の心理はアンケートだけでは難しい。定性調査で補完すべき」といった持論があります。
前者の行動予測(需要予測)において、印象に残っている事例を紹介します。それは、「開発予定の商業施設に、大型のランドマーク施設を建設するにあたり、商業施設の初年度利用者数を予測してほしい」という案件でした。その開発に投資すべきかを決めるにあたり、大手デベロッパーが公表している初年度利用者数が本当なのかを検証したいといった案件でした。
そこで、リサーチを企画する際に、ランドマーク施設の利用意向だけでなく、行動率への転換率、商業施設からの距離(利用確率は距離の2乗に反比例する)、開業予定月などの変数をもとに予測式を作りました。そして、調査結果をもとに、一切の手心を加えることなく、需要予測を算出しました。その結果は、デベロッパーの公表数とは誤差率10%未満で、開業後の実績とも大きくずれていませんでした。
別の案件でも、計算式をもとに分解し、2次データ、なりすましなどのデータクリーニングした数値を入力していくと、納得感がある需要予測(行動予測)になることが多いです。