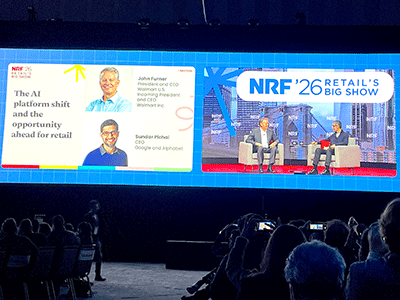着物への思いを強くした成人式での出来事
皆さんは、着物リメイクアパレルブランド「Keniamarilia(ケニアマリリア)」をご存知だろうか。同ブランドでは、一着の着物から仕立てた一点物のスカートやスカーフ、シャツを生産・販売している。デザイナーと運営会社の代表取締役を務めるのは、ブラジル・サンパウロ生まれの座波ケニアさんだ。

4歳で日本に移住した座波さんは、幼少期よりファッションに興味を持ち、洋服の絵を描いたりオリジナルスカートを自作したりしていた。将来の夢はデザイナーだったと言うが、着物リメイクブランドのデザイナーを務めるまでのストーリーは長い。
「着物にずっと興味はありましたが、外国籍の自分が日本の伝統文化の象徴でもある着物を気軽に着て良いものなのか、触れて良いものなのかがわかりませんでした。そんな中、成人式で初めて振袖を着ることができたんです。その際にお世話になった着付けの方々がとても優しく接してくれて。『私でも着て良いんだ』『この文化に触れて良いんだ』と感じることができたんです。このときに、着物への思いはより強いものになりましたね」(座波さん)
成人式で着物への思いを強くした後、座波さんは服飾の専門学校を卒業し、生産管理の担当者としてアパレル産業に従事するが、そこでアパレル産業の現実を目の当たりにする。
ハレの日のニーズだけでは衰退を免れない
2000年代前半、アパレル産業では生産拠点を国内からより安価に対応可能な中国をはじめとするアジア諸国へ切り替える流れが加速した。時が経ち、アジア諸国の工場が単価を引き上げたため、国内生産に再び戻そうとする動きが生まれたが、時既に遅し。希少な縫製技術が継承されることもないまま多くの国内工場が閉鎖され、国内で生産したくてもできない現実が待ち構えていた。
「このような状況は着物産業でも起こるのではないかと思いました。技術を、その継承者を、つまり文化そのものを次世代に引き継がなければ、着物は永遠に失われてしまうのではないか──そう感じたんです。もう悠長なことは言っていられないと」(座波さん)
着物産業の存続を危ぶんでいた頃と時を同じくして、座波さんは自身が衣装を担当していたバンド「HEAVENESE」のライブに帯同する形で、ドバイやエチオピアを訪問した。現地で座波さんが感じたのは、日本の文化と着物に対する熱狂的な支持だ。国境を越えて人々を引き付ける着物。この文化の継承を生業にしようと座波さんは決心した。
斜陽とも言える着物産業で文化を残すためには、従来どおりの“ハレの日ニーズ”に頼って着物を売っていては不十分だ。テコ入れによって、着物産業の本格的な底上げを図る必要がある。テコ入れの策を考え抜いた末に座波さんが導き出した結論は「自身で新たなブランドを立ち上げ、着物を広める」というアクションだった。