エントリー層の20代をターゲットに、楽しい飲酒体験を
「スマートドリンキング(以下、『スマドリ』)」とは、飲む人も飲まない人も一人ひとりが、体質や気分、シーンに合わせて適切なお酒やノンアルコールドリンクを選択できる飲み方だ。この考え方を提唱し多様な飲酒文化の創造を目指すアサヒビールは、2025年4月11日に方針説明会を開催。スマドリマーケティング部長 兼 スマドリの代表取締役社長を務める高橋徹也氏が、2025年の戦略テーマや取り組みについて説明した。
なおスマドリは、2022年にアサヒビールと電通デジタルによって設立され「スマドリ」の浸透および関連商品のコミュニケーション支援などを行っている合弁会社だ。

まず高橋氏は、2024年までの取り組みの進捗と中長期目標を紹介した。「スマドリ」の考え方の認知率は約50%まで達成され、2025年度は60%を目指すという。中長期的にはアルコール度数3.5%以下の「スマートカテゴリー商品」の購入者3,000万人達成を目標とするとともに、今後はメインターゲットに飲酒のエントリー層である20代を定めた。
同社が行った調査の結果、「最初のお酒との出会いや体験が楽しかった」と考える人々は51%となり、以降飲酒への関与度が高まっていった。一方、最初の飲酒体験が「残念な思い出になってしまった」と考える49%は、その後飲酒への関与度が低くなることがわかったのだ。
「良い体験をすることで今後の飲酒文化への関与度が高まっていくことから、当社はエントリー段階でより楽しい飲酒体験を提供できる商品やサービスの提供に取り組んでおります。中でもアルコール度数3.5%以下の領域に注力することで、飲む人だけでなく飲まない人も楽しめる『スマドリ』文化の浸透を実現したいと考えております」(高橋氏)
次に、エントリー層が飲酒に対して感じる障壁として、高橋氏は以下の4つを挙げた。これらの課題に対し、お酒を身近な存在へ感じてもらう働きかけを積極的に行っていく方針だ。
(1)ノンアルを選択したときの周りの視線(「逃げ」や「甘え」と思われそう)
(2)自分向けではないというマイナスイメージ
(3)味への不安
(4)飲用できる場の少なさ
2025年度の戦略テーマは「ノンアルのポジティブイメージ醸成」
続いて、2025年度の戦略テーマとして「ノンアルコールのポジティブイメージを醸成する」が示された。このテーマに向け、同社ではコミュニケーション施策や共創プロジェクト、ポップアップイベントといった取り組みを進めていく。
コミュニケーション施策では「ノンアルコール・微アルコール商品は、飲まない人にとっても自分らしく楽しめる選択肢」というポジティブイメージ醸成のため、新たなコミュニケーションを飲食店や小売店中心に推進。「ノンアルって誰のもの?」をキャッチフレーズに、お酒を飲む・飲まないの枠を超えて手に取りたくなるような商品の魅力を発信していく。
「スマドリ」共創プロジェクトでは、アサヒビール、よしもと芸人(吉本興業)、若者の3者でスマドリの原体験をアイディエーションする。お酒の飲み方や環境作りのアイデアをオリジナル番組(デジタル)で討論するなど、ターゲット層とのタッチポイントやイメージの創出に取り組み、行動変容へつなげる。
ポップアップイベントとしては、期間限定の体験型イベント「#SUMADORI Me(スマドリミー)」を愛知・大阪・福岡と韓国ソウルで実施。「私らしい楽しみ方を見つけるために“自分を知る”」をコンセプトに、「モノ」だけではなく「コト」の体験を組み合わせたコミュニケーションを通して、お酒を飲まない人の「スマドリ」の原体験を作っていく。
さらに同イベントでは、お酒を飲む人と飲まない人が一緒に楽しめる場所として2022年からスマドリが渋谷で展開している「SUMADORI-BAR SHIBUYA」の運営ノウハウを活用する。また国内に加えて、日韓のトレンドが若者の中でポジティブに循環している現状を背景に、韓国のソウルでの実施も決定した。
イベント内ではSUMADORI-BAR SHIBUYAで提供する「シグネチャーカクテル」やアサヒビール商品を使用したノンアルコールの「カンパイカクテル」、「オリジナルカクテルワークショップ」を提供する。オリジナルカクテルワークショップでは、アルコールに対する体質を把握できるアルコールパッチテストを実施した後、自身に合うアルコール度数や好みのテイストのカクテルを自ら作ることができる。

これらの取り組みを通して、飲まない人にもスマートカテゴリー商品を積極的に選択肢に取り入れてもらえる環境を作り「お酒とのいい関係」を創出。「飲酒の有無に関わらず、お客様がお酒とのいい関係を長く楽しめる文化や社会を目指していきたいと考えています」と高橋氏は語った。




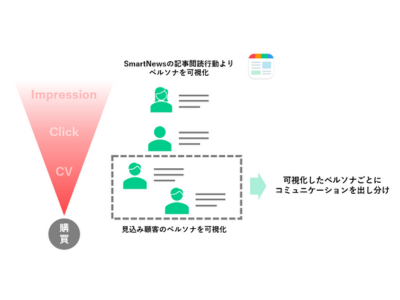










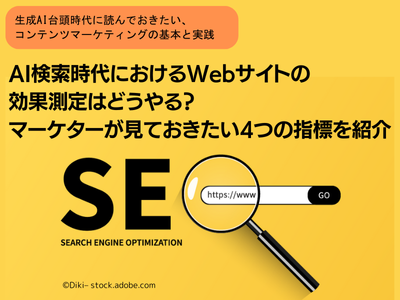



















.jpg)
