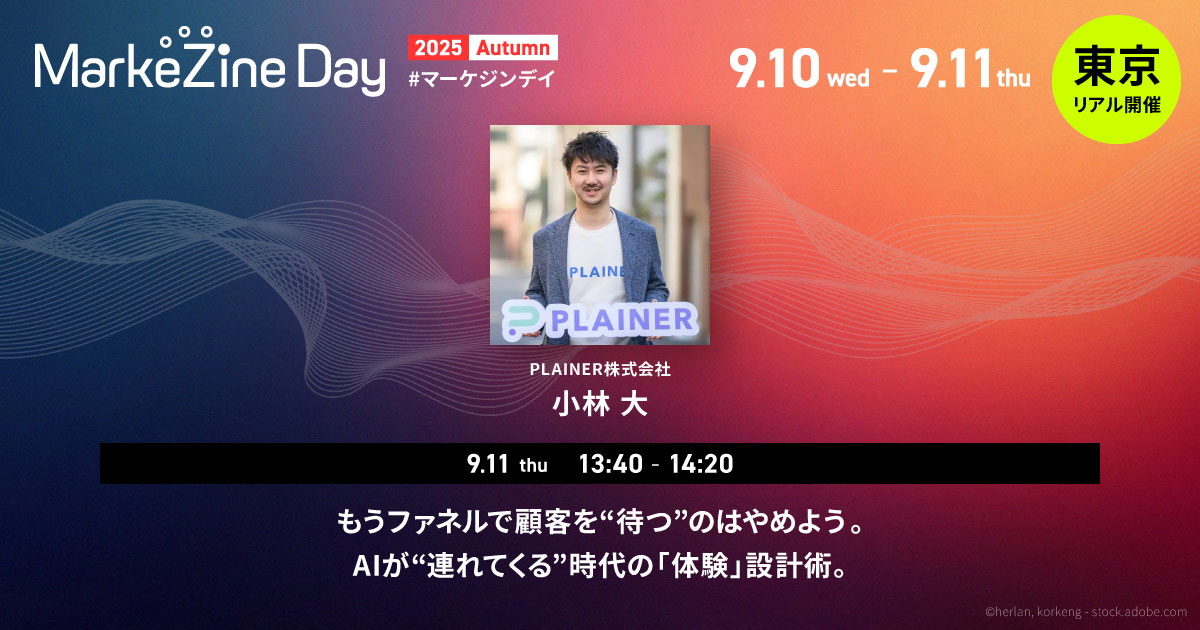AI時代、コンテンツマーケティングは戦い方が大きく変わる
MarkeZine:AIによる情報収集が当たり前のものとして浸透し、BtoBマーケティングにも大きな変化が生じています。今回は特に大きな影響を受ける「コンテンツマーケティング」にフォーカスし、お話をうかがいます。まず、小林さんは従来のBtoBコンテンツマーケティングにはどのような課題や限界があると考えていますか?
小林:従来のBtoBコンテンツマーケティングは、ホワイトペーパーや事例記事などの「読み物」が主流でした。しかし、なかなかCV増加や質の高いリード獲得に結び付かず、コンテンツの更新も停滞しがちです。
ソフトウェア領域に関しては、日本国内だけで1万種以上の製品が存在していると言われています。比較検討中のユーザーが「とりあえずDLしただけ」「読んでもよくわからない」となってしまうのは、想像に難くありません。機能差のみならずサポート体制や将来性といった無形価値を文章で伝えるのは難しく、似通った構成・表現が差別化を阻害します。
結果、判断の先延ばしや営業担当の人柄などによる選定が起き、製品の価値が十分に届かないという「認識ギャップ」が生じるのです。私たちはこのギャップこそBtoBマーケティング最大のボトルネックと捉えています。

上智大学法学部卒業後、フリー株式会社に新卒入社。初期配属のインサイドセールスチームで、50名中トップの成績を残した後、事業戦略として計画/戦略の策定から実行までを担当し、所属した全期で目標達成。その後モバイル版freeeのビジネスオーナーとして、YoY300%の成長を牽引。その際、プロダクトを活用した顧客コミュニケーションのインパクトを知ると同時に実行ハードルの高さに大きな課題感を持った。誰もがテクノロジーの進化を喜びとして迎え、自然に共生できる未来の実現を目指し、2019年にPLAINERを創業。
MarkeZine:AI時代、そうした従来の課題はどのように変化するでしょうか?
小林:生成AIの活用により、コンテンツマーケティングにおけるマーケターの業務は大幅に効率化されつつあります。ただ一方で、ユーザー側もAIを日常的に活用しており、情報収集の環境が変わっていることを無視してはなりません。検索行動にAIが組み込まれるようになり、ただ閲覧数を稼ぐ従来型コンテンツは現に通用しづらくなっています。
既に、現在のユーザーは、営業担当者と接触することなく購買プロセスの8割以上を完了させ、もはや従来のマーケティングファネルを辿らないそうです(出典)。この「AI主導の発見」時代においては、検索エンジンやAIに「価値が高いコンテンツである」と評価してもらえるか、推薦される質と多様性を担保できるかが鍵となります。
MarkeZine:BtoBコンテンツマーケティングは「AI」を対象者として意識することが、必須になっているのですね。
小林:そうです。AIの推薦枠に入れるか否かが事業成長を左右する時代と言えるでしょう。テキストの大量生産だけではWeb上で差別化できず、人にもAIにも「本当に伝わるか」がコンテンツマーケティングの勝負となっています。
予告:MarkeZine DayにPLAINER小林大氏が登壇
9月10日・11日に開催するマーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」に、PLAINER 代表取締役の小林大氏が登壇。『もうファネルで顧客を“待つ”のはやめよう。AIが“連れてくる”時代の「体験」設計術。』と題し、より具体的に体験軸のBtoBマーケティング実践に向けたポイントを解説します。
セッションの詳細をチェック・事前登録の上、ぜひご来場ください。
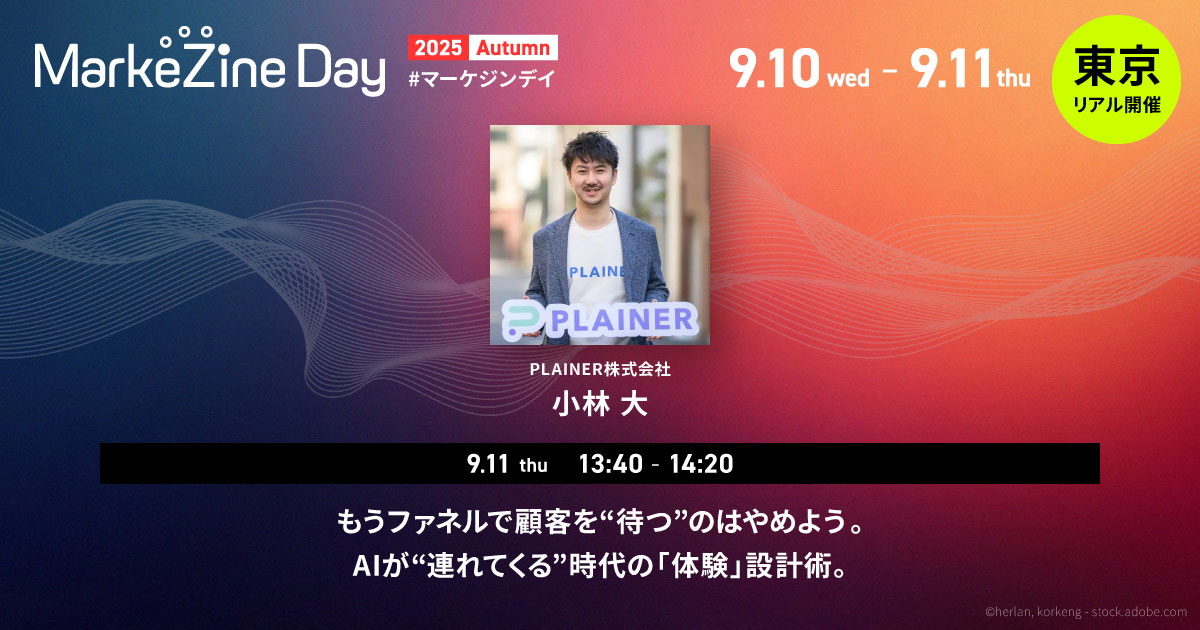
BtoBコンテンツでも「体験」の重要性が高まる
MarkeZine:製品の価値を伝えるために、従来のコンテンツマーケティングをどうアップデートすればよいと思われますか?
小林:言語による情報補足ではなく、実際の「体験」で製品価値を伝えることが必須になると考えます。具体的には、言語では伝わりづらい「使用感」「文脈」「ワークフローとの適合性」といったところまで伝えられる「体験型デモ」の重要性が高まるのではないでしょうか。
リアルな体験価値を設計し、専門性と信頼性を備えた多層的なコンテンツでユーザーの納得を引き出す――生成AIが“コンテンツの量”を担う傍らで、人間が担うべきは“リアルな体験価値の創出“だと考えます。
MarkeZine:コンテンツマーケティングの「情報を伝える」というゴール自体が、変わっていくイメージでしょうか。
小林:そうですね。 BtoBコンテンツは、“伝える”から“共に感じる”へ、目的意識をシフトしていくべきだと思います。情報を一方的に提供するのではなく、ユーザーやAIが操作しながら、製品の価値を「自分ごと」として体感できる「リアルな体験価値」の設計が求められます。
製品価値を「体験」してもらう方法は?
MarkeZine:BtoBマーケティングで製品価値を「体験」してもらうには、どのような方法があるでしょうか?
小林:BtoBマーケティングにおいて製品価値を体験してもらう方法は、無料トライアル、インタラクティブ動画、体験型ウェビナーなど多岐にわたります。中でも、最もシンプルかつ効果的なツールが「デモ」です。
たとえば、業種別・課題別にパーソナライズされたプロダクトツアーを用意すれば、資料を読むよりずっと速く製品の価値を直感的に理解してもらえるでしょう。ユーザーもAIも自社の課題解決のプロセスを、まるで本物の製品を触るかのようにシミュレーションできます。ポイントは、ユーザーが自社・自分の視点で製品の価値を発見できることです。業種別や職種別のユースケースを含めた体験型ツアーや、操作シミュレーションを通じて、「自社に本当に合うかどうか」を体感できる設計が重要だと考えています。
弊社が提供しているPLAINERは、こうした「体験型デモ」をノーコードで誰でも構築できる製品です。開発リソースを使わずに、マーケティング・営業・CS部門がそれぞれの顧客接点に合わせた体験コンテンツを作ることができます。デモ体験を通じて得られた行動データは、購入意欲の極めて高いリードを特定し、匿名営業活動を高度化させます。
予告:MarkeZine DayにPLAINER小林大氏が登壇
9月10日・11日に開催するマーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」に、PLAINER 代表取締役の小林大氏が登壇。『もうファネルで顧客を“待つ”のはやめよう。AIが“連れてくる”時代の「体験」設計術。』と題し、より具体的に体験軸のBtoBマーケティング実践に向けたポイントを解説します。
セッションの詳細をチェック・事前登録の上、ぜひご来場ください。
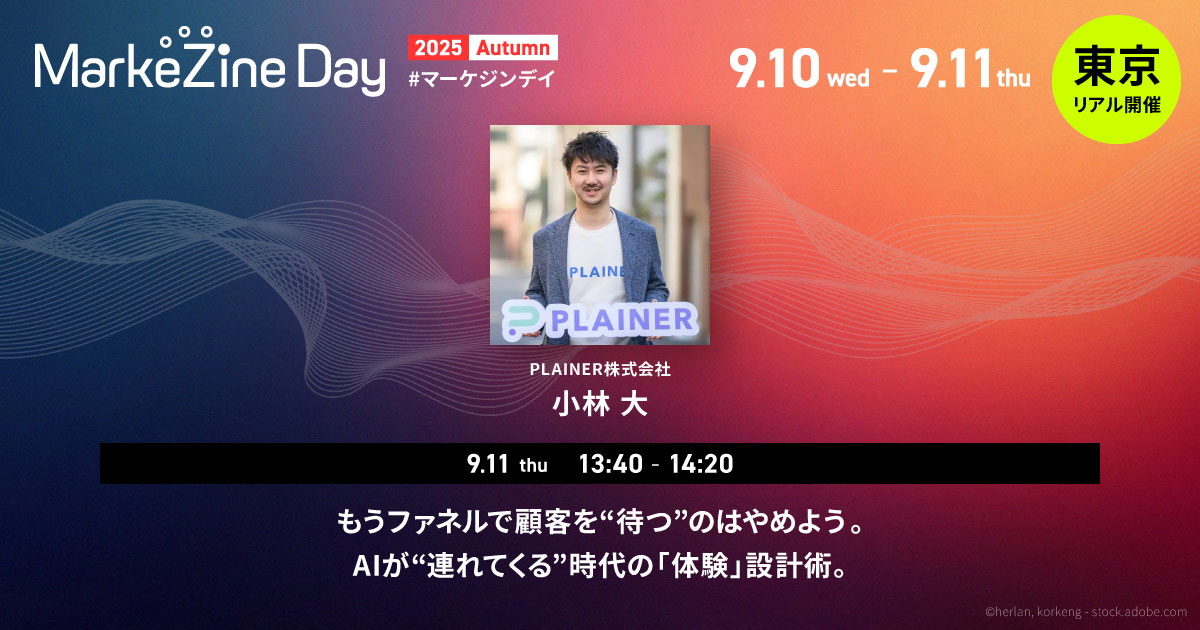
体験を軸にしたコミュニケーションで、組織全体の顧客理解が深化
MarkeZine:BtoBマーケティングに「体験コンテンツ」が入ってくることで、営業やカスタマーサクセス、プロダクトマーケティングなどの周辺領域にどのようなよい影響がありますか?
小林: 体験型コンテンツは、マーケティング部門だけでなく、営業・カスタマーサクセス・プロダクト部門にも大きな変化をもたらします。営業においては、お客様が事前に製品デモを体験した状態で商談の場を来てくれることで、説明に時間を取られず、課題の深掘りや導入提案に集中できます。CSでも、オンボーディング時の教育コストを大幅に削減でき、顧客の早期定着・活用促進につながります。
また、プロダクトマーケティング視点でも、ユーザーがどの体験フェーズで離脱したのか、どの操作に疑問を感じたかといった行動データを取得できるため、UI/UXの改善や訴求ポイントの最適化に活用できます。PLAINERでは、1つのデモを複数のユースケースに応じて複製・カスタマイズできるため、業務効率と体験精度を両立できるのも大きな強みです。こうして、全社で「体験を軸にしたコミュニケーション設計」が進み、組織全体の顧客理解が深まっていくことが最大の効果だと思います。
BtoBマーケティングは、情報を蓄積する「百科事典型」からユーザーの行動や感情に寄り添った体験をリアルタイムで提供する「インフラ型」へ進化していくと考えています。それにより、誰もがテクノロジーに対する抵抗感なく、信頼と納得のもとで購買判断できる世界が実現します。PLAINERはそのための基盤づくりに挑み続けます。
予告:MarkeZine DayにPLAINER小林大氏が登壇
9月10日・11日に開催するマーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」に、PLAINER 代表取締役の小林大氏が登壇。『もうファネルで顧客を“待つ”のはやめよう。AIが“連れてくる”時代の「体験」設計術。』と題し、より具体的に体験軸のBtoBマーケティング実践に向けたポイントを解説します。
セッションの詳細をチェック・事前登録の上、ぜひご来場ください。