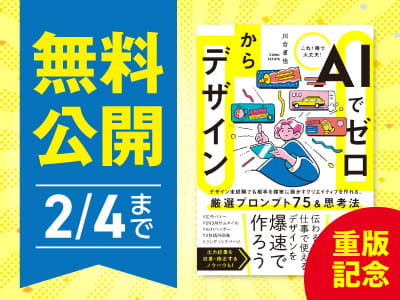花王は2025年8月25日、ヘルスケアブランド「めぐりズム」のグローバルリブランディングを発表した。同社パーソナルヘルス事業部 ブランドマネジャーの仲田実沙希氏が、その詳細を明らかにした。

海外売上比率49%に到達、グローバル戦略への転換点
「めぐりズム」は2005年にブランドが誕生してから、日本国内で地位を築いてきた。主力商品である「蒸気でホットアイマスク」の市場内 金額シェアは約99%(※2024インテージSRI+目用ケア用語市場)、ブランド認知度は84%に達している。
また、同ブランドはグローバル市場での需要が増加し、2024年には、国内に向けた出荷ベースでも日本人51%、外国人49%と、インバウンド客に向けた販売比率が急速に高まっているという。
しかし、販売を展開している中国大陸、台湾、韓国などの10エリアでの認知率(助成知名)や使用率(1年間)は、まだ低水準にとどまっている。この状況を受け、花王では2025年を起点とした本格的なグローバル戦略に舵を切った。
血液循環ケアを軸にした機能強化とブランド統一
今回のリブランディングでは、多くの人が医者にかかるほどでもない日常の不調に対し、同ブランドが発売当初から打ち出していた「血めぐりによる健康提案」の価値を再強化する方針だ。
血めぐりとは、体の中心から末梢まで血液を巡らせ、酸素や栄養分の供給とともに体の不必要な物質を回収する仕組みだ。
主力商品の「蒸気でホットアイマスク」も、製品改良を行い、名称を「めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク」に変更する。新ロゴでは、インバウンド需要や海外展開を踏まえた統一を図った。新スローガンは「ぐるぐる好循環」。
ブランドロゴに矢印を採用することで、日本語を母国語としない人々にも血液循環の好循環を直感的に理解してもらえる工夫を施した。8月末の日本市場を皮切りに、2026年春までに全エリアでのリブランディングを完了させる予定だ。

マスク外側の不織布を従来比約2.6倍の厚みとすることで、保温性を約1.5倍に向上、蒸気量は約113%に増加した
2030年出荷目標1.5倍、海外比率35%へ拡大目指す
今回のグローバル戦略により、花王では2030年に向けた大幅な事業拡大を計画している。2030年の出荷目標は2024年比約1.5倍とし、海外比率を現在の27%から35%へ引き上げる方針だ。コアターゲットとなるのは、心身の内側から循環(血めぐり)させる健康作りの意識や文化が根付く生活者、すなわち日本・東アジア・華僑の人々だという。
現在の主要ユーザーである20代から40代の女性層に加え、「ちょっとした不調を感じたときに気軽に使っていただけるような提案をしていきたい」と使用シーンの拡大を図る。
今回のリブランディングでは、日本に加え、花王上海、花王台湾、韓国のカネボウコスメティックスが参加するクロスボーダーなプロジェクト体制を構築。各国での生活者調査や新製品のコンセプト、ロゴ、パッケージデザイン策定を共同で進めた。
エビデンスマーケティングで差別化、各国の特性に合わせた展開
マーケティング戦略では、花王独自の科学エビデンスを活用したアプローチを各エリアで展開する。日本市場では、地上波テレビでCMを放映する他、デジタル広告やSNSでの強化も図る。花王主催の勉強会を実施し、ヘルスケア専門のインフルエンサーに価値を伝達していく方針で、デジタル広告費用の約3割をこの取り組みに充てる予定だ。
中国大陸市場では品質実証が得意なインフルエンサーとコラボレーションし、血液循環価値を実証とともに紹介。台湾市場では検証系のキーオピニオンリーダー(KOL)、韓国市場では科学的アプローチの商品レビューが得意なKOLとコラボを計画。蒸気温熱循環のメカニズムやエビデンスを伝達していく施策を実施する。
「中国大陸市場は競合が非常に多いため、その中での花王らしさ、めぐりズムらしさを出すには、やはりエビデンスがしっかりあるところが重要です」と仲田氏は競合との差別化ポイントを説明した。海外市場では、中国の天猫(Tmall)を中心とした展開を基軸に、各エリアの特性に合わせたプラットフォーム戦略を展開していく。
【関連記事】
・【耳から学ぶ】統合新会社「電通プロモーション」設立/花王新ブランドの取り組み【ニュースランキング】
・花王の新ブランド「MEMEME」、ドン・キホーテと連携しリテールメディア活用のプロモーション実施
・総合大賞は花王「THE ANSWER」@cosmeベストコスメアワード2025上半期新作ベストコスメ
・生活者のインサイトから、いかにサービスを作り出す?花王「ロリエ」に聞く取り組みとコミュニケーション
・花王「ロリエ」はリブランディングで何を変え、なぜBtoB事業を始めた? 背景の課題とインサイトを解説