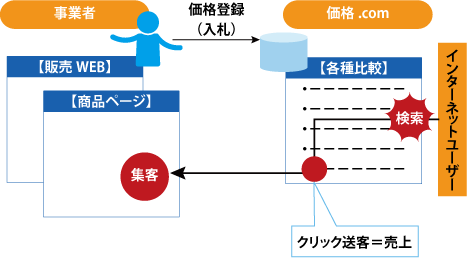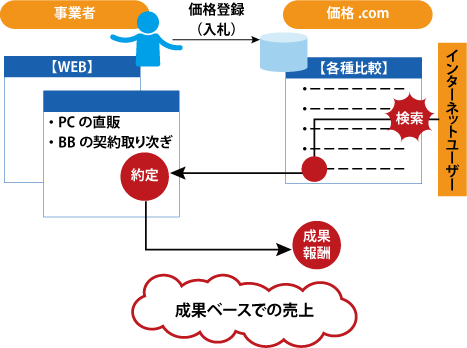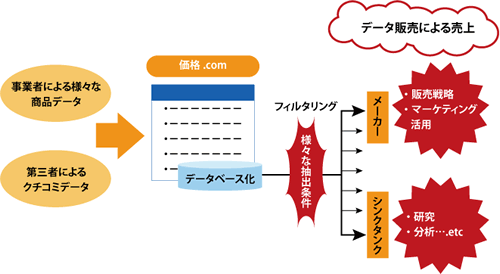価格.comの利益の源泉は何なのか?
さて、「情報を仲介し各事業者とユーザーの需給マッチングを図る」ことを主体にしている価格.comだが、そこから得る収益…つまりは、「儲け」の源泉はどこにあるのだろうか?
おおまかに分類すると、価格.comの「儲け」の柱は4つのモデルから成っている。
収益モデルその1
1つは、価格.comと契約を結んだ各事業者(さまざまなメーカーのプロダクトを取り扱う事業者)が提供する商品データがユーザーによって検索され、そのユーザーが目的の商品を見つけ出して詳細をみるためにクリックした際に発生するPPC(Pay Per Click)である。ここでいう“詳細”は、各事業者のもつ販売ページへのリンクのクリックであり、そのリンク先への送客ごとに、利益を得ているというわけだ。
PPCという括りでみれば、Webにおけるアドネットワークを牛耳っているGoogleが提供するGoogle AdSenseが卑近な例だが、その括りの中でも価格.comが優秀な点は「完全なLPO」が実施されている所にある。価格.comで欲しい商品を探しだし、かつ購入したい事業者(一般的には価格が最も安い店舗)を見つけたら、必ずその事業者(販売店)の該当商品ページにジャンプするのである。ユーザーの視点からすれば、その利便性・安心感たるやいかばかりかである。
ちなみに、このモデルにおける事業者の対象は家電製品などを販売する店舗が多く、事業者は商品登録せずにカカクコム側が登録した商品マスターに対して価格登録(入札)する形式になっているのが特徴である(商品マスター自体は、価格.com側が人海戦術で登録しているとのことであり驚きの事実である!)。
収益モデルその2
さて、2つ目の収益モデルはというと…ブロードバンド事業者やPC等を直販する事業者の商品を各社横断的にデータベース化し、その情報をユーザーが検索・選択して約定 ---例えば、ADSLの接続契約/直販PCの購入等--- に至った際の成果に基づく報酬がそれである。いわゆる、PPP(Pay Per Performance)モデルである。
このPPP収益モデルは、先述したようにBB事業者や直販メーカー(代表的な例で言えば『DELL』等)がその徴収対象となっているが、実は価格.comでは、1つ目にあげたPPCモデルに属しているような家電販売店などにも適用しており、クリック送客の結果による販売実績に応じた手数料を徴収していたりもする。
収益モデルその3
3つ目の収益モデルは「純広」…いわゆる、「純粋な広告の出稿」による儲けである。価格.comというサービスがメディア ---とはいっても、家電系等の特定のカテゴリーではあるが--- としての価値を有していることを意味するが、カカクコム経営企画部広報室長である甲斐氏によれば「サイトのコンテンツやサービス主導の会社のため、営業会社ではないが…少数精鋭の営業要員で直接契約をとっている」とのことであり、レップを殆ど使わない点が、本モデルの高収益構造を作り上げているようである。
数値からみてもわかるように、「平成21年3月期 第1四半期決算短信」のデータでは5億5,200万円もの金額を売り上げておりその企業努力は侮ることはできない。
収益モデルその4
4つ目の収益モデルは「情報提供」である。具体的には、保険や中古車査定・金融等の比較などのサービス提供の結果、資料請求件数などに応じて収益化する仕組みになっている。一方、それに加えて…本質的な「情報提供」サービスも存在している。どのような「情報」を「誰」に提供するのか?といったところであるが、その内実を記載すると
情報=ユーザー参加によるプロダクト等に関するクチコミ情報
誰=メーカー及びシンクタンク
となっている。本事業は、まだはじまったばかりの事業だが、ユーザーによる膨大な量のクチコミが蓄積された価格.comのデータベースは、メーカー側からすれば、商品販売戦略を練る際の有用なマーケティングデータであり、シンクタンクからすれば、分析・研究の対象となり収益の源泉として成立しているのである。
これら4つの収益モデルをもってして、価格.comは儲けを得ているわけであるが、このサービスが始まった当初の収益源が「純広」のみだったことを考えると、一日千秋の思いである。