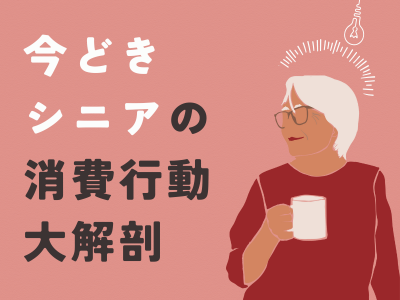“飽きた”もリアル。感情が循環する関係性へ
推し活における“熱の変化”は、ネガティブな現象ではありません。むしろそれは、感情の成熟と再編集のプロセスと解釈できます。
68歳女性は、こう話します。「学生の頃に宝塚に出会い、それが他の舞台を観るきっかけにもなりました。就職など生活の変化で、少し遠ざかりましたが、暮らしの張り合いになればと友人に誘われて、再び観るように。見始めると、ファンの付き合いが広がり、遠征で一緒に旅行するなど行動範囲も広がり、日々の張り合いにもなっています」
ライフステージの変化で一時的に熱が冷めても、完全には離れず、“感情の循環”が生まれています。若い世代が「熱狂→離脱→新しい推し」へと移るのに対し、シニア世代は「同じ推しと関係性を更新しながら、続ける」傾向が強そうです。
この構造は、企業と顧客の長期的な信頼関係を重視する“関係性マーケティング”にも通じます。推し活は、こうした関係性の積み重ねを日常の中で実践している好例といえるでしょう。
一時的な離脱も「休眠期間」と捉え、シニアがいつでも戻れるきっかけや接点を複数の媒体などで触れられるようにしておくと、信頼感が増すのではないでしょうか。世代的には「TVなどのマスメディア」×「OB顧客向けの案内・SNSでイベント開催をお知らせなどのパーソナルメディア」を掛け合わせると効果的です。
推しには惜しまない。支出にみえる心の投資
推しにお金をかけている人は約7割。推し活にかける年間平均支出は11万4,039円と、前年より1万円以上増えました。チケット代やグッズ価格の高騰もありますが、注目すべきはその「動機」です。
- 「なにわ男子の大橋和也。若くて、いつも元気で明るく人柄も良く、見ているだけで元気になります!」(56歳)
- 「草彅剛さん。心身の健康を保つことができる。イベントに行くために綺麗でいようと努力するし、健康を維持しようともすることから自分にとって良いことしかない」(60歳)
- 「BTSは生活に潤いを与えてくれる。元気になれる」(64歳)
推しへの支出は単なる消費ではなく、“心身の栄養”です。応援することが、健康・美容の維持や生活の質の向上につながるという効用をもたらしています。シニア世代の推し活は「自分の心を潤わせ、自らを幸せにするための経済行動」になっていました。