Helpingにおける効果測定手法とKPI設定
HelpingにおけるKPI設定についても、連載第4回で解説したとおり、「ストラテジックKPI」と「タクティカルKPI」に分けて考えることが重要となる。それぞれについて、考えられるKPIを示してみたい。
タクティカルKPI
まずは、タクティカルKPIであるが、基本的には短期的視点に立ち、行動目標として企業がコントロール可能な指標、およびインプレッション等のモニタリング可能な指標を設定することがポイントとなる。タクティカルKPIについては、ソーシャルメディアのタイプや、さらにブレークダウンした指標が考えられるため、下記は一例として捉えて頂きたい。
- コメント投稿数(質問に対するレスポンスの数)
- ベストアンサー数(Q&Aサイトの場合)
- エンゲージメントを行った顧客のフォロワー数(Twitterの場合)
ストラテジックKPI
ストラテジックKPIは中長期的にはファイナンス側のKPI、つまり売上や利益との相関についてモニタリング可能な指標が望ましい。
ストラテジックKPIの例
- コールセンターへの入電件数(Helpingによる削減効果を見ていく)
NPSと口コミの関係 ― ロイヤルティからアドボカシーへ
ここで、少しNPSと口コミの関係について見てみたい(図表4)。NPSは、企業と顧客とのリレーションの強さを測る指標である。また、ロイヤルカスタマーがもたらすベネフィットは、大別すると「購買行動の増加」「建設的なフィードバックの提供」「口コミによる推奨行動」に分けられる。
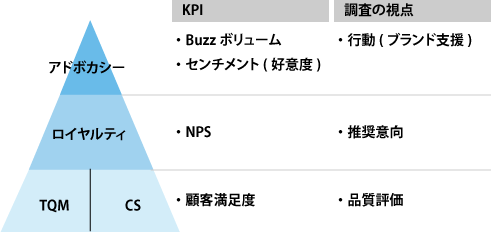
この中で、ソーシャルメディア上の口コミとして「建設的なフィードバックの提供」「口コミによる推奨行動」を顧客が行ってくれることが「アドボカシー(顧客によるブランド支援)」であると言える。
ソーシャルメディア上で顧客がブランドに対して貢献をしてくれるアドボカシーの形態としては、例えば、次のような行動が挙げられる。
- レビューサイト上での製品に対するレビュー
- Q&Aサイト上での製品に関する質問に対する回答
- ブログ、SNS上での製品に関する言及
- オンラインビデオによる製品のデモンストレーション
- 自社メディア内コミュニティサイトへの参加
Listeningにより、ボリュームとセンチメント(好意度)の両方を合わせて見ることで、ロイヤルカスタマーのソーシャルメディアにおけるアドボカシー活動のアクティブさを把握することができる。さらに、NPSとの関係を見ることで、例えば、「NPSが高いわりには、ソーシャルメディア上でのアドバカシーがあまり活発に行われていない」といった課題が分かる。ロイヤルカスタマーが、次のレベル、つまりアドボカシーのフェーズへ進んでいるかどうかが把握できる。
NPS調査で把握した推奨者、つまりロイヤルカスタマーが、ソーシャルメディア上でのアドボカシー活動を行いやすいような環境を、いかに整えられるかが、ソーシャルメディアマーケティングにおいて非常に重要である。
筆者は、この原稿を書いている直前(2010年4月6日)に、Net Promoter Score(NPS)アソシエート認定試験に合格している。ちなみに、日本人としては初の合格者となる。
次回は、ロイヤルカスタマーのアドボカシー活動支援としてのソーシャルメディアマーケティングである、Energizing、Embracingについて、具体的な事例を交えながら解説していきたい。




































