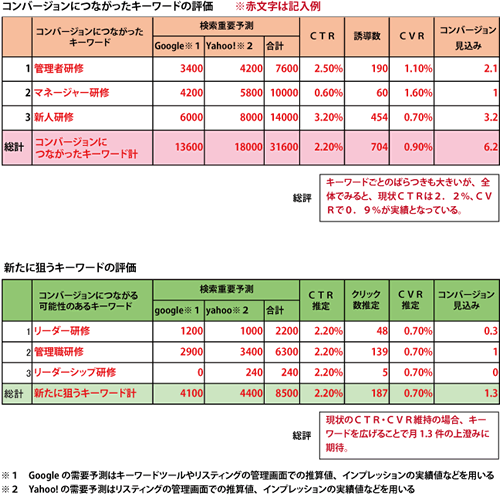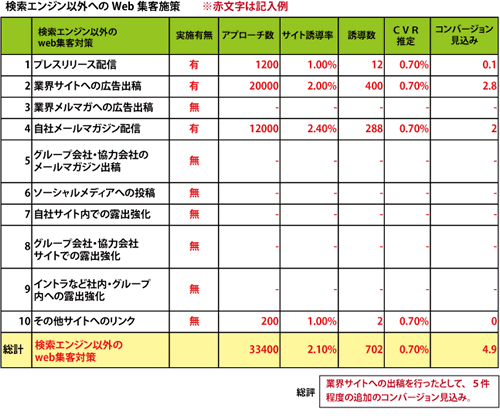Webサイトリニューアルは最適な手法か?
1つ目の疑問は、問合せ10倍という『目標』に対して、サイトリニューアルという『手法』が適切かどうかだ。このケースのRFPでは、目標も手法も決められてしまっている。
サイトリニューアルでは基本的にはサイト内にしかインパクトを与えることができない。サイト内の構造改善による歩留まりをアップさせることによって、サイトの集客に着手せずとも、問合せに至る率などを上げることはできる。
そのため、十分に集客ができているにも関わらず、直帰率が低かったり、離脱率が高かったり、CVRが低かったりと『成果に結びついていない』ということが主となる課題ならばリニューアルはコンバージョンを上げる方法として適切かもしれない。
だが、十分に集客ができていないサイトでは、サイトリニューアルだけを行ってもコンバージョン数を大幅に伸ばすことは難しい。
サイトリニューアルという予算名目を最優先してRFPを作成するならば、サイトリニューアルという手法で「どこまで問合せを上げることができるか」を各社に提示してもらうとよい。コンバージョン数が上がる論拠の納得度が高く、より上がる可能性が高い提案を選択すればよい。手法を『リニューアル』とそろえることで、提案間の比較もしやすくなる。
逆に、目標への到達を最優先にするならば、サイトリニューアルにこだわらずに、目標10倍に向け、集客へのプランニングなども含め、各社が多様な提案ができるRFPにすべきだ。目標を『10倍』にあわせることで、アプローチの方法やコストを比較しやすくなる。
目的と手法がごちゃまぜになってしまうケースはよくある。とくにWebマーケティングに詳しくなかったり、初めて本格的に取り組む場合はなおさらだ。最優先の目標をはっきりとさせることで的確なプロジェクトのゴールを定めなければならない。
集客は現実的に可能か?
2つ目の疑問は、集客施策を含めたRFPでよしとしたとしても、10倍がそもそも可能な値なのか? ということだ。Webマーケティングの可能性が拡大しているとはいえ、打ち出の小槌ではない。どんなに検索で1位になろうが、サイトのコンバージョン率が高かろうが限界はある。
そのため、C社が展示会やメルマガに限界があると推算していたように、Webサイトにも同様にどのくらい伸びるポテンシャルがあるのかを、しっかりと推算すべきであろう。
実際によく行う方法のひとつが検索需要の調査である。
例えば10,000回/月の検索需要があるとして、検索エンジン広告を通じてCTR5%を実現できれば500回/月の訪問を促すことできる。現状のサイトから1%程度のコンバージョン率があれば、5件/月のコンバージョン獲得を実現できるポテンシャルがそのキーワードにあるということだ。
もし月5件コンバージョンを増やすことが目的であれば、検索エンジンに向けた対策だけで十分かもしれない。もし月20件のさらなるコンバージョンを目指すのであれば、月15件分の他の集客方法を検討しなければならない。
これらを明確にするために【図1】のように、キーワードごとのポテンシャルを計るとよいだろう。もし既にコンバージョンの実績があるキーワードがあるならば、その値を参考にすることで現実に即した数値予測ができる。
もし、実績がないのならば、業種やサイトの状態により差はあるもののBtoBにおけるコンバージョン率は、経験則では検索需要の0.1%~0.05%というところをはじめの目標にするとよいだろう。
もちろん、エリアが絞られるキーワードや他業種が混ざるキーワードは、目減りさせて実際の需要を見込まなければならない。さらに、敵が多いキーワードではポテンシャルは高いかもしれないが、実際に検索エンジンで順位を上げるための難易度は上がる。単純に数字をみるだけでなく、堅実なポテンシャル予測が重要だ。
BtoBの集客は検索エンジン対策だけではない
さらに、今一度、BtoBでコンバージョンを生む可能性がありそうな集客の可能性を洗い出すべきだろう。
可能性の候補となるところが、【図2】の検討リストだ。自社だけでなく、プレス先やグループ会社、協力会社や社内への告知までさまざまな可能性がある。一度現状を把握する意味も含めて自社を想定しながら埋めてみるとよいだろう。
まずは推し量るところから
売り上げ目標から、逆算をしてWebサイトからの問合せ目標を設定するのは間違いだ。実現可能性の低い目標では、せっかく設定した目標も机上の空論だ。なるべく的確に各Webマーケティングのポテンシャルを測定し、実現可能性とコストを把握する必要があるのだ。
1度このプロセスを経験していれば、実測値が推算値とどのくらい差があるのかが、明確に分かってくる。初回の推算値の精度は低いかもしれないが、分析を積み上げていくことで社内の予測の精度が上がってくる。
Webサイトは数値が出しやすい分、科学的な検証を社内に定着させるチャンスでもあるのだ。