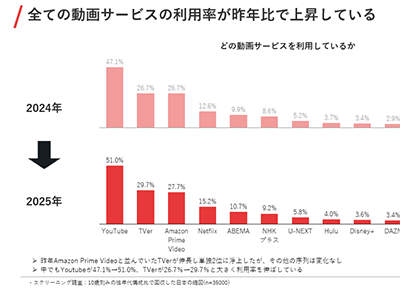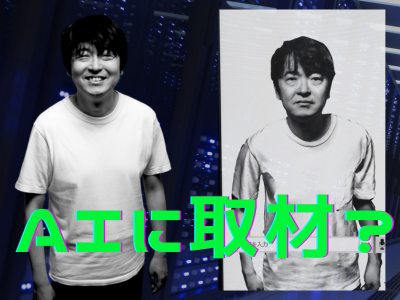テクノロジーのポジティブな可能性を信じて~あとがきより転載~
本書のテーマはオープニングにも書かれているが、小寺さんと僕がいろいろな人のところに話を聞きに行って「コンテンツの未来」がどのようなものであるか考える、ということであった。その意味で本書は単なる「インタビュー集」ではない。取材の場で2人の思っていることを相手にぶつけたことで、それぞれのコンテンツの未来がおぼろげながら見えてきたのではないかと感じている。全体を通して読むと、何か明確な結論を出しているわけでもないのに、コンテンツの本質がちょっと理解できたような気になる……何とも不思議な本に仕上がったと思う。
といっても、本書ですべてのコンテンツの未来を示せたなんて大それたことは僕も思っていない。一口にコンテンツといっても、その種類はさまざまだ。マンガやアニメ、ゲーム、映画といった産業規模の大きいコンテンツから、日本独自のケータイカルチャーや、いわゆるポルノ的なコンテンツについても本書では触れられていない。
これはなぜこの9人にお話を伺ったのかという話にも関わってくるが、小寺さんも僕も自分たちが今まで関わってきたコンテンツの守備範囲で話を聞くことが、はじめの一歩として重要なことだと考えていた部分がある。身も蓋もないことを言ってしまえば、コンテンツ論に「これだ」という正解はない。
だからこそ、いろいろな人と話していく際にできるだけ多くのインタラクションを起こす必要があった。そうすることで僕らも、そしてこの本の読者も自分なりのコンテンツ論を考えることができるのではないか。そういう狙いがあったということだ。本としての統一性を考えれば、今回あえて自分たちが不案内なジャンルまで網羅しようとしなかったのは、正解だったと思っている。
こうした対談本は、テープ起こしした内容を編集者やほかのライターが構成して、対談した者は著者校正という形で発言内容の確認だけ行うというのが基本である。だが、小寺さんも僕も構成者が構成した内容に対談では言わなかったことも含めてガリガリ編集を加えていくタイプなので、最初から小寺さんの担当は土屋氏、草場氏、西谷氏、遠藤氏。
僕の担当は長谷川氏、椎名氏、江渡氏、中村氏、松岡氏と決めて、鼎談の構成と司会進行を行った。具体的なプロセスとしては、テープ起こししたものを本書の担当編集が粗構成し、そこから小寺さんと僕がお互いの発言には触れない形で鼎談という形に本構成し、最終的に「GoogleDocs」にアップロードしたテキストをお互いに編集し合って作っていく(GoogleDocsは、編集した部分を差分として残してくれるという特徴がある。どちらがどのような編集を行ったのかがすぐにわかるし、元の状態に戻すことも簡単にできるので、こうしたコラボレーションワークに向いているのだ)というイメージだ。
当初本書の編集者である毛利さんから出版の話を持ちかけられたときには、僕もここまで大変な作業になるとは思わなかったが、結果的にそうした複雑なプロセスを経た分、内容的にも濃いものに仕上がったという自信はある。