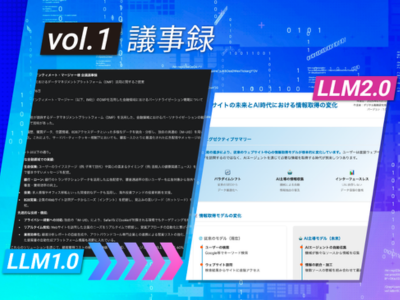会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
新規会員登録無料のご案内
- ・全ての過去記事が閲覧できます
※プレミアム記事(有料)は除く - ・会員限定メルマガを受信できます
- ・翔泳社の本が買える!500円分のポイントをプレゼント
この記事は参考になりましたか?
- 関連リンク
- 「マーケティングリサーチなんかいらない!?」 変わるものと変わらないものを考える連載記事一覧
-
- 変わることのない、基本として理解しておきたい、マーケティングリサーチの3つの考え方【最終回...
- 変わるべきマーケティングリサーチの視点 「代表性・単一調査への依存・同質性」について
- 拡張するマーケティングリサーチ、「調査手法」からリサーチの現在を俯瞰する
- この記事の著者
-

鈴木 敦詞(りんく考房)(スズキ アツシ(リンクコウボウ))
りんく考房代表。マーケティングエージェンシー、リサーチ会社を経て独立し、フリーランスにて活動中。独立を機に大学院で学び直し(多摩大学大学院経営情報学研究科修士課程修了)、現在はマーケティングおよびリサーチに関する支援、研修、および執筆活動を行う。blog/Facebook「マーケティング・リサーチの寺子屋」では、リサーチ関連の情報を提供中。
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア