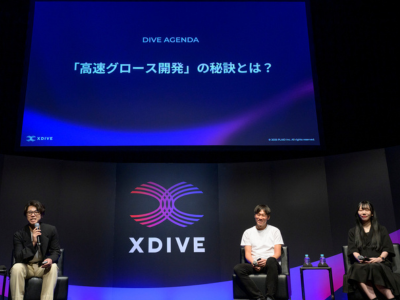スタートアップにこそ“CDO“が必要
一方、デザインはどうだろうか? 日本経済新聞電子版アプリの監修や、ハンドメイドマーケットアプリ「minne」のUIデザインアドバイザーを務める深津氏は、スタートアップ企業が抱える一番の課題は「デザイン=どんな色を使う・どんな模様にする・どんなレイアウトにするとかっこいい・かわいいかで終わってしまうこと」だと指摘する。
「デザインの守備範囲は、ユーザーがサービスを使う理由を視覚化し、サービスを使う中でユーザーが何をどう感じるかを設計するまで。まさにプロダクトを開発する段階にあるスタートアップにこそ、経営戦略やマーケティング戦略をデザイン設計に落とし込むことができる人材が必要」(深津氏)
ユーザーは誰か、どのようなメッセージを送るべきか、使い続けてもらうには何をどう伝えれば良いか。全体を俯瞰して、どのような構造を作るか考えることがデザインの仕事だ。しかし、初期段階でそれができているスタートアップは、ほとんどいないという。
マナボの場合も、フルタイムのデザイナーを採用したのは最近のことだ。その背景には、まず動くプロダクトを作るというプロダクト開発重視の方針もあったが、同時に戦略をデザイン設計に落とし込めるような上位レイヤーのデザイン設計を行えるデザイナーの採用の難しさがあったという。
「企業には“ユーザーをハッピーにすること”と“ビジネスの持続可能性を高めること”の両輪が必要。そのために、ユーザーに向き合い、ユーザーの満足度を高められるようなデザイン設計ができるCDO(Chief Design Officer)ができるだけ早い段階でいると良い」と深津氏。CDOの登用が難しい場合、経営陣とデザイナーがサービスのビジョンとターゲットユーザー像を共有し、各部署と定期的にそれらのビジョンをすり合わせ、組織横断的なデザイン設計の提案ができる仕組みが必要だと見解を示す。
マナボが解決すべき課題と、進めているチャレンジとは
ストラテジーに深く関わるマーケターとデザイナーの不在。マナボを含めた多くのスタートアップが抱える課題に対して、マナボは両氏とともに改善のチャレンジをしている。
「マーケティングについては、彌野さんと毎週一回、事業戦略と一貫性を持ったマーケティング戦略の再定義をしています。本来この場に、戦略レベルの設計を行える社内のデザイナーが加わることが望ましいのですが、現在はそのような人材が不在。ですから、深津さんに入ってもらいターゲットやユーザーインサイトなど、マーケティング戦略の根幹にあるものをいかにしてデザイン設計に落とすかを代行してもらっています」(廣田氏)
また、深津氏によるデザイン設計を基に、事業戦略やマーケティング戦略とサービス設計にズレを生じさせないために、デザイン制作のためのペルソナやカスタマージャーニーマップなどの内部資料の制作を行っている。ターゲットユーザーには様々な可能性が存在するが、これらの資料を作ることで、コアとなるターゲットユーザーを視覚化し組織で共通認識を持つことができる。これらは、事業戦略、マーケティング戦略、サービスのデザイン設計を、一気通貫させるために有効だ。
続いて、デザイン設計をビジュアルに落とし込むフローが変更された。具体的にはデザインプランを複数用意した上で、デザイン要素を印刷した紙を用いてボタン位置や要素の順をその場で変えるなど、デザインソフトを立ち上げる前に簡易的なABテストや評価を行うといったプロセスを行うようにした。こなすべきタスクも多く、リソースも限られるスタートアップは、「とりあえずガワをつくる」だけで精一杯になりがちだ。だからこそ、負荷の少ない簡易的な方法で、デザイン要素の当たり所をディスカッションし、掴んでから実際の制作に移るようにしたわけだ。
マーケティングの面では、企業の中長期目標を確認し、そこから導き出される各事業の位置づけや役割、それぞれの事業に求められる成長スピードの確認と、各事業で獲得すべきユーザー数やLTV目標のブレイクダウンを行った。次に、それらに基づいて狙うべきターゲットを明確にし、インタビューを通してターゲットユーザーへの理解を深めた。加えて、その結果を受けてプロダクトが提供すべき価値と、ターゲットユーザーの頭の中に作り上げるべきサービスのポジショニングの再構築を行った。
これらの取り組みを通して、ユーザー像がクリアになり、自社のプロダクトが提供すべき本質的なバリューを全員で共有できるようになったという。例えば、「mana.bo」は受験生向けのサービスだが、一口に受験生といっても頭に描く受験生像は人によって異なる。どのような受験生を狙うかによって、サービスに興味を持ち、使い始め、お金を払ってもらうために実現し伝えるべきことは変わる。そのため、ターゲットユーザー像に僅かでも齟齬があると、プロダクトをブラッシュアップするフェーズで様々な支障をきたしてしまうのだ。
「「誰」に「どんな」価値を提供すべきか、経営陣の中でも認識にズレが生じていました。事業戦略と一貫性のあるマーケティング戦略、およびターゲットユーザー像を経営陣全員で共有することでブレなく議論が進む。さらに、全社で共通認識を持つことでユーザーに対しても、本質的なバリューがストレートに響くプロダクトを作れる可能性が高まっているように感じます」三橋氏は手ごたえを語る。
「スタートアップは一人ひとりの仕事量が多い。多忙の中で、経営層が一同に集まってマーケティング戦略やターゲットユーザー像について十分にディスカッションする時間を作ることは正直、大変です。けれど、今回のプログラムで無理やりにでもその時間を作ったことは大きい」と山下氏。

現在、同社では上位レイヤーのマーケティングとデザインの両面で地盤固めを行い、実際のサービスやLPに落とし込む作業を進めている。この取り組みの結果は12月12日に開催される「Heart Catch 2015」で発表されるとのこと。スタートアップに新たなエッセンスが加わることで、どのような変化が起きるのだろうか。
スタートアップが抱える人材獲得の課題
スタートアップが抱える、上位レイヤーのマーケティングやデザインができる人材不足には、「スタートアップに参加してくれる優秀な人材がいない」という根本的な課題があるようだ。
「上位レイヤーを設計できるマーケターとデザイナーが重要であることは痛感していますし、CMO、CDOとして我々と一緒に戦略を考えてくれるメンバーを探したいと考えています。ですが、スタートアップが提示できる条件には限りがあります。そのような環境で、どうしたら優秀な方を口説くことができるか」と三橋氏も心境を明かしている。
対して彌野氏は、「スタートアップだけではどうにもならない部分もあるでしょう。外部からマーケティング戦略や組織構築、マーケティングメンバーの育成を支援する取り組みが必要かもしれません。その準備をしていければ」とスタートアップが相談できる仕組みの必要性を語った。マーケティングやデザイン面においてスタートアップを取り巻く環境が変化すれば、これまで以上に様々なイノベーションが世の中に出てくる可能性もあるかもしれない。
上で少し触れましたが、マナボの取り組み結果がイベント「HEART CATCH 2015」で発表されます。本記事でもアウトプットを聞き出したかったのですが、詳細はこちらで、とのこと。スタートアップがストラテジーデザインとマーケティングに出会った結果、何が起こるのか。ご興味のある方は足を運ばれても良いかもしれません。