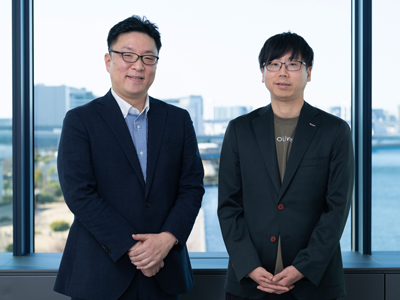分散型アプローチは企業のオウンドメディアにも
2つ目は「コンテンツ流通構造のさらなる変化」。以前は、マスメディアを通じて広告主からの情報がパッケージとして生活者に届いていた。だが、生活者がWebを含めた様々な情報源に接し、SNSなどを使って発信者にもなっている今では、情報が届く矢印は一方向ではなくなっている。
その矢印に乗って流通するコンテンツも、非常に断片化しているのが現状だ。昨年大ヒットとなったドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」、通称“逃げ恥”を例に挙げると、話題の大きさの割にTBSで放映されていたことはあまり知られていないのでは、と荒川氏は指摘する。
「コンテンツだけが一人歩きするようになった結果、生活者にとってどの媒体社が制作したのかということは、あまり気にされなくなっています。それでは良質なコンテンツを生み出しても恩恵を受けられないので、今までよりも一層“自社含め誰が手掛けているんだ”と声高にいう必要が出てきています」(荒川氏)
一方で、この断片化を味方につけた動きが、近年起こっている「分散型アプローチ」だ。これが今、オウンドメディアを運営する広告主にも広がりつつある。荒川氏によると、とある自動車メーカーではオウンドメディアで制作したコンテンツを積極的に流通させ、そこで得られたデジタルの知見やデータを販社の店舗運営に活かそうとしているという。

流通構造を考える上では、たとえばタクシーの車内サイネージや、飛行機の機内Wi-Fi利用画面など、新しい配信先も増えている。こうした新媒体の特徴を捉えることも欠かせない。
ブランド経験をマネジメントする発想が不可欠に
3つ目の「ブランド経験マネジメント」が、最も重要だと荒川氏は強調する。様々なクリエイターや研究者の指摘を加味し、荒川氏は「モノやサービスが過剰になっている中で選ばれるためには、ブランドがますます重要になっている」と語る。ブランドとの接点を重ねて、選択の瞬間にいかに好意的なイメージを浮かべてもらうかがカギになる。
くわえて、荒川氏は「企業がなぜブランディングに取り組むのか」についても解説。顧客接点をデジタル含め構築して顧客育成を行い、顧客にたくさんの伝えるべきストーリーを届けるためだという。各企業は顧客の中に生きるブランドをより良くするために努力し続けているのだ。
「ブランドとは、顧客の中に存在するものです。モノがあふれ、生活者が自由に選べる時代だからこそ、様々なことをイメージしてもらうことの重要度が高まっています」(荒川氏)
ブランドの重要性が増している背景には、多くのメーカーが陥っているコモディティ化も関係している。機能訴求が効きにくくなった今、差別化のために各社が注目しているのが、リアルな体験だ。
「イメージ訴求で選んでもらうのには限界があります。たとえ非効率でも、商品やサービスをリアルな場で体験し、その良さを五感で感じ取ってほしいと考える広告主が目立ってきています。実際に2017年度の予算配分に関しても、デジタルよりイベントなどリアルな施策を重視すると語る広告主もいます。体験を通して本質を伝えようというアプローチは、全体のキーワードに掲げた“回帰”に通じると思います」(荒川氏)
さらに荒川氏は、Web購読をきっかけに紙の新聞購読が見直されていることや、モノよりコト消費の加速を指摘した。
「情報を見る、聞くだけに対し、リアルに体験するほうが記憶に残りやすいという話もあります。デジタルの一方で体験も重視しながら、生活者の中にブランド経験を積み重ねていくという発想が、今年はさらに有効になると考えています」(荒川氏)