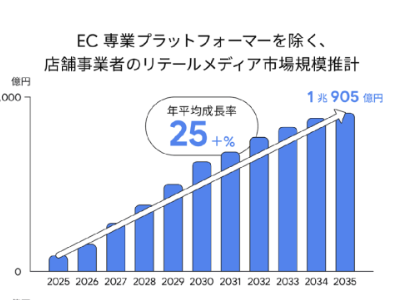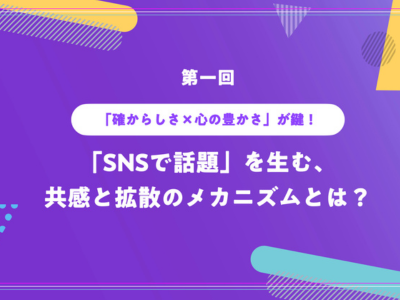D2Cをビジネスの成長の柱に
新型コロナウイルスの流行でデジタルトランスフォーメーション(DX)の遅れが顕著に表れた日本。特に政府や自治体などの申請手続き、はんこ文化、教育、遠隔医療など公共サービスでの遅れが目立つ。
一方、DX化の遅れは企業の経営においても大きなリスクになることが改めて浮き彫りになった。ブルックスブラザーズやセシルマクビーなど、店舗を中心としたビジネスの苦境がメディアなどで取り上げられているのを見た読者もいることだろう。

しかし、実店舗を持つ企業でもDXやD2Cへの投資を加速してきた企業群はこの状況下でも成長し続けた。
実店舗での象徴的な事例は第1回でも触れたがウォルマートだ。スマホで注文し、ドライブスルー方式でピックアップする仕組みに加え、アマゾンプライムのように年間100ドル程度を払えば、毎回無料で生鮮食料品、日用品、家電などを自宅へ配送できる「ウォルマート+」という計画も進んでいるという。
生鮮食料品の対応と即日配達でアマゾンとの差別化を図り、満足度の高い顧客体験を実現しようとしているのだ。
日本においても、ユニクロ、日本マクドナルド、ニトリ、スシローなど、長年DXに投資してきた企業が、コロナ禍で店舗閉店の影響は出たものの、ECやOMOの仕組みを整えたことで、逆に業績を伸ばしている。
「D2Cモデル」が求められる背景とは
新型コロナウイルスの影響で、多くの企業が非対面・非接触のサービスを取り入れてきたことだろう。もし今後も、非接触型の社会が浸透し続いていくと仮定した場合、避けて通れないのが「D2Cモデル」の構築だ。
近年、これらのD2Cビジネスが可能になった背景や要因を今一度整理してみると以下の通りである。
直近10年のテクノロジーの進化:インターネットメディア、ソーシャルメディア、スマートフォン、EC、データ獲得・分析基盤の普及など
SNSやインターネット広告による顧客との直接的なコミュニケーションコストの低下:メジャーブランドからマイクロブランドまでのあらゆるブランドで、マスメディアに頼らないコミュニケーションとマーケティングが可能になった
顧客との接点の指数関数的増加と多様化:オン/オフに関わらず直接的な体験提供と販売ができるようになり、それにより購買・反応データ、プロフィールなどの獲得が可能になった
スマホの普及で「棚」が生活者の手の中に:結果、小売店に頼ることや全国に販路を持つことが不要になった
これらの背景や要因を受け、日本でも最近D2C化の流れが加速してきた。
たとえば、百貨店業界で独自の路線を行くのが丸井グループだ。デジタル技術を活用した「ショールーム特化型店舗」いわゆる「売らない店」を模索している。その理由として「今やスマートフォンがあればどこでも買い物はできる」「店舗で買うよりよっぽどスムーズだ」「販売の場所から『体験の場所』へ変える」としている。渋谷PARCOの1階にも売らない店「BOOSTER STUDIO」がはいる。
メーカーのD2Cとしては、花王がファインファイバーテクノロジーを活用した美容液と化粧水、機器の販売を開始した。機器を買ってもらい、継続して美容液などを買ってもらうモデルである。資生堂でも現在はサービスを停止しているが「オプチューン」という月額定額サービスにも挑戦している。