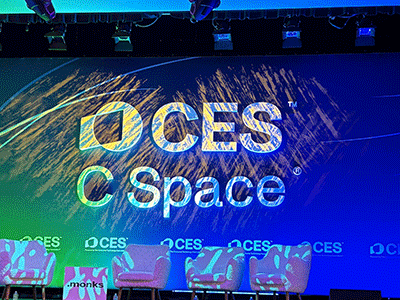会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
新規会員登録無料のご案内
- ・全ての過去記事が閲覧できます
※プレミアム記事(有料)は除く - ・会員限定メルマガを受信できます
- ・翔泳社の本が買える!500円分のポイントをプレゼント
この記事は参考になりましたか?
- 関連リンク
- この記事の著者
-

吉田 朗子(ヨシダ サエコ)
アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 マーケティング部
広告代理店とカナダでのワーキングホリデーを経て、2018年アジャイルメディア・ネットワーク(AMN)入社。AMNでは、マーケティング部に所属しながら”寄り添う企業として”をスローガンにしウェビナー、イベントなどを開催中。個人では保護犬のボランティアなどを行いながらより良い未来を模索している。
アンバサダープログラム事業部:https://agilemedia.jp/ambassador-program
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
-

宮崎 綾子(ミヤザキ アヤコ)
編集者。編集プロダクション勤務を経て2009年に独立、“ひとり編プロ”アマルゴンを運営。PC・スマホ・ウェブ関連の技術&カルチャー書籍編集制作を中心に、PRコンテンツ企画など幅広く関わる。電子書籍の導入期にはImpress QuickBooksシリーズに参画。実績は https://amargon.net
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
-

田口 和裕(タグチ カズヒロ)
タイ在住のフリーライター。ウェブサイト制作会社から2003年に独立。雑誌、書籍、ウェブサイトなどを中心に、ソーシャルメディア、クラウドサービス、スマートフォンなどのコンシューマー向け記事や、企業向けアプリケーションの導入事例といったエンタープライズ系記事など、IT全般を対象に幅広く執筆。著書に『できるfit メルカリ&LINE&Instagram&Facebook&Twitter 基本+活用ワザ』(インプレス・共著)、『ゼロからはじめるテレワーク実践ガイド ツールとアイデアで実現する「どこでも仕事」...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア