なぜ沖縄のダイビング経営者に沖縄出身者がいないのか?
酒井:確かに、ブームと一緒に育った人たちは、その特徴に気づきにくい側面はありますよね。この件に関して、私は沖縄のダイビングショップの経営者に沖縄出身の人がいない、という話がとても好きなんです。
古川:それはおもしろいですね。
酒井:沖縄の人たちは、そこにきれいな海があるのは当たり前すぎて、都会から人が来ても何が楽しいのかよくわからないらしいんです。その良さを発掘・発信するためには、沖縄の海に違和感を抱いて「ここがすごい!」とわかる、着眼できる人がいなければ始まらない……こうした話はインバウンドも含めて、実は様々な場面であります。
上原先生の話もそうだと思うんです。過去の韓流ブームと比較したときにどうなのか。韓流との比較ではなくとも、たとえばEXILEのブームと比較するとどうなのか。このように、視点をエクスパンドしていくことでおもしろいインサイトが生まれる、というのはおっしゃる通りですね。
上原:この『デジノグラフィ』の本では、一般の人でも使えるビッグデータのサイトを紹介されていますよね。学生がこうしたサイトを活用して調べてみると、自分たちの“普段の実感”とは違った事実が見えてきて驚くことがあるはずです。そこから、新たな好奇心というか、新たな視点を紐解いていくきっかけが生まれるんじゃないかな、と期待しています。
習慣としてのデータ分析で広がるインサイト
酒井:上原先生や古川先生は、様々な業界のことを研究されているからこそ多種多様な業界のことを知ることができるし、比較もできるようになる。では、研究者ではない人はどうすればいいかというと、データ分析を習慣化していくことが重要なんじゃないか、と考えています。
たとえば、消費財系企業のトップには、毎週一度は店頭を覗くようにしている、という人はたくさんいらっしゃいます。店頭を習慣的に覗くことが、何かを発見するための大きな暗黙知になっていくからです。
私は最近、音声SNSのClubhouseで「その場にいる人からお題をもらって検索データを分析する」というルームを定期的に開いています。これも、検索データで人を観察することを半ば強制的に習慣化する行為だと思っています。それぞれの立場でそうした習慣を持っておくといいのではないでしょうか。
上原:コロナで外にあまり出なくなったとか、売り場に行かなくなったとすると、気づきの機会が減ってしまうことにもなりかねません。データ自体はどんどん吸い上げられるんでしょうけど、現場というのは人によって見方が違うので、やっぱり自分の目で見たかどうか、というのが重要になってきます。
酒井:現場で実務を担当されている皆さんは、往々にして現場を回すことで精一杯。そのため、わずかな変化に気づくどころではないケースもよくあります。だからこそ、岡目八目的に現場に通って観察するマーケッターが気づけることも、その気づきから現場にフィードバックできることもたくさんあるんだろうなと思います。
古川:今やビジネス界隈で「DX」は避けて通れないキーワードですが、その一方で、データを拒絶する人、難しくて自分には扱えないものと決めつけている層も少なからず存在します。
でも、この本を読むことで、ビッグデータを扱うことのハードルを下げられるというか、グラフを重ねるだけでも見えてくるものがあるよ、という気づきを得られるんじゃないかと思うんです。いろいろな立場の人に、自分らしい分析にチャレンジしてもらえたらいいですよね。
酒井:データサイエンティストの周辺では、文系的な思考を持った人を求めていることが意外とあります。データサイエンティストの方々は、分析技術は持っているのに肝心のお題がない、という悩みを抱えているからです。お題があるのはビジネスサイドだったり経営学や商学の先生だったりするので、そこがマッチングできると非常におもしろいものができるんじゃないかなと考えています。
今やツールもデータもどんどん民主化されているので、ご自分の手元でデータを回してみると気づきが得られ、人に話すことでどんどんインサイトが広がっていくのではないでしょうか。
古川:今回はいい議論ができましたね。『デジノグラフィ インサイト発見のためのビッグデータ分析』、とてもおもしろい本ですので、多くの人に読まれてほしいと思います。
プロフィール

古川 一郎氏
武蔵野大学 教授/一橋大学 名誉教授/日本マーケティング学会 会長博士(商学)。武蔵野大学教授。一橋大学名誉教授。日本マーケティング学会会長。主な著書に、『マーケティング・リサーチのわな』『マーケティング・サイエンス入門』『地域活性化のマーケティング』『デジタルライフ革命』『超顧客主義』など。最近は、生活者の「多形化」をキーワードに、社会と企業の関係の変化と新しい関係を見据えたマーケティングの未来に関心がある。
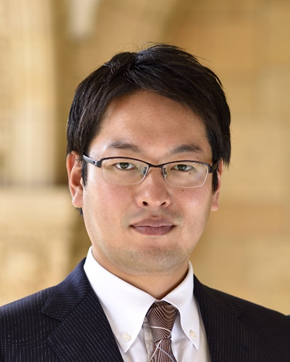
上原 渉氏
一橋大学大学院 経営管理研究科 准教授2008年一橋大学大学院商学研究科博士後期課程修了。博士(商学)。2016年から2018年タイのチュラロンコン・ビジネススクールで客員研究員。研究テーマは新興国におけるマーケティング組織と、消費価値の多形化。消費のIoTというコンセプトから新しいマーケティング・マネジメントのあり方を研究している。『日本企業のマーケティング力』(共著、有斐閣)や「ポリモルフィック・マーケティング」(『マーケティング・ジャーナル』)、「企業主導の単線型マーケティングの終焉」『マーケティング・ホライズン』。

酒井 崇匡氏
博報堂生活総合研究所 上席研究員2005年博報堂入社。マーケティングプラナーを経て、12年より現職。デジタル空間上のビッグデータを活用した生活者研究の新領域「デジノグラフィ」を様々なデータホルダーとの共同研究で推進中。行動や生声あるいは生体情報など、可視化されつつある生活者のデータを元にした発見と洞察を行っている。著書に『デジノグラフィ インサイト発見のためのビッグデータ分析』(共著)、『自分のデータは自分で使う マイビッグデータの衝撃』(星海社新書)がある。


































