KINTOが立ち上げ期に仕掛けた3つの施策とは?
サービス体験に価値を置くという点に関して、両社は共通した考え方を持っていた。では、具体的にサービスの普及や浸透を目指す上でどのようなマーケティング施策に講じているのだろうか。
KINTOでは、検索による流入数を伸ばすためにテレビCMやデジタルを使った認知施策に注力していたという。
「菅田将暉さんや二階堂ふみさんらを起用し『買うか、KINTOか。』というメッセージでCMを実施しました。そもそもクルマのサブスクがイメージできないということやKINTOという名前をまだ知らない方がほとんどであることから、知ってもらうことに重点を置きました。また、若い方に知っていただきたいということから同世代に支持されるタレントさんの起用を行いました」(藁谷氏)
テレビCMを放映した結果、ブランドの認知率が向上し、契約件数の底上げにも寄与。それに合わせて、3年契約のみだった契約期間に5年と7年を追加し、ニーズに合わせたプラン選択を可能にした。この契約期間のバリエーション増加も、契約数を伸ばすのに大きく貢献したという。
KINTOの認知を広げる施策に取り組んだ藁谷氏であるが、それだけにとどまらずオウンドメディアにも注力している。
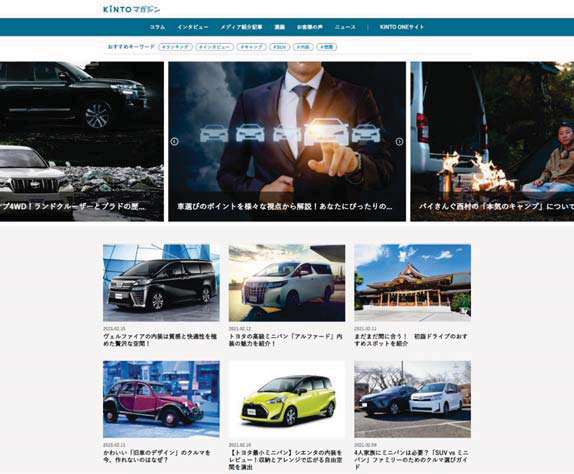
「テレビCMによる認知の効果も非常に大きいですが、まだ立ち上がって間もないサービスなので検索して深く理解してもらうことが重要です。認知して興味を持った方との接点として、オウンドメディアは非常に重要な接点だと考えています。KINTOのオウンドメディア『KINTOマガジン』では、クルマに関する直接的なテーマだけでなく、キャンプをテーマに芸人さんにインタビューを行うなど、様々なアプローチで日々コンテンツを公開しています」(藁谷氏)
また、クルマのサブスクリプションという枠を超えて、モビリティサービスのマーケットプレイスである「モビリティマーケット」を2021年4月にオープンした。「これにより、今後はモビリティという体験そのものの価値向上を目指す」と藁谷氏は語った。
醤油のサブスクは「リアルの体験会」が顧客開拓のポイントに
キッコーマン食品のBottleBrewは、サービスリリースからどのように顧客を開拓したのだろうか。
「BottleBrewは、リアルの体験会を開き丁寧にお客様に説明し、その魅力をご理解いただいた上でサービスインしていただくことを重視しました。リリース時は2019年で新型コロナウイルスの蔓延よりも前でしたので、レストランと組んでBottleBrewを体験できる発酵イベントも開催していました。コロナ禍の現在は事前にキットをお送りしてオンラインで体験会を楽しんでいただく試みにチャレンジするなど、おうち時間の充実に貢献できるような形にシフトしています」(花田氏)

利用前に体験してもらい、そこに価値を感じてサービスインにつなぐことを重視しており、ここで先に解説したKINTOの施策との違いについて、花田氏は次のように語った。
「醤油を作ってみたいという方は限られるため、マス向けにテレビCMを放映しても広く関心を集めるのは難しいと考えています。そのため、醤油作りに関心を持ってくれそうな方と深く関係を築いていくことを意識しました」(花田氏)
サービスに価値を感じ、継続的に利用することで顧客との結びつきを深めファン化を目指す。そして、ファンを起点に口コミやコンテンツの発信によってさらなる認知を拡大させていく戦略をとっているのだ。


































