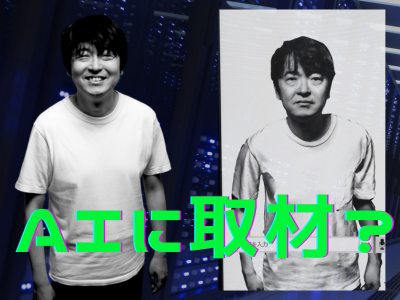「スマートであれ」というマナーが創造性を阻む

インテージとMIMIGURIは業務提携し、生活者リサーチとワークショップを掛け合わせた手法でイノベーション創出を支援している。本記事では、MIMIGURIの安斎氏、小田氏が翔泳社より上梓した『リサーチ・ドリブン・イノベーション 「問い」を起点にアイデアを探究する』の内容にも触れながら議論した。
小田:檜垣さんは、カゴメで商品開発やマーケティングを担当され、インテージへ移られて以降、ずっとリサーチに関わり続けていらっしゃいます。現在のリサーチの在り方、リサーチャーという仕事を、どのようにご覧になっていますか。
檜垣:現代の私たちの仕事には、「目標を立てて、到達までの道筋を明らかにして計画を立案し、最短距離で向かう」というマナーがあるように感じています。ご多分に漏れず、マーケターもリサーチャーも、そのようなワークスタイルになり、スマートになったと思いますね。
小田:確かに、限りなくムダを省くことができるようになり、様々なデータが取れる分、生活者をいかに精緻に掴んでいくかが求められている印象があります。それに従い、データから新しい価値を創るよりも、どこかその正確性を競い合う世の中になっているような気がします。
檜垣:マナーが、新しい価値を創りにくくしていると言えそうですね。安斎さんは、リサーチ・ドリブン・イノベーションの中で、「イノベーションが生まれない理由は、組織の探究的衝動が抑圧され、創造的自信が失われているから」と書いていらっしゃいますが、私はそれを「ビジネスから野性味が失われている」と読み取りました。
野性味というのは、人間理解の営みです。たとえばカスタマージャーニーを設計するときも、データの先にあるカスタマーの心理を捉え、新しい行動を促すところまでを考えたいものです。マーケターたるもの、やっぱり世に新しい価値を問うてなんぼの存在ではないでしょうか。

「リスク回避のためだけのリサーチ」ではもったいない
小田:長年、リサーチャーとして活躍されてきた鮎澤さんはいかがですか。ある種の窮屈さを感じるような体験が、実際にあるのでしょうか。
鮎澤:そうですね。データ分析の中で見えてきた問いに対し、どのように向き合うべきか迷うことはありました。調査報告の場では多くの場合「明確な答え」が期待されるので、明確な答えがまだない「問いの状態」であるものについては、今までとは見方を変える必要性などが気になりながらも、取り上げることができずにいました。
そんなとき、安斎さんの「問いの研究会」に参加し、「問い」をたてることの奥深さを知りました。私はアンケートの調査票を考える業務をしていますが、「問うべき問い」とは、知りたいことをそのまま聴取するのではなく、疑問を含めて気づきを得られるかが創造への第一歩ではないかと気づいたのです。
その後、一人の生活者の購買データを読み込み発想を拡げるワークショップに、安斎さんにご参画いただきました。対象は発泡酒のヘビーユーザーだったのですが、購買データを見ていくと、とある金曜日と12月24日だけはビールを買っている。そこから「このユーザーは、量的には発泡酒をたくさん飲むユーザーである。ただし、生活の中の“意味づけ”では、少量のビールの方に想いがこもったストーリーがあるのではないか?」という気づきがあり、「このユーザーを発泡酒のヘビーユーザーとラベリングして良いのか?」と疑問が生まれたんです。こうしたモヤモヤこそが、生活者を理解する上で大切なことだと気づきました。
安斎:購買データそのものに、人間味のある情報があるわけではありません。ですがデータを読み解いていくと、妄想や創造性を刺激され、対象に対する愛が立ち上がってくる。「このユーザーがもっと幸せになるにはどうしたらいいか?」という感情が、創造性とともに立ち現れ、相手を理解していくことにつながるんです。
スマートにマーケティングをしようとして、いつの間にか「お客さんはこんな感じだろう」と斜に構えて評する態度になっていないか。当事者不在で議論を進めていないか。野性味を取り戻した人間理解のために、データとワークショップで何ができるか考えてきました。
檜垣:リサーチャーにも同じことが言えそうです。データや数値を扱うぶん、クールな印象を持たれやすいのですが、本当はそれと同じくらい好奇心の塊を持っている人たちです。ですから、リサーチが、リスク回避の手段としてのみ用いられるのは、すごくもったいないこと。リサーチャーの好奇心の翼を羽ばたかせることが、新しい価値の創造に向けてはより重要だと思います。