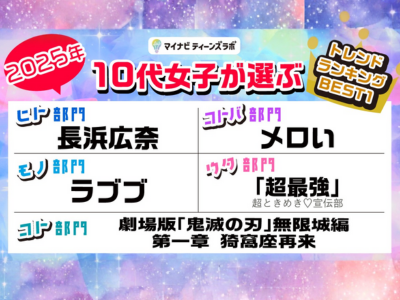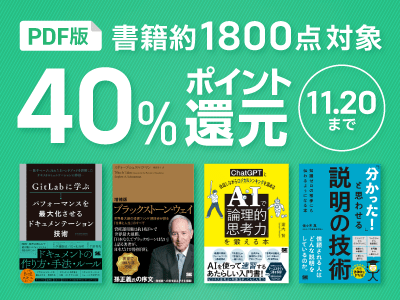顧客理解の大事さに気づけた「ラ・フランス」事件
廣澤:シェア需要という通常のお菓子とは少し異なる特徴を持つパイの実ですが、定番商品とは別に期間限定品も出していますよね。2月には「パイの実<贅沢とちおとめタルト>」も発売していますが、年間でどのくらいの期間限定品を出しているんですか。
久保田:年間で3~4くらいは出てます。私がパイの実ブランド担当になってからは10を超えると思います。
廣澤:商品の基本的な内容は一緒だとしても、10の企画品や派生品を作ってきたというのは、食品業界ならではのスピード感を感じます。ちなみに、その中で思い出深い商品というのはありますか。
久保田:一番思い出深いのは、私が着任して初めて出した「パイの実<ラ・フランスのご褒美タルト>」ですね。

廣澤:ラ・フランスですか、面白いですね。どのような味がするのでしょうか。
久保田:廣澤さんが今言った「どのような味でしょうか」というのが消費者の頭の中で浮かんでしまって、全然売れませんでした。失敗が一番思い出深くなっているのですが、でもこの経験が今の自分を構築してくれていますし、2024年のリニューアル成功の糧にもなっています。ラ・フランス事件のような出来事を、二度と起こさないと肝に銘じています。
廣澤:当時の自分を振り返って、ラ・フランスの味が売れなかった理由をどう捉えていますか。
久保田:顧客のことが本当に見えてなかったなと反省しています。社内コンサル的にいろんなブランドのマーケティングを支援してきて、そこからブランド担当に移って初めての担当商品だったので、なんとしても成果を上げたいという思いが先行していました。
それがこじれて、今まで出てないパイの実を出したいという思いも強くなってしまい、それが起点の企画がラ・フランスの味でした。
もちろん、ラ・フランス味で売れるのかは定量調査をして検証していましたし、他の商品と比べてリピート率も高かったので味もおいしいものができたと自負しています。でもどういう味かイメージできないため、トライアル購入してもらえなかったのです。
「ラ・フランス」事件以降、マーケティング思考はどう変化した?
廣澤:「ラ・フランス」事件の失敗を経て、10以上の商品を出していくわけですが、その中でコンセプト作りやマーケティングの考え方に変化はありましたか。
久保田:世の中やお客様が何を求めているか、以前より広く見るようになりました。どのような食品・味が流行しているのかはもちろん、食品業界に関係のないものでも流行しているものは片っ端から体験するようにしました。
そうすると、関係ない領域の流行であっても自分の業務にリンクする瞬間が出てきて、「この前体験したあれがプロモーションに活かせそうだ」「この前食べたあれが商品の着想になりそうだ」と新たなアイデアが生まれてくるようになりました。
廣澤:自分が扱う商品・サービス周辺の流行だけでなく、より広い視野を持つようになったとのことですが、とはいえ情報が飽和し、流行の移り変わりも早い中、久保田さんはその中からどのように情報を取捨選択しているのでしょうか。
久保田:意識せず気になったもの・ことはできるだけ体験するようにしています。また、パイの実のターゲット層は女性が多いので、自分自身はメインターゲットではありません。そのため、自分の妻だったり、ターゲット層に近い女性の声を聞いたりして、ターゲットの人たちが興味を持っているもの・ことに関する情報を集めるようにしています。