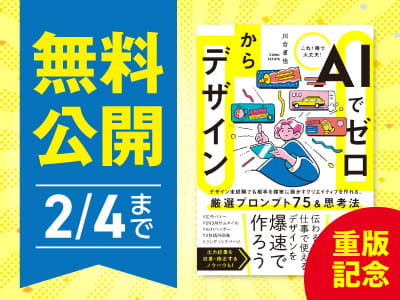コロナ禍を経て定着した今の価値観を探る
野村総合研究所(以下、NRI)は、2024年の8月に全国で15歳~79歳の男女個人1万人を対象として、訪問留置法で生活価値観や消費実態を尋ねる「生活者1万人アンケート」を実施した。同社では1997年以降3年おきにこのアンケートを実施しており、今回が10回目だ。
最新の2024年8月実施とその前回2021年8月実施の間には、いわゆるコロナ禍の収束期が含まれる。人々の生活には当然大きな変化があったが、それを経てコロナ以前のように戻ったもの/戻っていないもの、現在のスタンダードとして定着した価値観を確かめられるのは、今回の調査結果がもたらす大きな価値の一つだろう。
今回の講演ではNRIのプリンシパルの松下東子氏、同シニアコンサルタントの林裕之氏が、調査結果とその分析内容、見解を速報版として発表した。その冒頭でも、以下のような点が挙げられている。
- 「デジタル化がシニアを中心に加速したことで余暇の楽しみ方やチャネル利用、人付き合いの仕方が戻っていない」
- 「テレワークなど柔軟性の高い働き方を経験したことにより就業価値観が変わった」
メディア向け講演では、「1.生活価値観」「2.働き方・就業価値観」「3.余暇・チャネル利用」「4.消費価値観・消費スタイル」「5.情報利用行動」の5つの分野について、2024年に見られた時系列変化のポイントが紹介された。
景況感はやや改善するも拭えぬ不安
まず景況感に関しては、「家庭の収入に関して多少は回復したものの、やはり増税や円安、物価高の影響もあって、『生活者は景気の先行きを依然厳しく見ている』」というのが、松下氏の見解だ。

今年から来年にかけての家庭の収入の見通しについて「悪くなる」と考える人が前回の33%から30%へと減少。また家庭の状況に限らない質問として、今年から対年にかけての「景気の変化」に対する見方を聞いた場合についても「悪くなる」との回答が46%から34%に回復していた。なお、どちらもコロナ禍以前の水準には戻っていなかった。コロナ禍によって「多くの企業が倒産して立ち行かない」「この先日本どうなってしまうのか」などの不安感が大きかった前回実施時の状況からしても、「依然回復できていない」という見方のほうが正しそうだ。
家族や夫婦の在り方に変化 個人のキャリアを優先
また、生活価値観の変化を時系列で見ていくと、景況感以外にも様々な分野で変化が現れていることがわかる。

傾向が強まる「伝統的家族観からの脱却」は、ファミリー層を想定した商品ブランドの見直しや顧客の再定義の契機になりうるトピックだろう。また夫婦に関しても、「お互い経済的に自立したほうが望ましい」「秘密を持っても構わない」「自由時間の使い方に干渉するべきではない」など、旧来よりも余裕のあるべき関係として捉え直されているようだ。
「家族の形よりも個人の選択、個人のキャリアを重視するような価値観になってきています」(松下氏)
結婚について直近の3年間の変化を見ていくと、結婚したほうが良いとする価値観は2021年時点で女性側を中心に大きくダウンしており、続く2024年調査では女性30代以上でさらに減少した。
他に「興味深い変化」として挙げられたのが、「隣近所との干渉を避ける」傾向の強まりだ。お互いに干渉しないほうが良いとするコロナ禍の価値観は2024年でも継続しているのだという。コロナ禍でも家族、離れて暮らす親といった関係性では連絡を密に取り合う傾向も見られたようだが、隣近所、職場の知り合い、子ども関係の知り合いといった人付き合いの中でも“辺縁”部分に関しては希薄となり、それが2024年でも下がったままなのではないかと見解が示された。
一方、以前のほうが強かった価値観では、「自分で事業を興したい」「まわりの人から、注目されるようなことをしたい」「より良い生活のためなら、今の生活を変える」など、変化の受容や挑戦をあらわす価値観が下がっていると松下氏は指摘する。