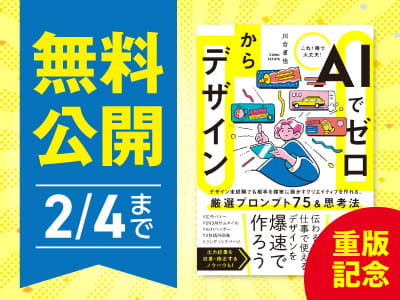10年かけて構築したデータ基盤とクラブ横断のCRM活用
飯髙:顧客理解を大切にすることがわかります。Jリーグでは、どのような流れで顧客起点の取り組みをしているのですか?

竹渕:2016年までにデータベースを開発・整備し、2017年にJリーグIDをローンチしたことが分岐点になりました。そこからCRM施策の推進をしてきて、特に2023年からは脱コロナ期として顧客体験最適化に動いています。

小森:現在は9segsの下層から上層まで、各種データをJリーグIDで紐づけて管理しています。システムだけではなく、年に数回、全60クラブが集まって人材育成講座をしたり、Jリーグから派遣されるクラブサポート部が中心となり、クラブごとのマーケティングデータベースの活用をサポートしたりしています。
飯髙:なぜ全クラブのデータを1本化したのでしょうか?
小森:ホームスタジアムに来場した方がアウェーにも来場され、そこからコアファン・サポーターになっていくステップもあると考えたためです。ホームクラブでもアウェークラブでも同じツールを使っていることで、他クラブの成功事例をすぐに取り入れやすいですし、比較もしやすいので、自クラブの改善点も見えやすくなります。
4人に1人が試合に3回来場する、大規模招待施策
小森:認知関心のフェーズでは、コンテンツ強化・メディア露出強化をしています。ローカル中心に地上波中継も数年で4倍ぐらいになっています。関心を持っていただいた方に試合へ来ていただくために、大規模招待施策と国立競技場の活用をしています。
飯髙:招待施策はどのような設計になっているのでしょうか?
小森:基本的に招待に応募するためにはJリーグIDにご登録をお願いしています。各クラブのお気に入り登録をしていただくことで、クラブのCRMのリードの獲得につなげています。

招待で来場した人が次につながらないと意味がないので、2回目、3回目にどれだけつながっているかを重視しています。国立競技場のキャンペーンであれば、2回目来場が32%、3回目が16%、全国のスタジアムでの大規模招待が2回目来場44%、3回目が25%になっています。つまり4人に1人は3回目来場につながっているので、各クラブのCRMがうまく届いていると判断しています。

竹渕:紙のチケットを渡すのはバラマキだと思っていますが、IDと紐づけてデジタルで実施することで、顧客になってもらうための1つの接点として、クラブが丁寧にCRMを行っていくことができます。
そして招待施策を通して初めて来場された方には、試合終了後に試合のハイライト動画をお送りし、少し時間を置いて関連コンテンツの情報を提供します。さらに期間が経った絶妙なタイミングで「もう一度来ませんか?」とアプローチするなど、非常に丁寧で"愛のあるCRM"ができるようになったと感じます。