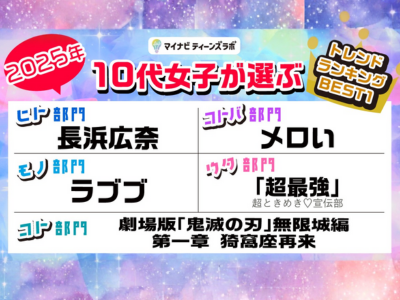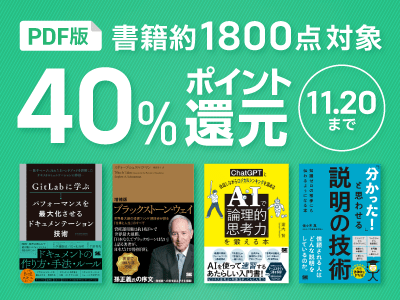Q 畑違いの分野での企業にあたっての工夫は?
立ち上げ当初、東京23区内に絞って葬儀社を1社1社調査していきました。電話して、訪問して、実際に行う葬儀を見てということを繰り返しましたが、当時は葬儀社紹介サービスはかなり珍しいモデルでしたので、サービスの趣旨を説明してもなかなか理解してもらえませんでした。
Q 葬儀業界の知識はどのように高めていったのでしょうか?
事業を立ち上げるにあたり、実際に葬儀社の仕事を無償で手伝うなどして、どんなお仕事なのかを少しですが経験させて頂きました。
もちろん、書籍や葬儀ディレクター試験のテキストなどでの勉強も行っていますが各地でしきたりや慣習も違い、それぞれにご要望も違うので、やはり経験が最も重要になってきます。これまで13,000人を超える方々から葬儀の相談を受けてきておりますが、全て一人ひとりデータベースに記録を残し、相談スタッフが常にその履歴を見ながら相談対応できる体制を整えています。
ただし、素人目線を忘れないこともとても重要な要素だと思っていますので、葬儀慣れせず、葬儀社目線にならず、常に利用者としての気持ちや意見を葬儀社にぶつける、ということを意識しています。
Q 他社との差別化・競争優位性はどこになりますか?
いくつかありますが、まとめると下記3つだと思います。
- ご紹介した方の葬儀に相談スタッフが立ち会うこと
- 蓄積されたアンケート
- 多岐にわたる集客ルート
2003年に立ち上げた当初は、インターネット上で葬儀社紹介サービスを探しても皆無でしたが、今では同じようなサービスがたくさん立ち上がっています。しかしながらそれらの多くは葬儀社が別会社として運営していたり会ったこともない葬儀社を紹介し、マージンをとるような会社がほとんどです。
「ご紹介した葬儀に立ち会う」という当たり前のことをしている会社が葬儀サポートセンター以外にほぼ無いのが現状であり、一番の差別化になっていると思います。
また、アンケートも1500通を超えており、どの葬儀社の、どの担当者がどんな性格で、どのような対応をしてくれるかというタイプ別のご紹介が可能となっています。
Q なぜ「葬儀に立ち会うこと」が差別化になるのですか?
葬儀に立ち会うことは、良い葬儀社を紹介する上で必要不可欠なことだと思います。どんな担当者がどんな価格設定で、どのようにお葬式を行っているのかを見たことも無いのに、ご相談者様に対して説明やご紹介するのは相当無責任だと思います。
葬儀社のことを良く知らずに紹介を行うことは、無知な消費者をだましている行為だと思います。
立会いに出向くことで、葬儀社のタイプや担当者の人柄などを把握でき、よりマッチしたご紹介ができると考えています。
喪主様にとっても、私共が立ち会うことで、より一層安心していただけることも多く他社ではないサポート体制だと思っています。